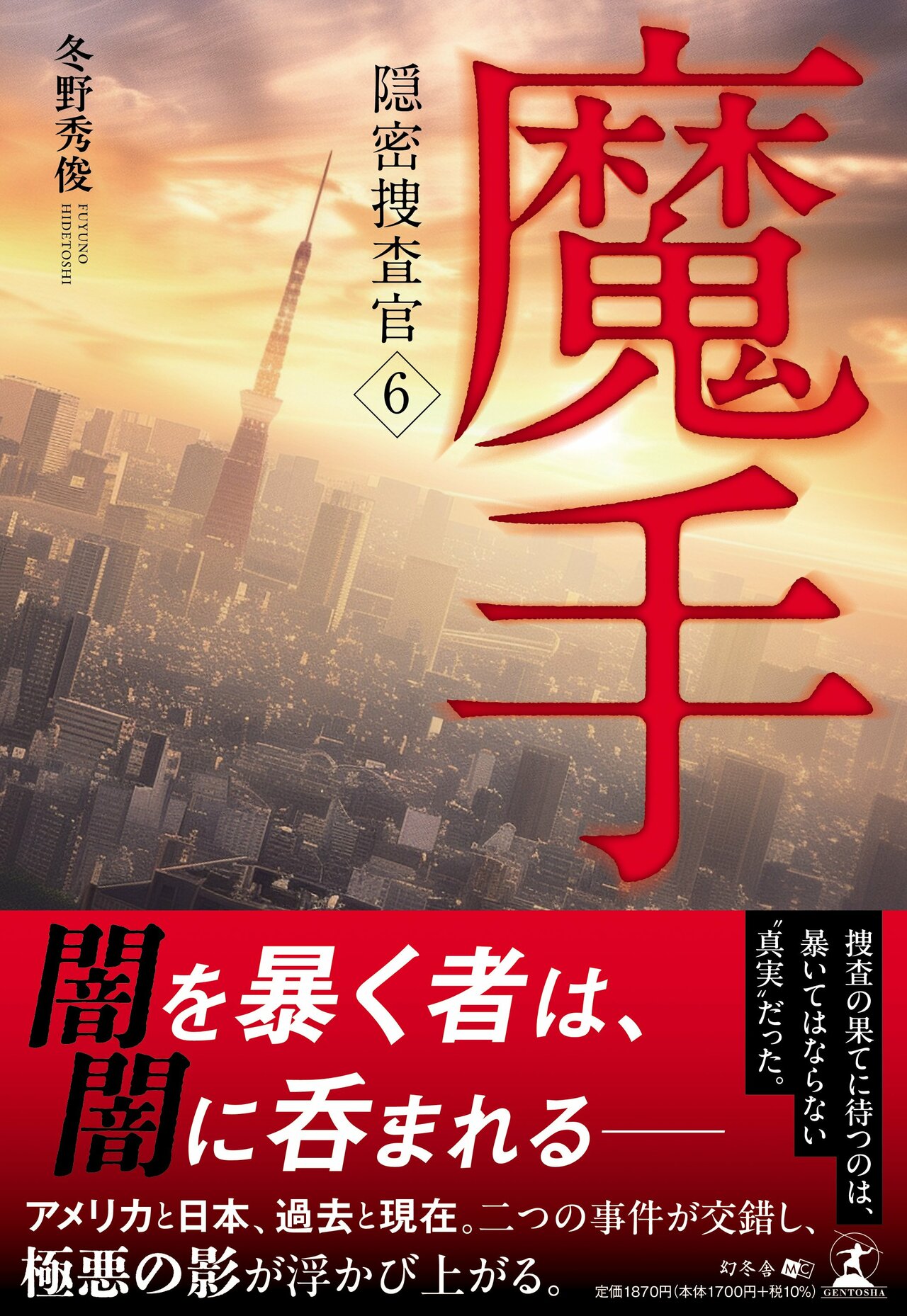「僕らの行動は、すべて把握されているようだ」ドアの片側に陣取った清一が言った。
「清一さんが襲われた時、すぐ警察には連絡したわ。間に合うといいんだけれど」
不安顔のスージーだったが、随分経験を積み重ねてきているだけあって、どこか余裕があった。
二人が、警察が到着するまで十分くらいはかかるだろうと話していると、けたたましい靴音が近づいてきた。そして、ガチャガチャ、ドンドンという音が続いた後、
「いるんだろう、出てこい」
清一たちは、侵入を防ぐために二台のテーブルでドアを抑えていた。遅かれ早かれ突き破られるのは分かっていたが、少しでも時間を稼ぎたかったからだ。拳でのノックが足蹴りに代わり、体当たりでもダメとなると、次は発砲しかなかった。
ドアが少しだけ開いた。しかし、清一たちは諦めるわけにはいかなかった。必死でテーブルを押し返し、警察が到着するのを待たなければならなかった。
バーン、銃声が鳴り響いた。それでも、スージーともども命を繋ぐには、歯を食いしばるだけだった。
反撃する手立てのない清一たちが抵抗を続けてしばらくすると、静寂の中から声がした。
「大利家戸さん、僕です。安心してください」
ドアの向こう側から叫び声が聞こえた。ポートランド市警の若手刑事だった。
清一とスージーは、顔を見合わせた。それは、何とか危機を乗り切ったという安堵からだった。二人は事情聴取を済ませると、十五階にある部屋へ戻った。
今度の襲撃も前回同様清一を狙ったものだと推測はできたが、どうして、清一をターゲットにしたのかまでは分からなかった。
そのため、清一は部屋に戻ってから眠ることができなかった。スージーの依頼でポートランドへ来ただけなのに、再三にわたって命を狙われたからだ。単純に考えれば、スージーたちが追っている一味が清一の参加を疎ましく思っての犯行なのだが、一概にそう割り切れない何かがあった。
【イチオシ記事】マッチングアプリで出会った女性と初デート。新橋にほど近いシティホテルのティールームで待っていると、そこに現れたのは…