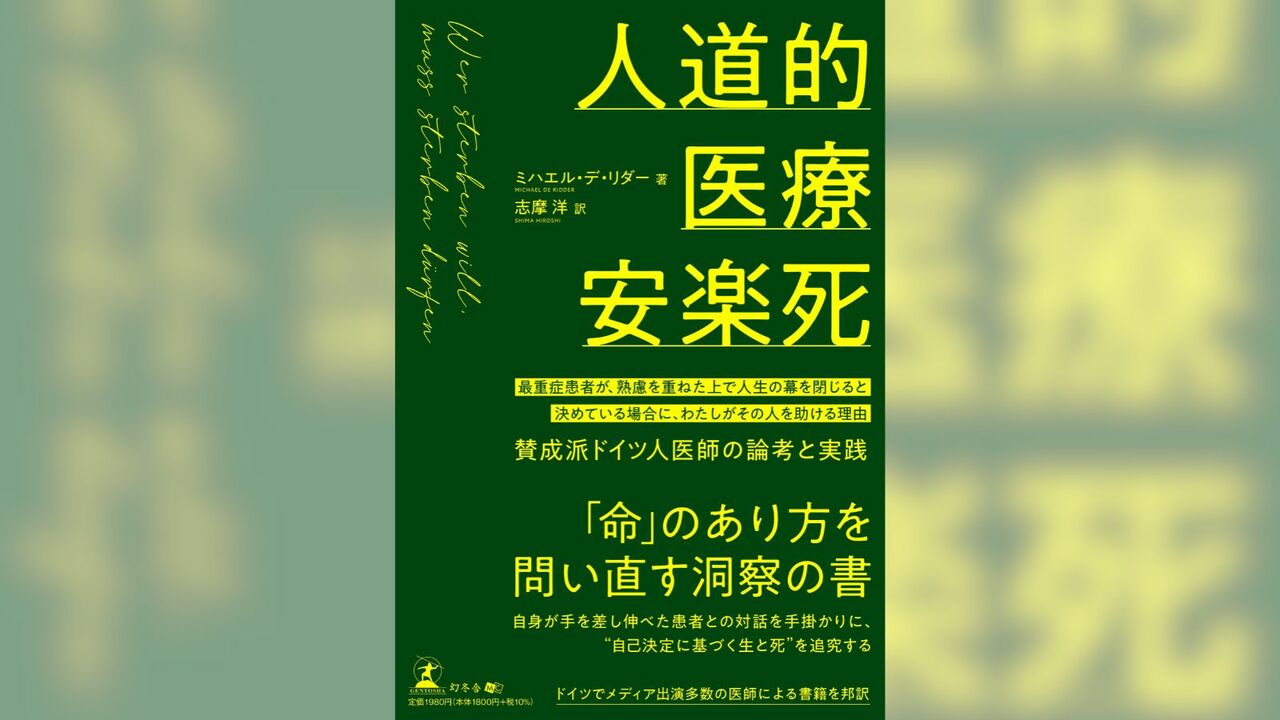【前回の記事を読む】本人の希望に従って、苦痛の少ない方法で死に至らせる——ベテラン医師が唱える、"人道的"な安楽死とは
第2章 序文にかえて
―この本を書く動機と正当性
その一方で、わたしは、苦しんでいる患者さんに対しては、可能な限り最善の医療処置を施すだけではなくて、言葉には出さないにしても、多かれ少なかれ、人間的な処置を期待していたのである。病気の身体的な側面だけではなく、それを超えた苦しみの体験に耳を傾けることは、昔も今も、患者さんが主治医に望んでいることではないだろうか?
注意を込めて、患者さん自身の資質に配慮しながら、それを強化するために「元気を出してね、大丈夫だから……!」というたったの一言が、大きな慰めを与えるのではないだろうか? この言葉は、当時も今も大きな価値がある言葉である。
患者と医師の関係は、わたしが医学の道に入った1970年代の後半には、まだパターナリズム(父権主義)が蔓延していたが、今日では、お互いの目の高さの関係にその道を大きく譲っている。少なくとも、自己決定が主張されて以来、患者の自己決定が、医師と患者の関係の中心課題へと変わっていったのである。
わたしが見習いをしていた当時は、医学的な命令や禁止が患者さんとの対応の大部分を占めており、それが一般的であった。
ある治療法が医学的に正当化されている場合には、医師が患者に恥をかかせたり、制裁を加えたりすることをはばかることがない時代であった。「自分のお腹をしっかり鏡で見てごらんなさい。もし、ここで処方された食事療法を守らなければ、この病院から出ていってください!」というような具合であった。
医学、特に印象に残っている集中治療医学の成果と、そこで起こり得る欠陥との間の大きなギャップは、わたしが最初に助手として働いていた時から今日に至るまで、ずっとわたしのこころに異様な苛立ちを残していた。この矛盾は、今も昔も変わっていない。
その考え方は、「できる限りのことをします!」という文言に象徴的に表れている。この紋切り型の文言は、特に、生命を脅かすような急性疾患(例えば、裂傷、心臓発作)においても、希望と自信を与えて医学の可能性を最大限まで引き出すことを約束する文言である。
その一方で、この文言は「これ以上やることはありません!」と言い放っていた。この言葉は、長い努力の末に、もはや助かる見込みがない場合には、患者さんを見捨てることを意味している。つまり、医術が失敗したことを認める文言なのである。
治療が無駄であったことがわかった時に、それ以上のことはできないというのは、死に逝く患者さんを無視することに他ならない。
そのような治療やケアは、牧師や親族や介護者だけに任せてきた医療体制の棘のように、早くからわたしのこころに突き刺さっていた。わたしは苛々していた。この棘は、最初は潜在的な意識であったが、今ではわたしにとって、医療の主たる関心事になっている。
絶望的な病気であっても、医学は、苦痛を和らげるという意味で、常に何かを提供することができるし、もっと正確に言えば、何かを提供しなければならないのである。しかしながら、ドイツの医療関係者が、緩和ケアが倫理的にも治癒的ケアと同等の価値があって不可欠であることを認識するに至るまでには、数十年の歳月が流れていた。
因みに、緩和は、痛みの緩和だけではなく、それをはるかに超えている。それは今日に至るまで、現実というよりも、約束のようなものである。緩和医療は広い意味で患者さんを包み込むことであり、今では、それが医療活動の中核となっているのである。わたしは、2012年にホスピスを設立し、今日に至るまでその運営に携わっている。