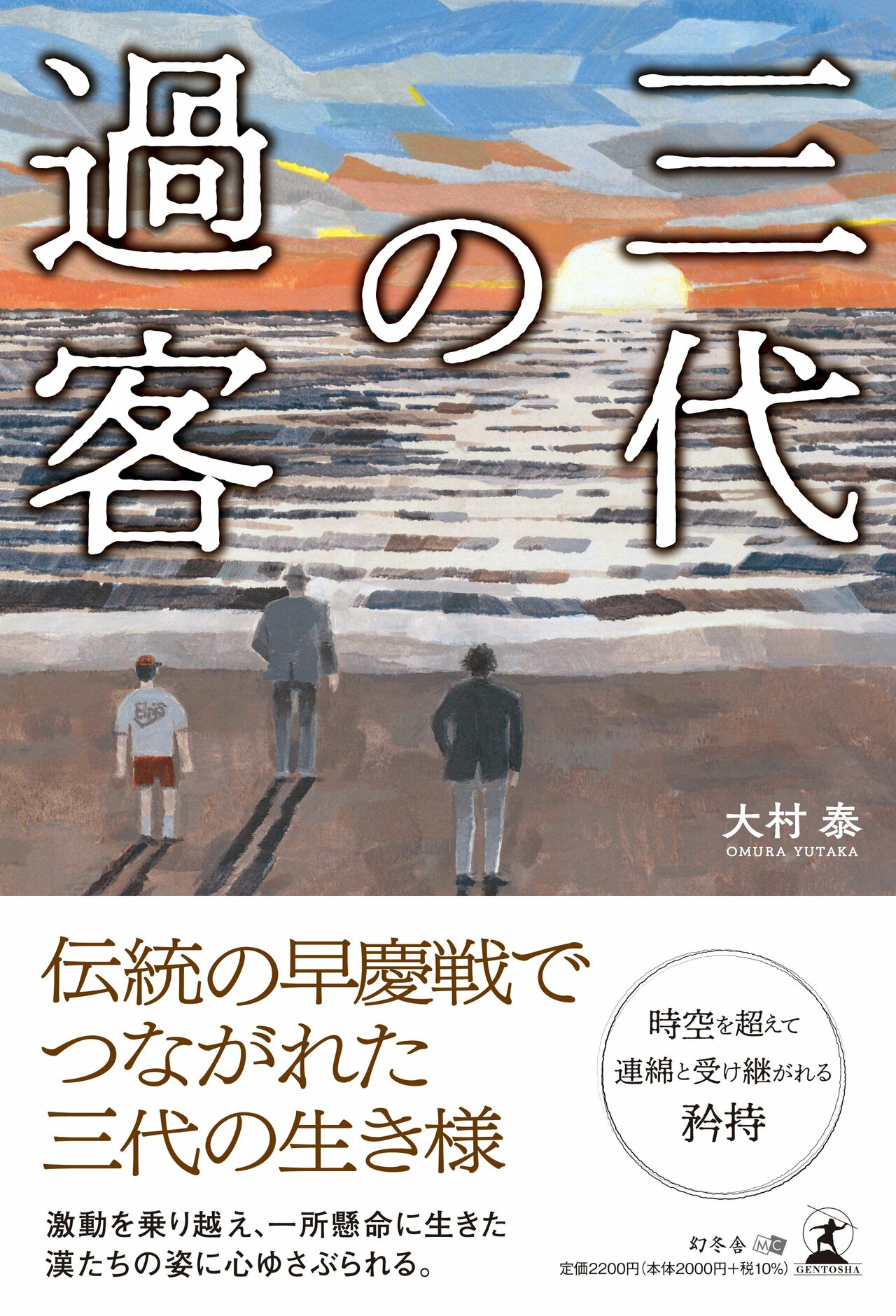八月二十三日、夏の甲子園決勝戦
WBCから五か月後。同じ祖父・父・息子の三代が阪神甲子園球場の三塁側内野席の上段に陣取っている。抜けるような蒼穹(そうきゅう)を白球が切り刻む。カキーン! 快音の残響。打球は満員のライトスタンドに突き刺さる。
夏の高校野球決勝戦では初めてとなる慶応高校の先頭打者ホームランで幕が開く。昼過ぎの日差しが光と影の境をくっきりと分断する。その境界線が時々刻々と移動していく。選手たちは試合終了まで光のステージのなかにいた。お日さまも舞台にスポットライトを当て続けることに手を抜かない。
埋め尽くす観客の大音響。サラサラヘアの宇宙一幸せな選手たちがグラウンドで躍動する。着々と点を稼いでいく。二枚看板の投手が失点を最小限に抑える。四つも失策したって彼らの心は決して折れない。部訓に掲げる「エンジョイ・ベースボール」のなせるワザなのか。
悠真は、ともに馳せ参じた諭の高校野球部時代のチームメイト塚田駿平の息子と肩を組んで応援歌「若き血」を歌ったり、点が入るとハイタッチを交わしたりしている。
彼らは九人でまとめて席を取り、家族あげて集まった。平日なのに夏休みを取り大挙して押し寄せた恐るべきチームワーク。
九回裏。最後の打者を打ち取る。八対二。マウンドに駆け寄るナイン。晴れがましきチームワーク。
「おめでとう、ありがとう」。満場の観客は大声援を惜しまない。高齢のOBがつぶやく。「生きているうちにこんな光景が見られるとは。長生きしてよかった」。
大正五(一九一六)年以来百七年ぶりの全国制覇だ。慶応高校野球部の部訓である「日本一になろう」と「エンジョイ・ベースボール」が二つながら結実した瞬間だった。
【イチオシ記事】「いい?」と聞かれ、抵抗なく頷いた。優しく服を脱がされてキスを交わす。髪を撫でられ、身体を撫でられ下着姿にされた。そして…
【注目記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。