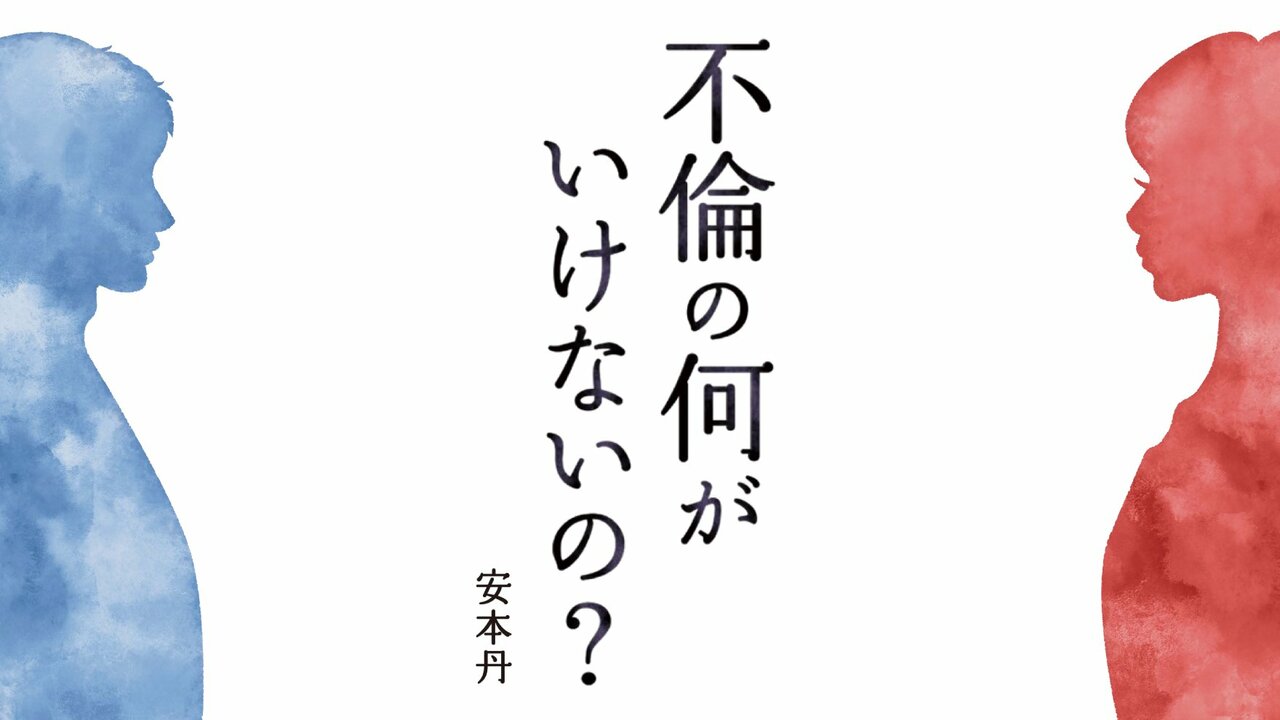第四章 主従関係
付き合ってしばらくは私とハギの交際は恐ろしいほどに順調だった。私はハギに激しく恋をしていた。しかしヒロキに振られた反省を活かして彼には執拗に会いたいだの、好きだのは言わないようにしていた。
会えない日、連絡の来ない日、ハギは一体何をしているのか気になって仕方がなかった。もしかして他の女子と遊んでいるかもしれない。私のことなんてどうでもよくなったのかもしれない。そんな不安に押しつぶされそうな日もあった。
しかしまた重いと思われるのが怖かった私は、自分の感情をしばらく抑えていた。そん な私の態度に彼も、本当に自分のことが好きなのか疑ってしまうほどだった。お互いが探 り探りのまま月日を重ねて、徐々に私は彼に自分の想いを伝えていった。
すると彼は私の好意を、その全てを真っ直ぐに受け入れてくれた。重いと言われ傷ついた過去、それがトラウマとなり、気持ちを伝えることが怖くなっていることも話した。
「僕はどんなことをされても絶対に重いなんて思わない。会いたいと毎日言われるなら応えるし、どんな伝え方でも愛されていることが伝われば嬉しい限りだよ」
そんなハギの言葉に私は甘えた。情熱的でロマンチスト、溢れる想いを様々な手段でとにかく伝えたくて堪らない私にとって、彼はまさにうってつけの存在だった。
ハギは人に嫌われることを異常に恐れている人間だった。もちろんそれは私に対しても例外ではない。私に嫌われたくない彼は、私の言うことをなんでも聞いた。
夜中に急に会いたいと呼び出しても、デートの待ち合わせで二時間以上待たせても、彼は怒らなかった。私は彼といれば、いつだってお姫様でいられた。それがいつのまに女王様になってしまったのだろう。
私は次第にハギのことを人として対等には見られなくなっていた。最初は何でも言うことを聞く彼に、優しさを感じていた。
しかし徐々に彼が私の言うことを聞くのが当たり前になっていった。いくつもワガママを言いながら、私はコップに少しずつ水を注いでいる気分がした。この水が溢れる時はいつだろう。
始末の悪いことに、ハギもまた私のしもべであることにある種の快感を覚えていた。私の要求を叶えることで自分は必要とされている、愛されているのだと実感できる。