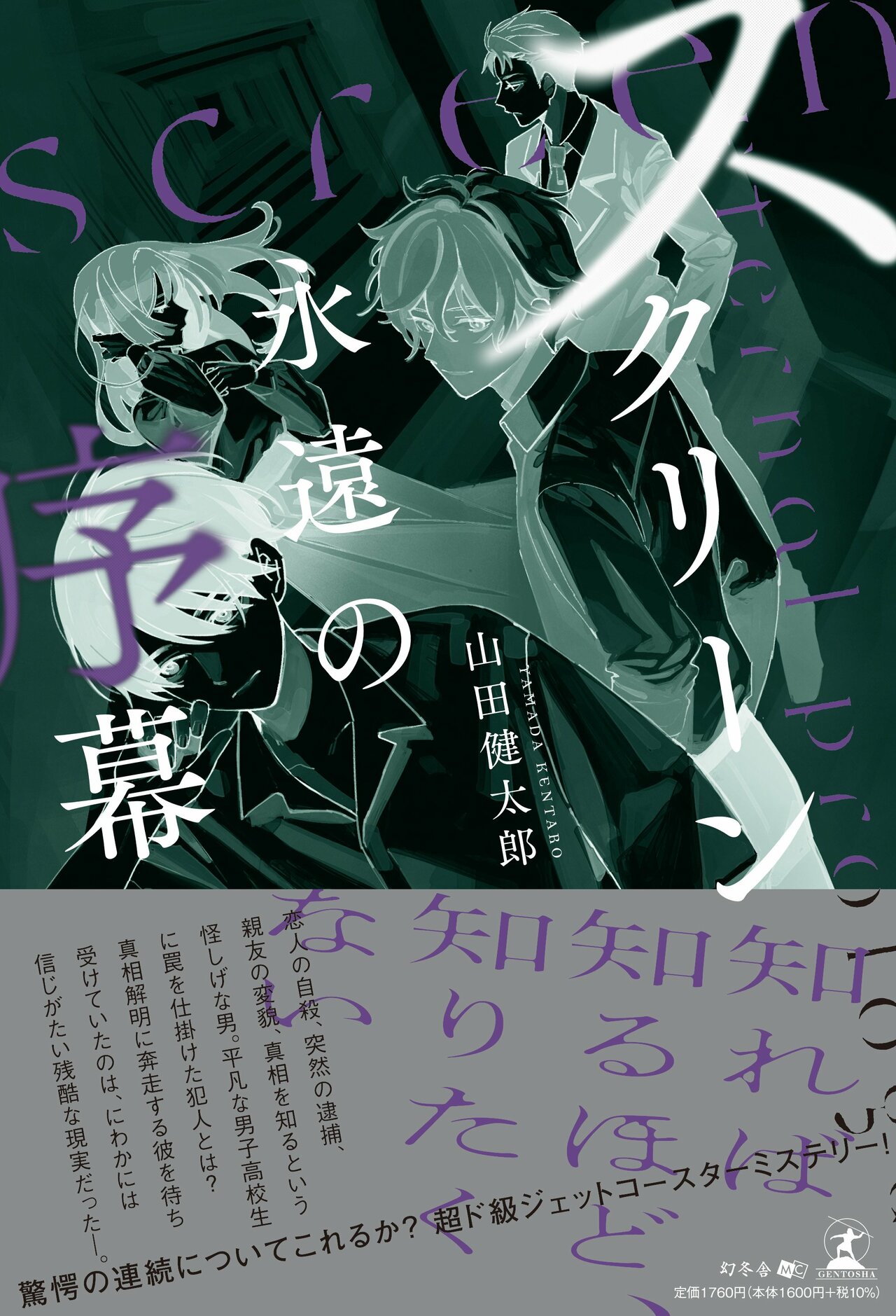帰り道はしばらく車の走る音すら聞こえなかった。そして感じたことのない気持ちに支配され、ただただ棒のように歩いた。
理由はたった一つ、俺には商品をバッグの中に入れた自覚があったのだ。
「蒼斗」
静寂を裂いたのは母さんだった。しかし、すぐ親父が切った。
「なあ、美和。俺たちが自分の子供を信じないでどうするんだ?」
母さんは戸惑った。
「蒼斗、俺たちはこれ以上何も聞かない。家に入るときはいつも通り『ただいま』って言うんだぞ。家ってのはな、笑って帰る大事な場所なんだ。父さんは蒼斗を信じている」
親父の優しさが俺の心を完全に貫いた。その日の夜、恐怖に怯(おび)え、裏切りという重圧に潰されながら過ごした。罪悪感は消えるどころか瞬く間に増幅していく。
結局、翌日には万引きした高柳商店の前に来ていた。
「おじさん。俺、ごめんなさい」
ここまでで言葉に詰まってしまった。
「うん、よく来たね」
おじさんの声色に徐々に視界が滲(にじ)んだ。そっと目線を上げるとおじさんの顔は穏やかでとても温かかった。
「君のお父さんは嫉妬するくらい立派だった。でもね、君も勇気を出して今日ここへ来た。負けていないよ」
激怒されるより優しくされるほうが心を強く掴む。この後、両親と共に店に謝りに行ったのだが、両親が頭を下げている姿は今でも鮮明に覚えている――
こんなことがあったのに、親父はまた俺を信じてくれた。そして、母さんは親父に倣って俺のことを信じ切った。込み上げる思いにこらえられず二階へ駆けあがる。日常生活の大切さを知り、そして改めてその当たり前の生活に戻ることができた。嬉しくて、幸せでこんなにも涙が流れるのに、結局親父と母さんに「ありがとう」の一言が言えていない。
じっと天井を見ていると、不可思議な感情が生まれた。
意として泣きたい。
布団を被ってすすり泣くと涙が止まらない。声を出さないようにしても口から漏れる。その口を必死に両手で押さえて泣く。こんなにも自分の口を覆って泣いたことがあっただろうか。
誰にも知られずひっそりと流す涙、この涙には計り知れない力があった。