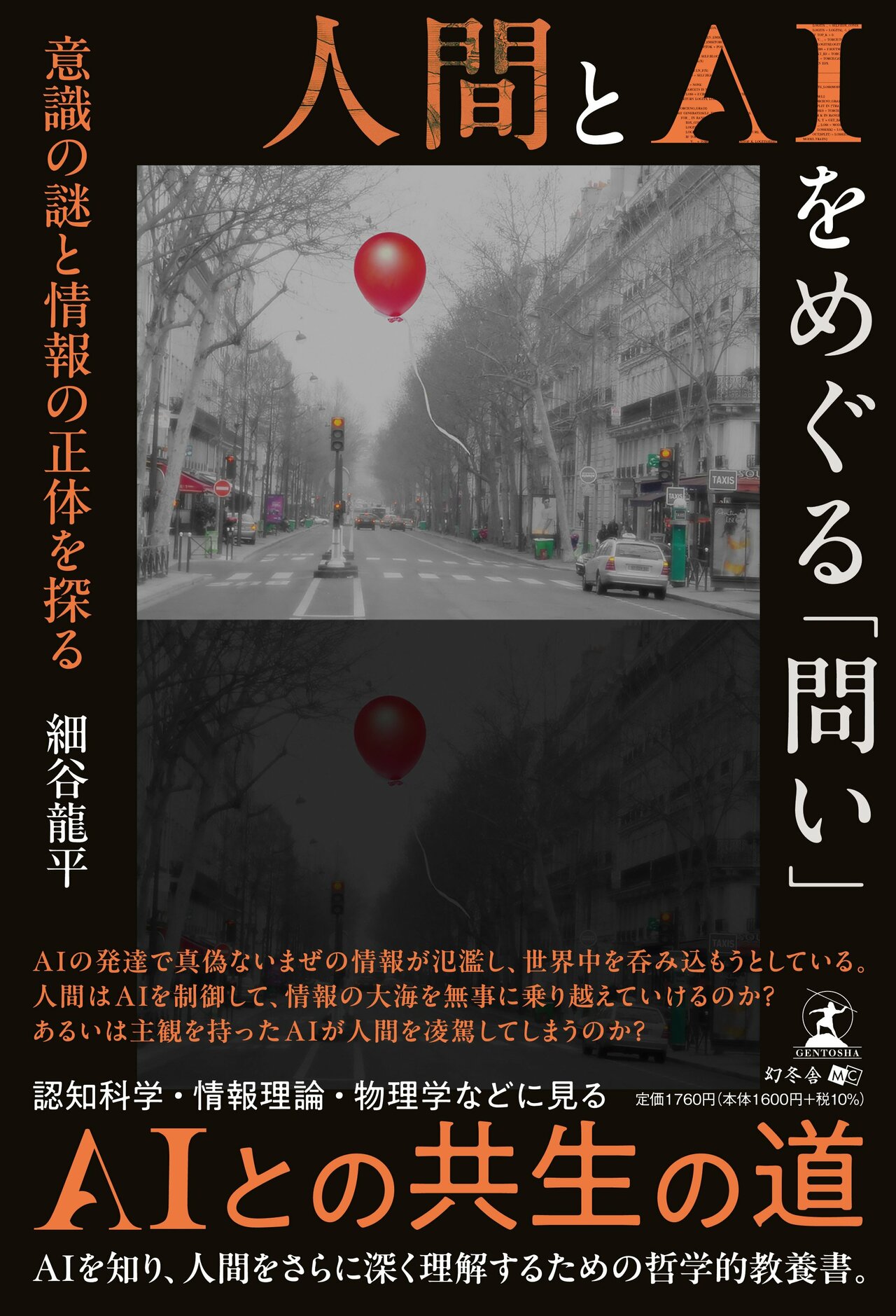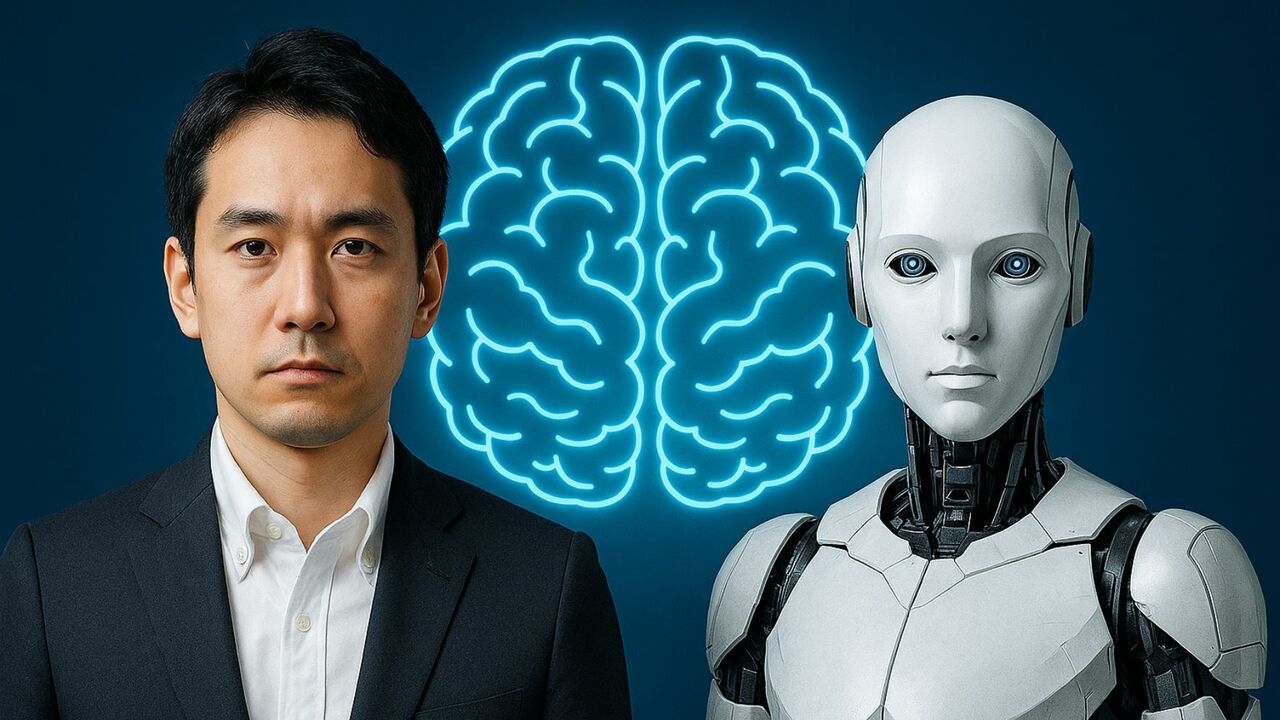一方で、このように大きなメリットをもたらし得る技術革新の芽は摘むべきではなく、リスクを適切に管理しながらもその開発は推進していくべきである、私たち人類はAIの優れた能力を活かして、適切な(当然、私たち人間にとって適切な)共生関係を築いてその恩恵を最大限享受していけるであろうといった楽観論もあります。
それは、私たちが「車のハンドル」を自ら離してしまうような愚は犯さず、主従逆転は起きない、いや起こさせないという強気な楽観論です。
政策当局者のレベルでは、警戒的な立場からすでに包括的なAI規制法を成立させているEUに対して、トランプ大統領が返り咲いたアメリカは強気なAIの自由開発促進の方向に舵を切っています。日本は今ようやく両方のバランスを取ったAI戦略の策定を目指しているところです。この間に中国は国家レベルでAIの開発を強力に進めており、アメリカはこれに対する警戒を強めています。
かつて核兵器の開発や宇宙の探査が米ソ両大国間の競争によって加速したのと同様に、現在はAIの開発競争が、米中の覇権争いと、その他の主要国を含む合従連衡(がっしょうれんこう)の構図を決定付けるかもしれない政治戦略要因となっています。
また一部の巨大IT企業間での技術的、経済的優位をめぐる競争は、ともすると十分な歯止めなきAI開発をさらに突き進め、遠からずAIによる暴発的な独り歩きを許してしまいかねない恐れが指摘されています。
国際政治や経済の問題に踏み込むことは本書の目的ではありませんが、AIが人間と社会の利益に沿う形で適切に開発されていく方途と、そのために必要なAIのリスクコントロールのあり方は、国家、企業の枠を超えて、客観的・中立的な検討に基づく国際的な合意形成が求められる人類共通の緊急課題だと言っても過言ではありません。
今一つ重要だと思われるのは、人間とAIとの関係が将来どのような方向に進むとしても、人間の存在のあり方は大きく変わっていくのではないか、否すでに変わり始めているのではないか、それと同時に社会、ひいては世界のあり方はどう変化していくのかという視点です。
これは究極的な未来についての空想ではなく、意外に遠くない将来への問いかけであることが、AI開発の最新状況と先端の関係者や識者の論調から窺えます。
【イチオシ記事】彼と一緒にお風呂に入って、そしていつもよりも早く寝室へ。それはそれは、いつもとはまた違う愛し方をしてくれて…