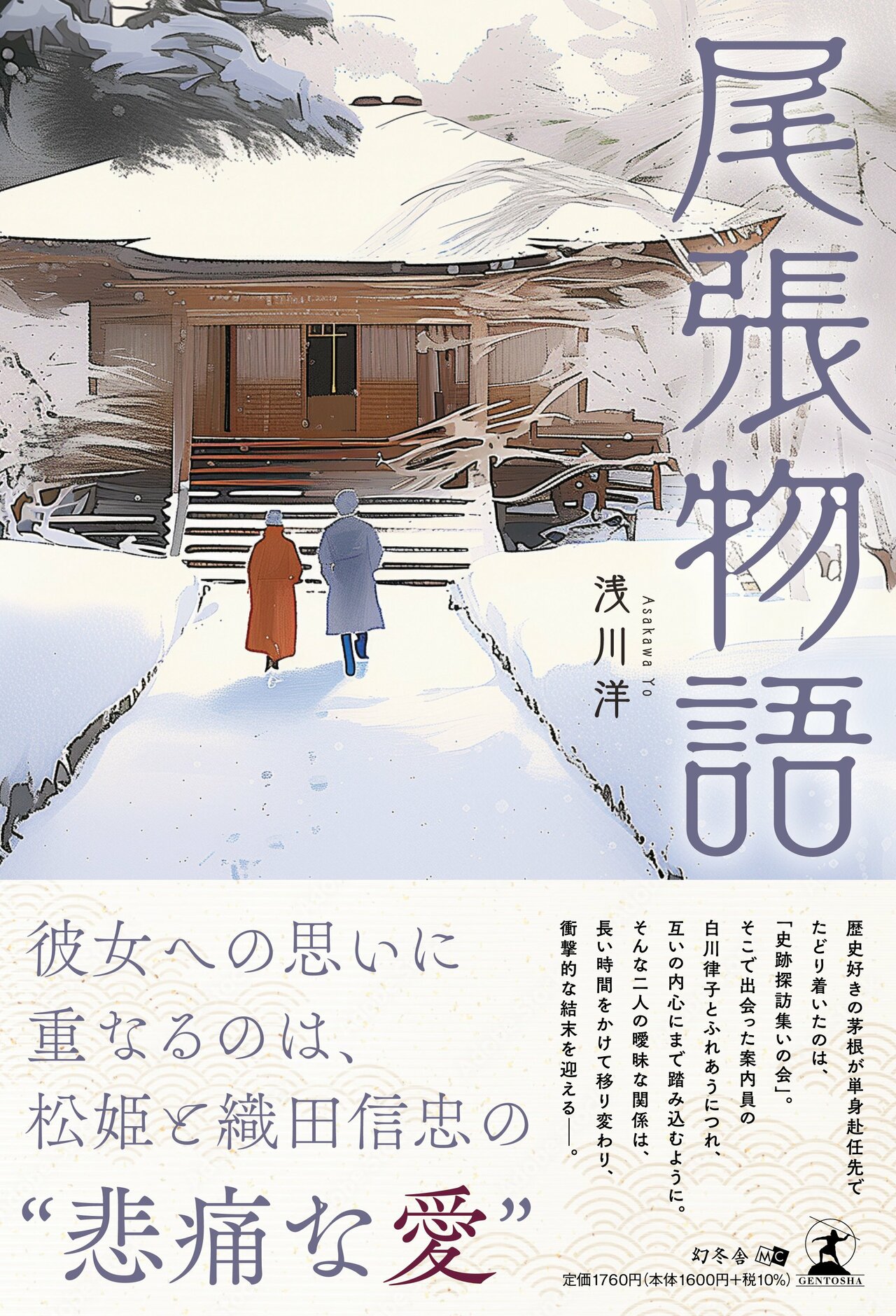第二章 分岐点
茅根が五十六歳の時だった。会社の人事部から転籍の話があった。転籍は社外の企業を会社が斡旋する制度だが実質リストラだった。茅根は保険会社の営業マンであったが、現在は内勤部門に配属されていた。
茅根は転籍を辞退し、早期退職を希望した。早期退職は退職時に一年分の給与を退職金に上乗せしてくれた。しかし早期退職は、あくまでも具体的な起業計画を持っているとか、身内などが経営する事業の後継者になるとかの理由があった場合に認められていた。
茅根は五十代に入ってから退職後のことを考え出していた。老後の生活資金は年金だけでは十分とは言えないが、できたら何にも縛られずに自由にやりたいと思い、随筆や作文をパソコンに書き留めていた。
ことに歴史に興味があり、雑誌などの募集に応募し掲載された時もあった。会社はその点を大目に見てくれ早期退職を認めてくれた。妻の知加子は「あなたは一度決めたら変えないでしょう。あなたが決めたのなら、それでいいんじゃない」と言ってくれた。
退職日付は十二月末だった。その日、社内の挨拶回りを済ませ席に戻ると、職場の同僚から花束の贈呈があった。帰宅して、玄関先でその花束を知加子に渡した。知加子は「長い間ご苦労様でした」とねぎらいの言葉をかけてくれた。
二十四時間が自分のものになった。ついこの間まではスケジュールや目標を立て実行することが日常茶飯事だった。しかし、自由業になった現在、集中力は散漫になっていた。身体の衰えは明白な事実だった。清く澄んだ渓流にも似た、生き生きとした血液に満たされた肉体は二度と戻らない。
茅根はどういう風の吹き回しか、かつて自分の仕事場だった新宿に足を向けた。オフィス街は昼時ということもあって外食に向かうビジネスマンが数人の塊となって歩いていた。ラーメン屋には行列ができていた。茅根は駅近くの店に入り蕎麦を食べた。頭上を電車が通過するたび轟音を響かせていた。
その後、歌舞伎町界隈を歩いた。夜間、不夜城のごとくネオンが瞬く歓楽街は閑散としていた。路地裏のビデオ、個室、ミュージックなどの店の看板はうす汚く見えた。ラブホテル街の店先の道路にはペール型のプラスチック製のゴミ箱が並べられていた。
林立する高層ビルのガラス窓に陽光が当たって反射していた。新宿中央公園に向かいベンチで休息した。歩き疲れて睡魔に襲われた。気が付いた時は日差しは西に傾きかけていた。
【イチオシ記事】彼と一緒にお風呂に入って、そしていつもよりも早く寝室へ。それはそれは、いつもとはまた違う愛し方をしてくれて…
【注目記事】(お母さん!助けて!お母さん…)―小学5年生の私と、兄妹のように仲良しだったはずの男の子。部屋で遊んでいたら突然、体を…