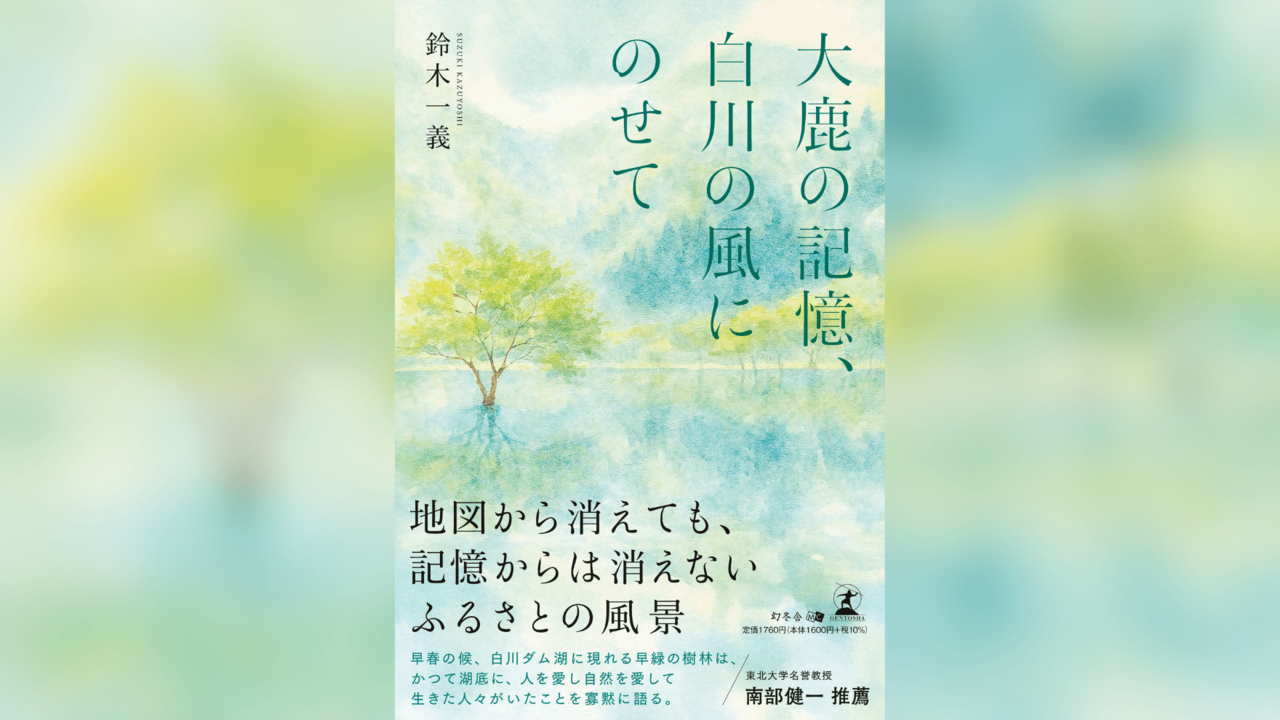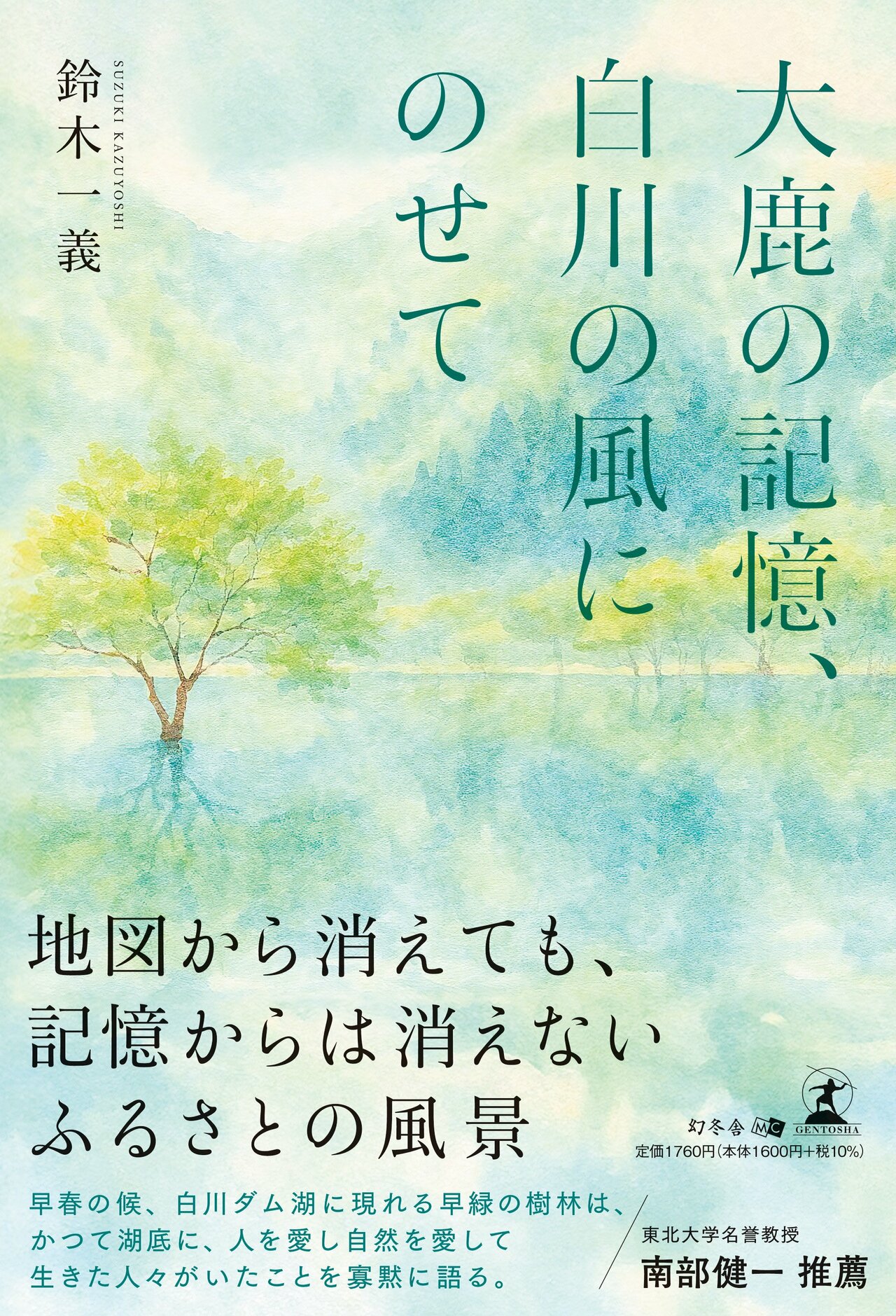かたくり
もののふの八十娘子らが汲み乱ふ寺井の上の堅香子の花
大伴家持のこの句に触れたのは、置賜農業高等学校を卒業して、冬期間、飯豊 (いいで)町立中津川中学校寄宿舎の舎監として採用された、中学校の図書室で目についた句であった。
私の心の片隅に長年「かたかこ」の言葉が残っていたのであり、新しい元号「令和」の出典が万葉集から選ばれたとの解説がなされ、万葉集が大きくクローズアップされ、冒頭の句が大伴家持の作品として、あるテレビ局の解説員が紹介しており、もう一度「堅香子」の句に出会えた喜びに浸っている。
私たちの地方では、カタクリを「かたかご」と名付けており、奈良の都から遠く離れた、東北のしかも世離れをしたような、狭隘の山間部に、大和ことばが使われていることに驚きと誇りを感じたのが、この句に最初に出会った時の感情であった。
さて、私の幼年期を育んだふるさとでは、雪解けを待つかのように、家々の屋敷林から山麓まで、点てんと続く栗樹林の根本に一面に赤紫の百合の花に似た可憐な「かたくり」の花が絨毯を敷き詰めたように咲き乱れるのである。
現在でもカタクリは早春の山菜として供する割烹店もあるそうだが、郷里では小学生や幼児までも容易に大量の、カタクリを摘み取り、老婆たちは、干し菜を作って保存食とし冬期間の貴重な食材となるのである。
カタクリの群集地は、落葉樹林の手入れされた場所しか自生しない植物であり、春一番に蕾を持った芽をだし、日を置かずして満開の花園を造り出すのだ。