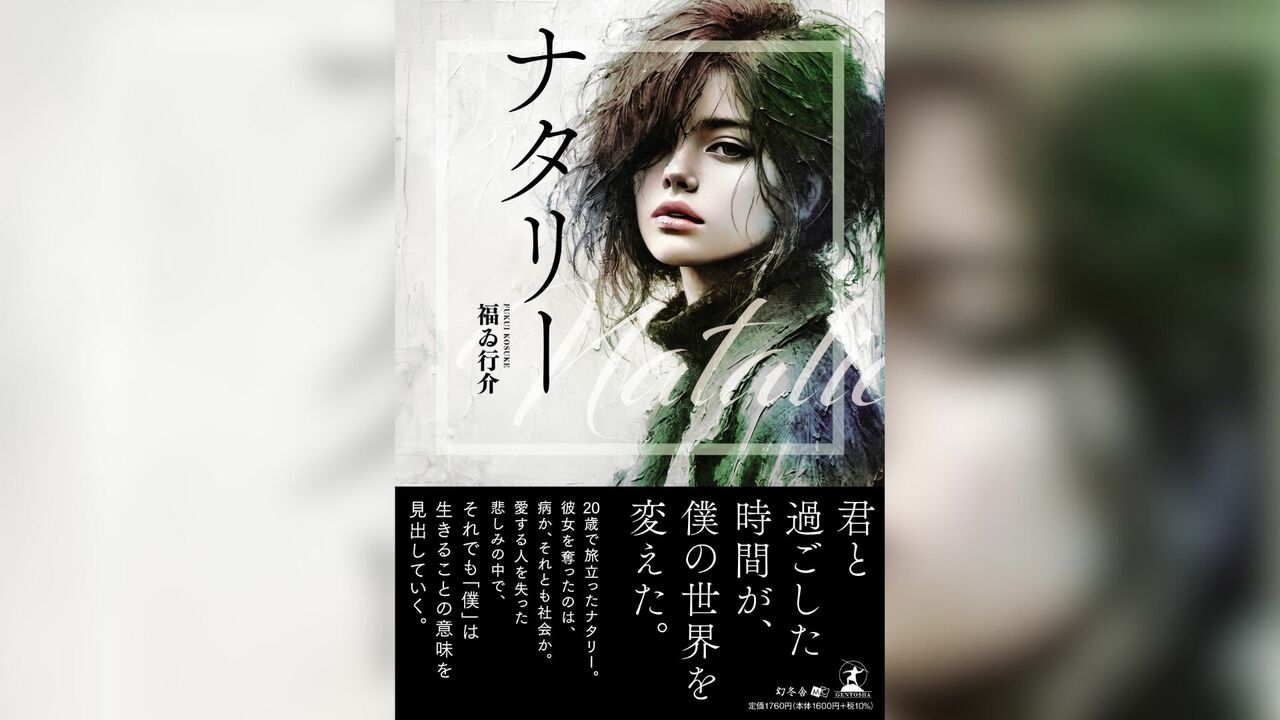【前回の記事を読む】1年間住むことになるウェストキャンプの小さな家の前に立った時、満天の星空と縦横無尽に飛び交う蛍の群れが祝福してくれた
一
家を出て30分も歩けば、空になったコーヒーカップをもつ右手の感覚は手袋をしていても、殆どなくなってしまう。従って帰り道は速足にならざるを得ない。
針葉樹の森を抜けると唐突に原野が現れ、その先には再び緩やかな斜面を伴った低木の茂みが広がっている。わずかに覗く木々の間からは、氷結により徐々に流れを失いつつあるハドソン川が晒(さらし)の帯のように横たわるのが見える。
そして、さらに緩やかな坂道を登れば、そのハドソン川の対岸に果てしなく広がる森と、はるか地平線近くに見えるコネチカット、マサチューセッツのなだらかな山並みを眺めることも出来る。私の住む家は、そのような光景を一望出来る小高い丘の片隅にこぢんまりと建っていた。
「おはよう! タカオ」
私がようやく「わが家」に辿り着き、靴についた泥を落としている時に声をかけてきたのは200mほど離れたところにあるマーティン家の次女、ティナであった。
「一緒にスケートに行かないかと思って。あの森の先に大きな池を見つけたの。ナタリーとレイモンドも行くと言っているわ」
「池とはこの先の大きな沼のことかい?」
私はこの秋、その沼まで歩いたことがあった。
当時は辺り一面背の丈ほどの葦(あし)に覆われていたのだが、ガレージの隅に落ちていた古い地図でその先に大きな沼があることを知った私は、どうしてもこの目でそれを見たいと思い、枯れ切った葦をかき分けるように歩きながら、ようやくその沼のほとりに辿り着いたのだった。そして、そこで見た落日のすさまじさは今もって脳裏に深く刻み込まれている。
「ねえ、どうするの?」
そばかすだらけの顔が妙に媚びた表情に変わり、そこに低い初冬の日差しが当たっていた。
「悪いが今日はやめておくよ。これから取材に出なければならないんだ」
そう言いながらも、マーティン家の姉妹は何故こうも妖艶な表情をいとも簡単につくることが出来るのだろうと思う。
とりわけ10歳になったばかりのティナは妙に大人びていた。
「分かったわ。せっかくナタリーも行くと言っているのに……」