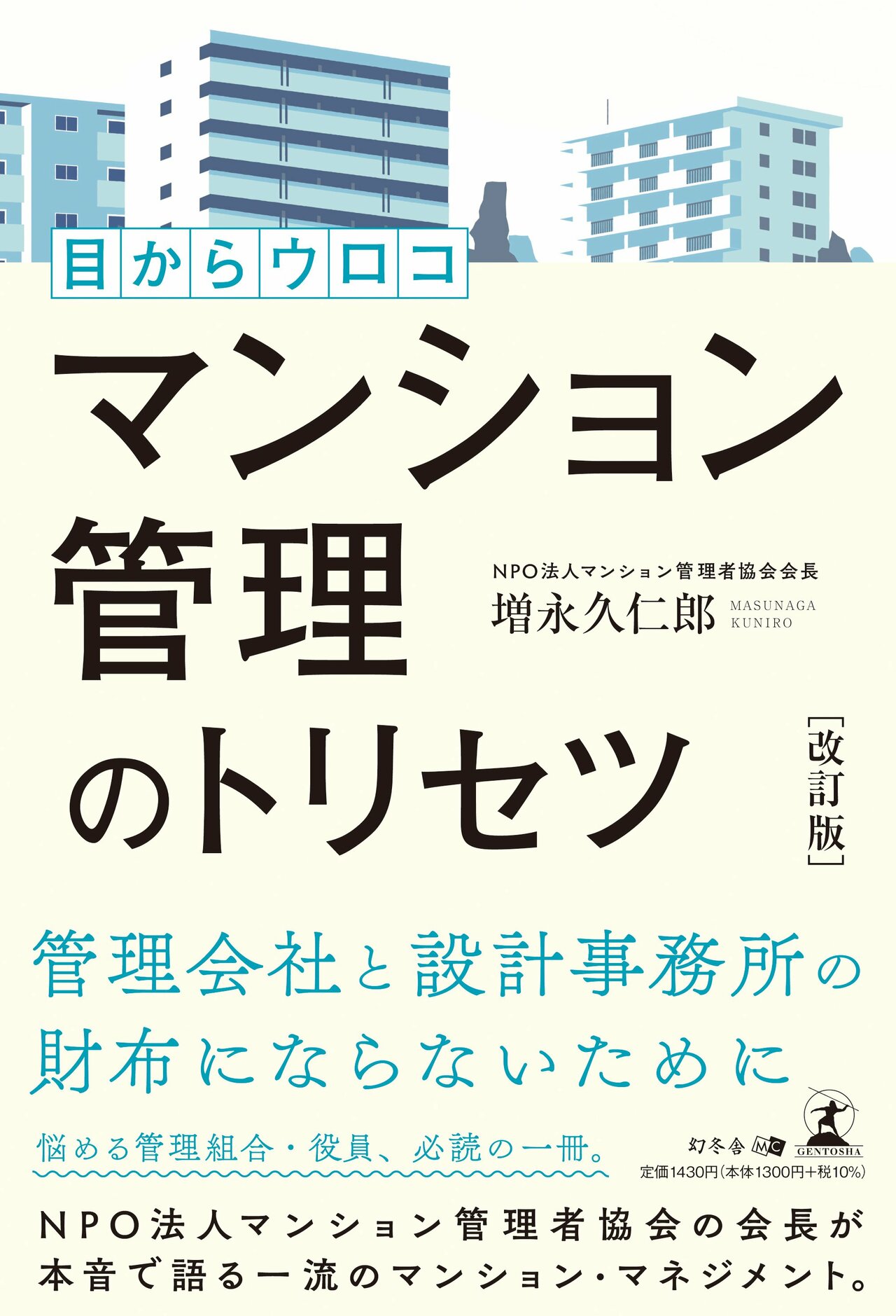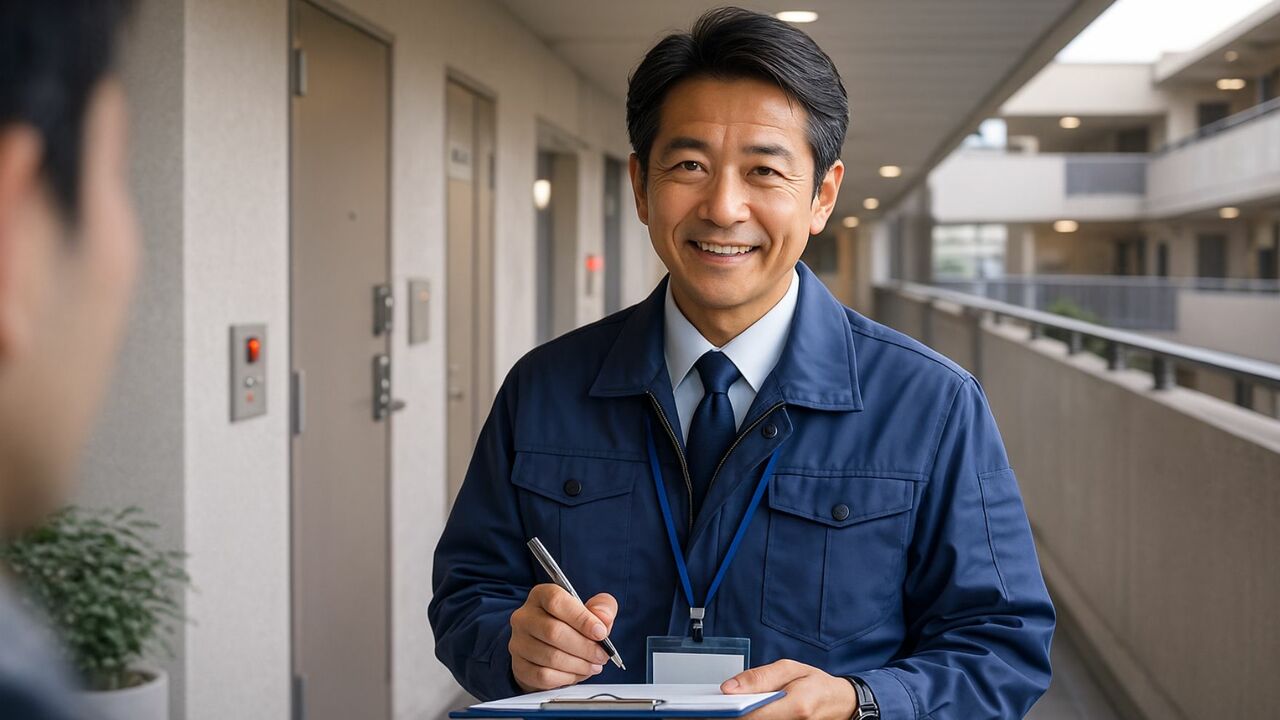2 マンション管理特有の用語の解説
分譲マンションを購入し、晴れて管理組合の区分所有者として管理組合運営やマンション管理に興味を持ち、または役員になったから勉強しようと思っても先ず立ちふさがる難関が法律用語とマンション管理特有の言葉です。
私が47歳の時に生まれて初めて管理組合の理事長になった時も管理会社のフロント等の言葉を100%理解する事ができませんでした。
その経験から、先ずマンション管理特有の用語の解説から入ります。
1.区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
戦後の焼け野原から木造のバラック小屋、長屋、文化住宅等が雨後の筍のように続々と建設された中で鉄筋コンクリート造の集合住宅が建設された1962年に民法の特別法として制定されました。
ところでマンションと言う言葉は何時頃から使用されたのでしょう。実はマンション管理適正化法が制定されるまでマンションは集合住宅や区分所有建物と呼ばれていましたが、マンション管理適正化法が成立した2000年以降はマンションと言う呼び名が定着しました。
しかし区分所有建物はマンションだけではありません。区分所有された事務所ビルもありますので、同ビルも区分所有法が適用されます。
1960年代後半になると高嶺の花だったマンションも大衆化され1970年に住宅金融公庫の融資制度が誕生すると一気にマンションブームが到来しました。ちなみに同年には大阪では万国博覧会が開催されましたが、その頃が第1回のマンションブームです。
また、民法の特別法である区分所有法の罰則規定は、例えば「規約、議事録の保管」に違反した場合に20万円以下の過料等僅かです。
2.管理規約
管理規約の改正や建替えなどの強行規定を除き、区分所有法30条で管理組合は管理規約を自由に定めることができます。また国土交通省は時代に応じて標準的な管理規約を改正しますので、マンションの個性や区分所有者のライフスタイルやライフステージに対応した管理規約を制定する事ができます。
例えば古い管理規約でペット飼育禁止や役員の輪番制など、世界基準から遅れた非平等的な規律を押し付ける管理組合もありますが、管理規約制定の目的は良好なコミュニティの形成である事を忘れてはなりません。
中には管理規約を金科玉条のごとく押し付ける管理組合もありますが、管理規約の原典は民法の特別法である区分所有法ですから話合いを重視しなくてはなりません。
ちなみに区分所有法の区分所有者と管理規約の組合員は呼び名こそ違え同じ意味です。
👉『改訂版 目からウロコ マンション管理のトリセツ』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】店を畳むという噂に足を運ぶと、「抱いて」と柔らかい体が絡んできて…
【注目記事】忌引きの理由は自殺だとは言えなかった…行方不明から1週間、父の体を発見した漁船は、父の故郷に近い地域の船だった。