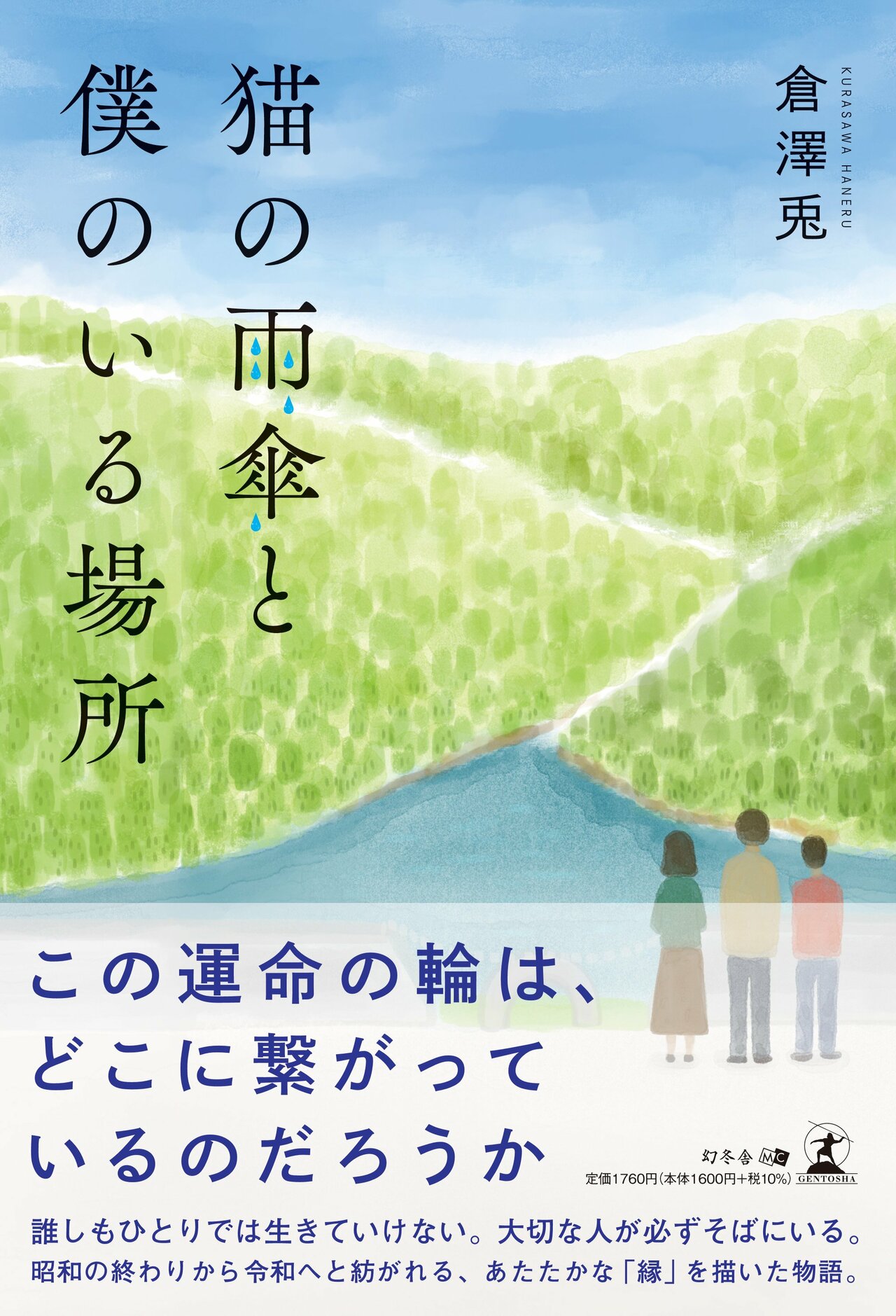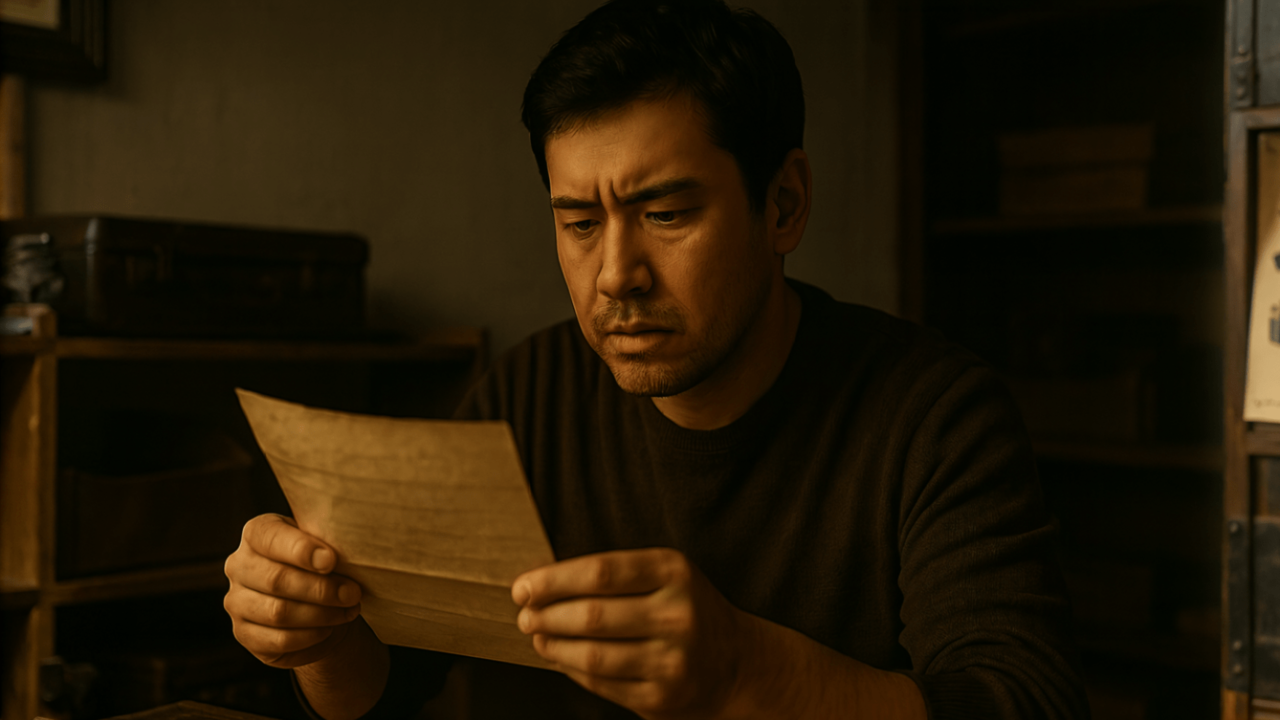倉嶋家の先祖代々の墓は、善光寺から西にある西慶寺境内にあった。善光寺の仁王門をくぐると、すぐの十字路を西に曲がる。その通りの一角が桜枝町で、その通り沿いに嘗ての父が育った家があった。
祖母が亡くなり、次に祖父が亡くなると、長男の貞一は桜枝町の実家を引き払い長野市の郊外に引っ越した。もちろん倉嶋家先祖代々の墓は、西慶寺墓地にそのままある。
西慶寺での墓参りを済ませると、その後、善光寺の本堂内陣にて、親族二十名ほどで法要が営まれた。
善光寺での法要が終わると、門前町を下り権藤にある「蕎麦処大門」で昼食となった。予約された店の暖簾をくぐる。すると黒光りする堂々とした大黒柱が最初に目に飛び込んできた。黒檀であろうか。過去に多くの人が案内されて、時間とともに自然に黒く磨かれたと思われる上がり框を踏み、二階の中座敷に案内された。
僕の席は伯父夫婦の隣にあった。倉嶋姓を名乗る伯父夫婦と息子の聡志、そして僕の席が上座に設けられていた。父が纏っていた何気ない誇りや品の良さは、このような家風により育まれてきたのであろう。何代にも亘って継続されてきたお斎(とぎ)である。
「昔は、蕎麦なんて、こんなに大仰に食べるもんじゃねかったさ!」
「まったくだな。粟や稗とおんなじで、食うもんが無うて、仕方なく婆さんが打った蕎麦を食ったもんだなァ」
「いまぁ、ざる蕎麦ァ一盛でも、千円以上は取るだろぅ」
二人の老人の話を興味深く聞いていた僕は、父が休暇で家に帰ってくると必ず「うどん」を打ってくれたのを思い出した。生憎、東紀州には「蕎麦」を日常好んで食する習慣が無い。ましてソバ粉を販売している店などは無かった。仕方なく父は「うどん」を打ったのだ。そうに違いない。
僕は父が打ってくれた不揃いの「うどん」を思い出しながら、木の葉型に形成された土色の練り物を頬張った。「蕎麦がき」である。蕎麦の旨さは「つゆ」の旨さではないかと以前から思っていたが、初めて「蕎麦がき」を食べてそれを確信した。きっとソバは汁の発明により蕎麦になったのだ。
二人の老人の会話と、父が作ってくれた濃い醤油色のうどん汁の味を思い出しながら勝手な想像をし、――蘊蓄(うんちく)のネタにでも――と考えている自分に気がつき笑ってしまった。そして二人の老人のやり取りが、慣れない親族との会話や法事での緊張感を和らげてくれたことに感謝した。
本連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。
【イチオシ記事】店を畳むという噂に足を運ぶと、「抱いて」と柔らかい体が絡んできて…
【注目記事】忌引きの理由は自殺だとは言えなかった…行方不明から1週間、父の体を発見した漁船は、父の故郷に近い地域の船だった。