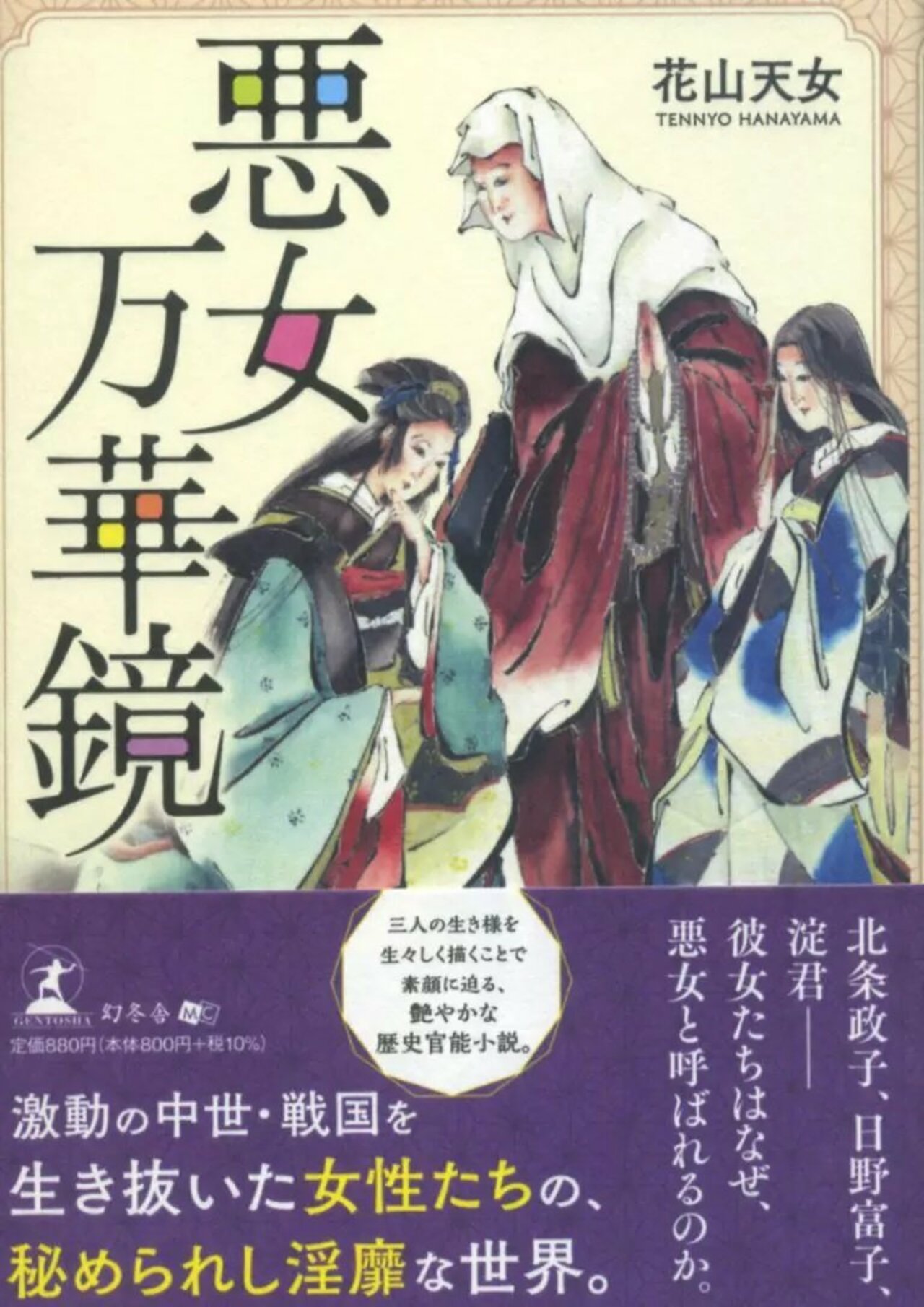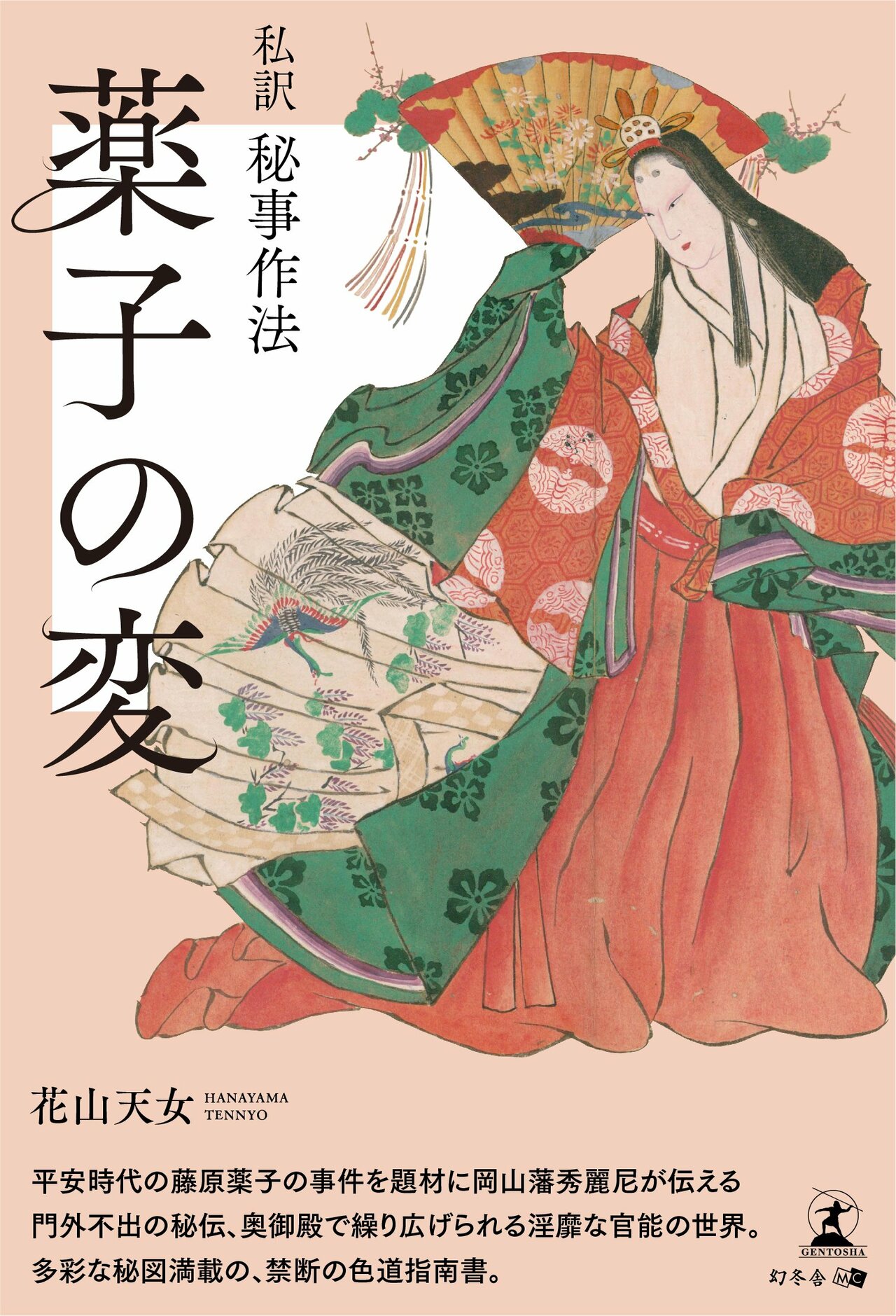桓武は即位前の山部王時代には将来の望みも薄かったこともあり、官吏として政(まつりごと)の苦労も経験し、また自由奔放に野山を駆けめぐっていて、それまでのお飾り人形のような天皇が多いなかで、骨太の自我の強い本来の帝王型の人物でした。
そんな桓武と比較して、叔父である早良の怨霊に取り憑かれた安殿が無事に皇統を繋いでいけるものでしょうか。今となれば桓武は後継者としての安殿を一人前に育て上げる責任があります。
東宮時代の安殿は十九歳で既に高岳親王(たかおかしんのう)をもうけておりますが、相変わらず本人は早良の怨霊に責め続けられ部屋に閉じこもる毎日でした。
昼日中も落ち着かない素振りで、何者かに追われているように青ざめた顔で部屋の中をうろつき回り、やっと寝入ったかと思えば、突然、粗野(そや)な胴間声(どうまごえ)を張り上げ喚(わめ)きちらす始末。ふだんの安殿は痩せこけた老人のように背を丸めて、その言動にも男子の活発さはありません。
「親王さまは、早良さまのことをご存知なのでしょうか。あの、お寂しそうなご表情は何ともお可哀相です」
このような噂話は魘魅、呪術が信じられていた当時、早良怨霊説となって世間にも広まっていたのです。桓武が安殿を見限ることができないのは、本来は自分に向かうべき怨霊が、心身虚弱な安殿に憑(つ)いて申し訳ないという気持ちがありました。
そんな怨霊に脅えながらも安殿は学問を好み、律令などの法典を研究し、漢詩や文章にも長(た)けていて、桓武はそこに一縷(いちる)の望みを持たれていました。
桓武が山部王の時代から、市井(しせい)の一官人(中務卿(なかつかさきょう))として社会の風に触れ、野山で体を鍛えていたこと、また、弟の早良が幼くして出家し、東大寺に住んで親王禅師として修行の日々を過ごしたのは、父白壁王(光仁帝)の、子の将来を案じての計(はか)らいでした。
しかし安殿は生まれながらの桓武の後継として、お蚕(かいこ)ぐるみの温室育ち、加えて父桓武が被(こうむ)るべき、井上(いがみ)・他戸(おさべ)母子、叔父の早良(さわら)親王、後の伊予(いよ)親王事件の怨念まで背負い込んでいたのです。