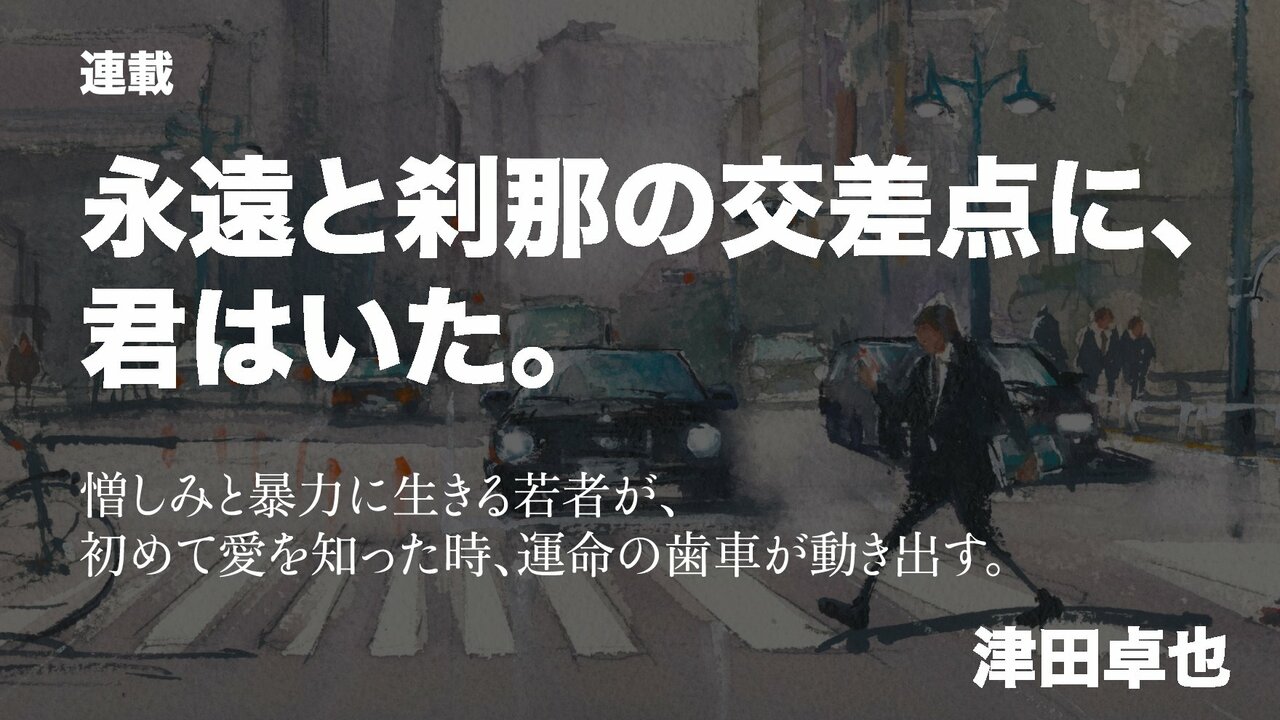第二章
8
静かな店内に肉を切る音だけが響く。最後の一切れを咀嚼すると、博昭はナプキンで口を拭った。加瀬はすでに食べ終えている。目が合った。
「先日は大変でしたね。あの娘もよほどショックだったんでしょう。あのあと、病院に行ったようです」
「病院? どこの?」
「街の総合病院です」
「で、何だったんだ?」
「そこまではわかりません」
「連中は?」
「連中?」
「骸に決まってんだろ」
「今のところ見かけていません」
博昭は考えた。ということは、骸は今日子の居所までは知らないということか。それとも……。
「街が騒がしいようですね」
博昭は顔を上げた。
「渋谷ですよ。あなたに関係があるんでしょ?」
「だったら何だ?」
「仕事に集中してもらわないと困ります」
「おまえがやればいいじゃねえか?」
加瀬は首を傾げて微笑んだ。
「風間さんはあなたにお願いしたのです」
「知るか」と博昭は吐き捨てた。
「変更はありません」
「俺はあの女に目撃されてる」
「好都合です」
「何?」
「もうこそこそする必要がない」
「どういうことだ?」
「正直に話していただいて結構です」
「風間のこともか?」
「それは困ります。依頼主の名前は隠してください。守秘義務です」
「嫌だと言ったら」
「選択の余地はありません」
「俺に命令するつもりか」
「とんでもない。私は風間さんの指示に従っているだけです」
二人の男は睨みあった。
「工藤さん」
加瀬が右手を上げた。
「私は珈琲を頂きます。工藤さんは本当に何もいりませんか?」
博昭は問いには答えず、加瀬の顔をじっと睨んだ。店員はすぐに来た。注文を済ますと、加瀬は両手を組んで前傾姿勢になった。
「風間さんにはこのことは言わないように止められているのですが、仕方がありません。正直に言いましょう。風間さんがどうしてあなたに雨水今日子の監視を依頼したのか」
「もったいぶんじゃねえ。コヨーテ」
加瀬はほんの一瞬ぽかんとしたが、すぐに笑顔を取り戻した。
「いいたとえですね」
加瀬は、くくく、と忍び笑いをした。
「確かに残飯漁りのような人生でした」
「そんなことはどうでもいい。で、何なんだ? 理由は」
「いや、すみません。あまりにもぴったりだったものですから。コヨーテか。工藤さん。あなた文学の才能あるんじゃないですか?」
「おい」
「あっ、失礼」
加瀬は再び、くくく、と笑ってから、大きく息を吸い、姿勢を正した。加瀬が真顔になった。そして、囁くような声でこう言った。
「風間さんは息子を死に追いやりました。実の息子をね」
博昭は言葉の意味が理解できなかった。実の息子を殺した?
店員が珈琲を運んできた。テーブルに珈琲が置かれ、店員が去る。
その間、二人は無言だった。加瀬が珈琲に砂糖を入れた。
「息子を殺したのか?」
「風間さんはそう思っています」
「それは本当の話か?」
博昭は尋ねずにはいられなかった。加瀬は肩をすくめて、「ええ」と答えた。
それから加瀬は語り始めた。風間家の物語を。