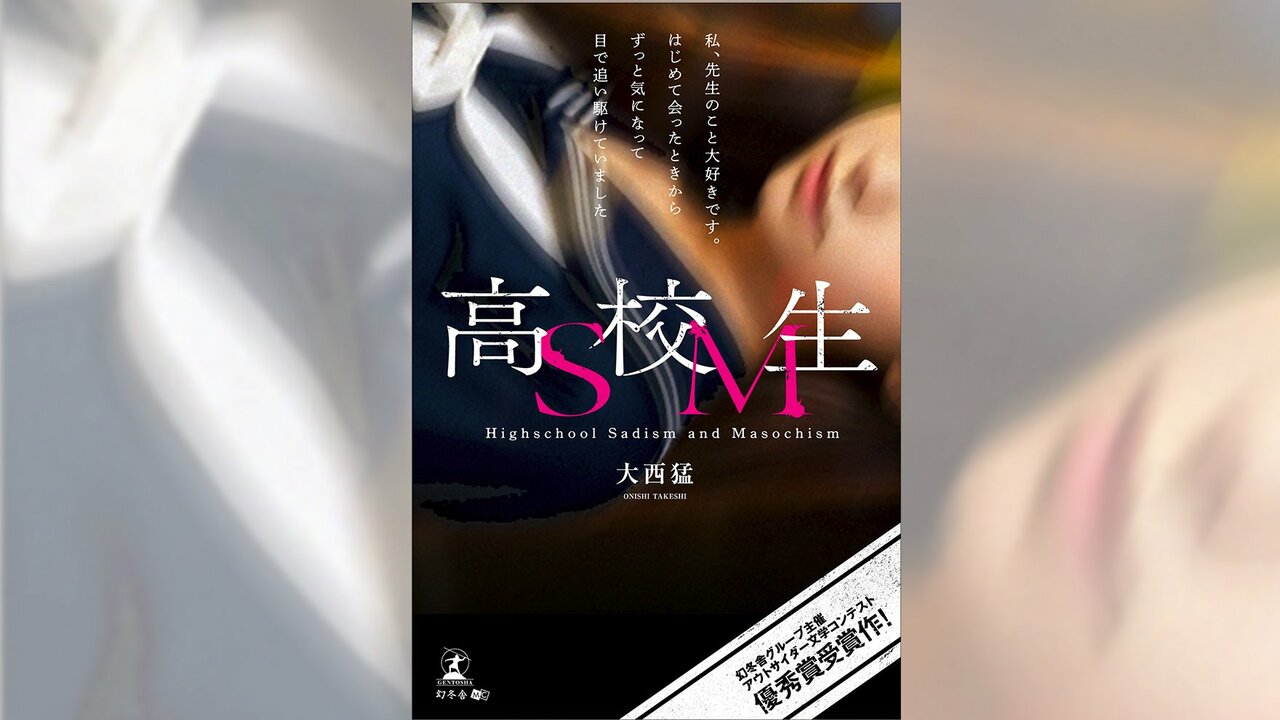1
「えっとあの、もしよかったらまた先生のおすすめの映画を教えてください」
「僕のおすすめ? なんだろう」
あの人はうっすらと生えた下顎の髭を触りながら天井を見た。
「世界史の勉強ということであれば『ブレイブハート』はどうかな。十三世紀のイングランドの状況について学べると思うよ」
「ありがとうございます。借りてみます」
私はそう言ってから脇にどいた。あの人に行ってほしくない気持ちは変わらなかったが、私に課題が与えられた。観た後でまたあの人に会える。
「ありがとうございました」
あの人は小さく頷いてから歩き出した。私は鼻腔いっぱいに広がるあの人の匂いを嗅ぎながら遠ざかる背中をじっと見つめた。
この日を境に、あの人にすすめられた映画を観て、あの人に感想を言うことが日課のようになった。私はいつも決まって授業の終わりに廊下であの人を捕まえ、映画を観て感じたことや驚いたことを話した。
そして、必ず最後には次に見るべき映画や小説を教えてくれた。数分にも満たない短いやり取りだったが、私の体を喜びで満たした。
私とあの人が廊下で話す姿は当然、他の生徒の視線にさらされた。
「ねえ、さっき吉見先生と何話してたの?」
あるとき、私はいつもの三人と昼食をとっていたとき、直子に聞かれた。
「授業でわからないところがあったから聞いたの」
私はあの人への思いを悟られないように嘘をついた。
「最近、よく吉見先生と話してしてるよね」
友麻も不思議そうな顔でそう言った。
「世界史って複雑だから授業だけじゃわからなくて」
「絵里、真面目すぎるでしょ。私なんて世界史だけじゃなくて他の教科もわからないよ」
友麻は自虐的に笑った。
「でもよく吉見なんかに聞く気になるね。私は絶対嫌だ」
晴美は表情に現れる嫌悪感を隠さなかった。
私はこうした周りからの好奇な眼差しを受けながらも、あの人に近づくのを止めなかった。いや、あの人に近づけば近づくほど、その引力はますます力を増し、心は離れなれなくなった。
いつの間にか、私は一日のほとんどをあの人を考えて過ごした。食事中も、お風呂に入っているときも、さらには夢にまで出てくることもあった。
あの人の存在が私の生活を侵食していた。でも、それは私が望んだことだった。できるなら私はあの人以外のことは考えたくなかった。しかし、そんな日常を断ち切る障害が私の前に立ち塞がった。それは夏休みだった。誰もが喜ぶ夏休みは私にとっては、あの人と会えなくなることを意味していた。
私はその間、どうやってその孤独に耐えればいいのかわからなかった。たった一日あの人に会えないだけでも辛いのに、それが四十日間も続くのだ。私は夏休みなんて欲しくなかった。
毎日暑苦しい教室であの人の授業を受けているほうがよかった。でも、夏休みはどんなに拒んでもやって来る。他の生徒が喜ぶ中、私だけが絶望していた。