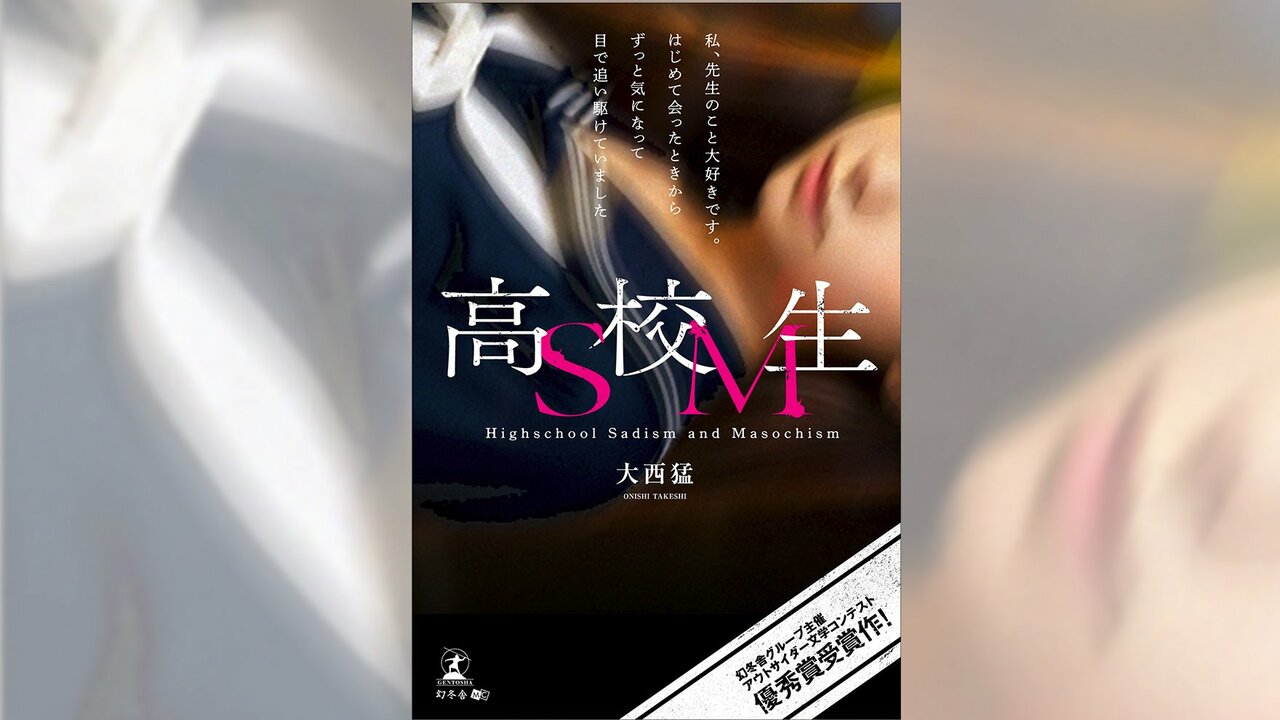1
私は職員室の前で立ち止まり、呼吸を整えた。手に持った教科書が急に重く感じた。私はあくまで授業でわからないことを聞きに来たのだ。今からは完璧に役を演じなくてはいけなかった。あの人を好きだという気持ちは押し殺して。
ノックするまでに何度も唾を飲み込んだ。なかなか気持ちが定まらなかった。
むしろ時間が過ぎれば過ぎるほどノックする勇気まで削りとられていくようだった。しかし、私は待つのを止めたのだ。
「失礼します」
うわずった声が自分のものでないように聞こえたが、言い直すこともできず、私はドアを開けた。すぐにあの人の姿を探した。一番奥の机のファイルの山の陰に、白髪の混じった頭頂部が見えた。あの人だった。
前と同じくドアの近くの机にいた先生が振り返って私を見た。私が会釈すると、先生は私の顔を思いだしたのか「ああ」と言った。私は「失礼します」ともう一度言って、先生の横を通ってあの人に近づいた。他の先生も私に視線を向けたが、何も言わなかった。
あの人は机に向かって書き物をしていた。私の存在にはまったく気づいていなかった。ファイルや消しゴムのかすが散らかった机は、持ち主の性格をわかりやすく映し出していた。私はあの人のワイシャツの袖口のボタンが一つなくなっているのに気づいた。でも、きっと本人はそのことにも気づいていないに違いなかった。
「あの、お忙しいところすみません」
私はあの人を驚かせないように小さな声で言った。それでもあの人は自分の後ろから聞こえた声に驚いたのか、一瞬体をびくつかせてから振り返った。
「突然すみません」
あの人は私の顔をじっと見た。まるで誰だか思い出そうとするかのように。もしかしたら本当に私の名前がわからなかったのかもしれない。あの人はいつも生徒に無関心だった。私もあの人にとっては数いる生徒の一人にすぎなかった。
「私、一年B組の川北と言います」
私がそう名前を言うと、あの人は「ああ」と言って頷いた。前に私が筆箱を持って来たことを思い出してくれたのかもしれない。私はあの人の意識の中にわずかな痕跡を残せたことが嬉しかった。
「どうしたの?」
あの人は教壇の上でソクラテスの思想について語るときと同じ小さな声で言った。
「あの、わからないところを先生に教えてもらいたくて来ました」
先生からのはじめての質問に緊張しながら答えた。口の中は水分を失い、唇が歯に張り付いていた。
「わからないところ?」
「はい。教科書の二十四ページなんですが」
私は持って来た教科書を開いた。あの人は身を乗り出してそれを見た。その瞬間、あの人の匂いも迫ってきた。私はそれを鼻いっぱいに吸い込んだ。