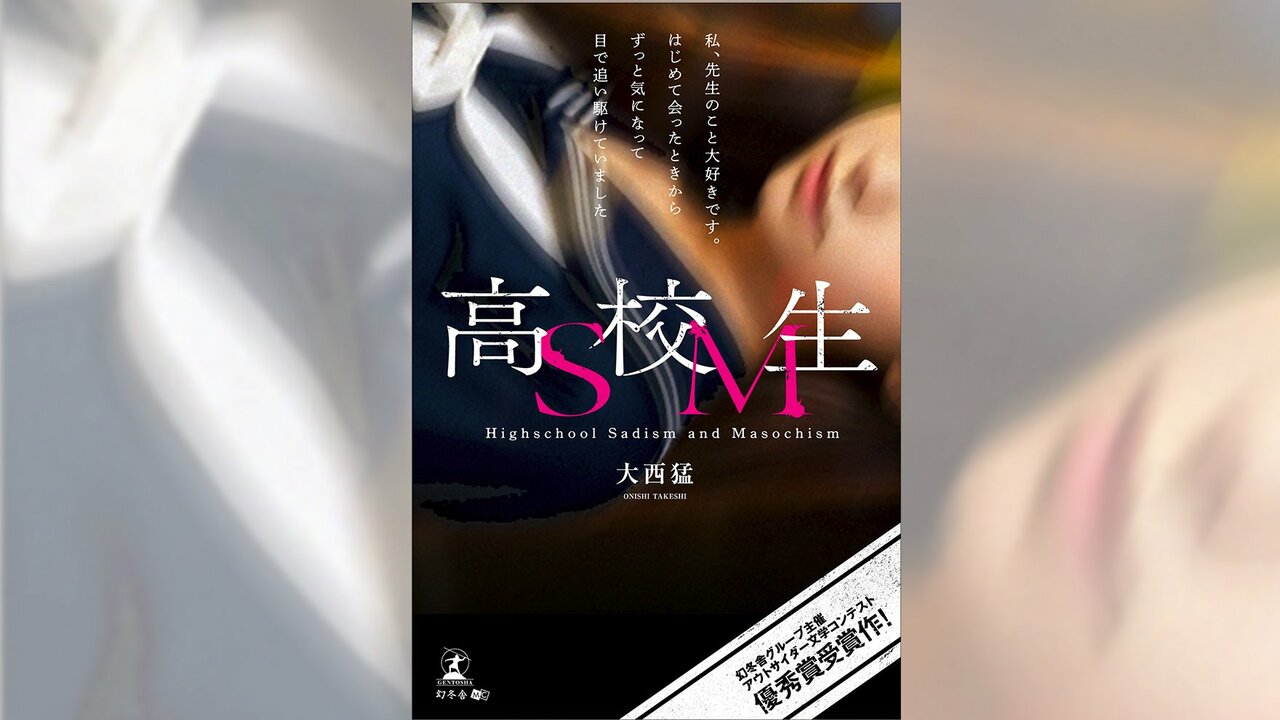1
職員室の前に着くと、立ち止まって乱れている呼吸を整えた。ドアの向こうにあの人がいるのだという思った瞬間、緊張は喉元にまでせり上がってきた。私は自分の頬を軽く叩いて気持ちを静めると、ドアをノックした。
「失礼します」
私はゆっくりドアを開いた。最初に目に入ったのは入口の一番近くの席に座る先生の姿だった。全校集会で見たことがある髭面の男だったが、名前はわからなかった。
「あの、一年の川北です。吉見先生の忘れ物を届けに来ました」
私はそう言ってから教室を見渡した。それほど広くない空間に六つの机が中央に固まって並んでいた。私はすぐにあの人の姿を発見した。あの人の机は入口から一番離れた奥の隅にあった。
私が気づくのと、あの人が顔を上げるのがほとんど同時だった。あの人は私を見ると、「あ」と小さく言い、さらに私が持っている筆箱に目を向け、今度は大きな声で「あ」と言った。
私は見やすいように筆箱を顔の高さまで持ち上げた。
「これ、先生のですよね」
私があの人に向かって発したはじめての言葉だった。
「あ、忘れてた」
あの人はそう言って立ち上がり、いつも教室のドアから教壇まで歩くときと同じ速度で近づいて来た。私は思わず逃げそうになったが、後ろに傾きかけた重心を足で押し戻した。
「そっか、机の上に置きっぱなしにしたんだった」
あの人は独り言のようにそう言うと、私の目の前で立ち止まった。その距離は一メートルも離れていなかった。
間近で見るあの人は教壇の上にいるときよりも大きく見えた。目線は私よりわずかに高いところにあった。その目は真っ直ぐ私に注がれていた。
私は一瞬自分がなぜここにいるのか忘れそうになったが、手の中の筆箱の重みを思い出し、それを差し出した。あの人は何も言わず受け取った。が、その後で私の顔を見て、思い出したように「ありがとう」と言った。私は「どういたしまして」と答えたが、はじめてあの人にかけられた言葉がまだ耳の中で木霊していた。
あの人に見つめられている間、息をするのを忘れた。それは喜びに満ちた瞬間だった。私はもう少しで「こちらこそありがとうございます」と言いそうになった。
次の授業が始まっても、私の夢見心地の状態は続いた。休み時間に「絵里、なんか目の焦点が合ってないよ」と友人の晴美に言われた。同じことを仲の良い直子と友麻にも言われた。私は適当に誤魔化したが、上手くいった自信はなかった。