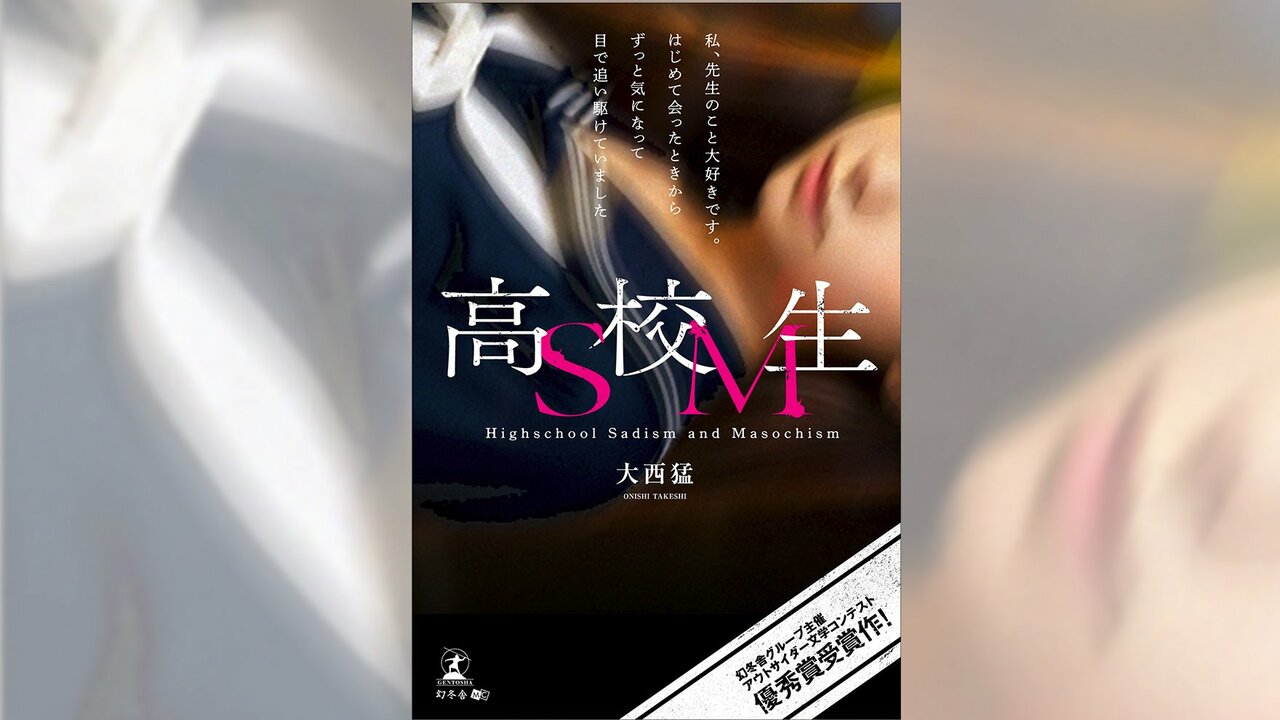1
私は授業中、いつもあの人の書いたものを一字一句残らずノートに写し、あの人が言ったことも聞き漏らさないように耳を澄まし、メモした。ノートは一回の授業で二ページ、三ページ埋まることは当たり前だった。それでも私は新しい知識が増える喜びを覚えた。
あの人が紹介した小説や映画もなるべく観るようにした。映画は「ベン・ハー」や「スパルタカス」「ローマ帝国の滅亡」などを観た。小説はアリストパネスやソフォクレスの戯曲を読んだ。中には難解すぎて理解できない内容のものもあったが、途中で投げ出すことはなかった。
なぜならあの人が観たものを私も観たかったし、あの人が理解したものを私も理解したかったからだ。私はもっとあの人に近づきたかった。あの人を知りたかった。小説を読むことも、映画を観ることも、あの人をより知るための手段だった。
そのかいあってか、五月に行われた中間テストでは、世界史で九十八点をとった。間違えた問題は文章の読み間違えだったので、実質満点と言ってよかった。
特に嬉しかったのは教科書にも資料にも出ていない問題に正解したことだった。それはあの人が授業中にしたなにげない話の中にでてきた哲学者の名前だった。
他の生徒にしてみたらまったく答えようがない問題だった。でも、私はあの人の話す言葉を一つも聞き漏らさなかったからこそ正解できた。それはどんな数学の難問に正解するよりも嬉しいことだった。
あの人の授業を受けている以外は退屈でつまらない毎日だった。私はそのつまらない日常を、しかしあの人を思うことで紛らわした。あの人に会うことができなくても、心に思い描くことで孤独を癒すことができた。
通学の電車の中でも、国語の授業中でも、私はあの人に会うことができた。現実の世界では笑った姿を一度も見たことがなかったが、想像の中では私のために笑ってくれた。優しく愛の言葉を囁いてくれた。私は完全にあの人の虜だった。猫背で消え入りそうな声で愛を囁くあの人の姿はどんな俳優より眩しかった。
そんなあの人とはじめて現実の世界で言葉を交わしたのは、学期がはじまって二ヵ月が過ぎた頃だった。
その日もあの人はチャイムと同時にドアを開け、教壇に立ち、耳を澄まさないと聞こえないような声で世界史について語り、チャイムが鳴ると「では、また」と言って、気づくといなくなっていた。
私はこれで明日の授業まで会えないのだと思って寂しい気持ちになった。そして、あの人が書いた黒板の小さな字をぼんやりと見つめていた。