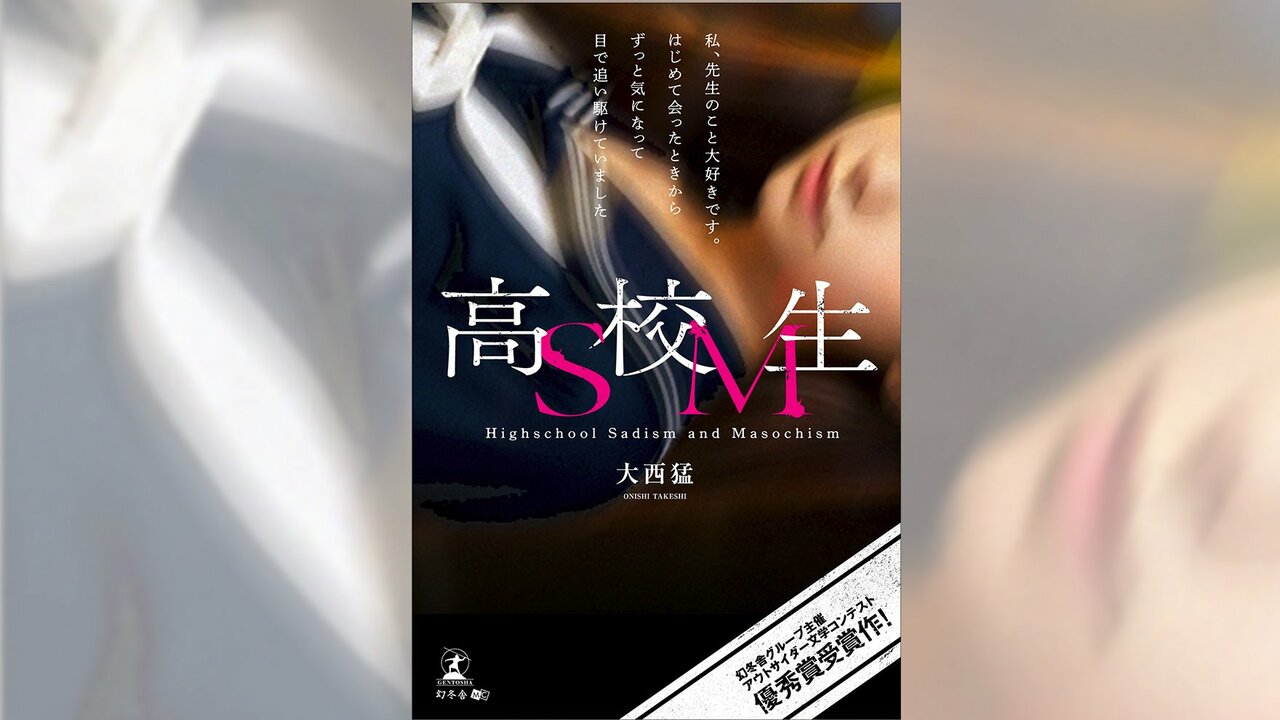1
その日、私は深さ三十センチ横幅二十センチはある大きな穴を掘った。このまま掘り続けたら砂場の砂が尽きてしまうのではというほど大量の砂の山が隣にできた。
ひろと君は私以上に大きな穴を掘った。自分がそのまま入ってもまだ余裕があるほどの大きさだった。私がその穴を見て、「すごいね」と言うと、ひろと君は口元を少しだけ上げた。それはあまりに小さな変化だったが、笑ったことに間違いはなかった。私はそのとき少しだけ、ひろと君に認められた気がした。
それから、私たちは常に行動をともにするようになった。ひろと君が砂場で穴を掘れば私もその横で穴を掘り、積み木で高い建造物を作れば私もそれを真似した。ときには言葉をかけることもあったが、それは私からの一方通行で、会話にはまずならなかった。
はたから見れば一緒に遊んでいるというよりは同じ場所で別々に遊んでいるようにしか見えなかっただろう。でも、私はひろと君の隣にいられるだけで一緒に遊んでいる気になれたし、十分楽しかった。たとえ会話ができなくても、いやほとんど会話がないからこそ、逆に見えない何かで繋がっているような不思議な感覚になった。
ひろと君は幼稚園を卒業してしばらくしてから県外に引っ越した。父の仕事の都合だということを先生から聞いた。でも、本人は最後まで別れの言葉を口にすることはなかった。私も「さよなら」を言わなかった。ひろと君は私の前に現れたときと同じように静かに目の前からいなくなってしまった。
その後も私が惹かれる人は大抵周りから浮いた人ばかりだった。小学生のときは同級生のノブ君を好きになった。彼もまた休み時間に一人で机に向かって本を読んでいるような地味な子だった。他にも、心臓の持病を持っているため一年の半分以上学校を休む川上君を好きになったこともあった。
ただ、残念ながら彼らとは仲良くなることはできなかった。彼らの住む世界の壁はあまりに厚すぎて、私の入る余地などなかったのだ。私は思いを胸に秘めたまま、遠くから彼らを見るだけで満足しなくてはいけなかった。