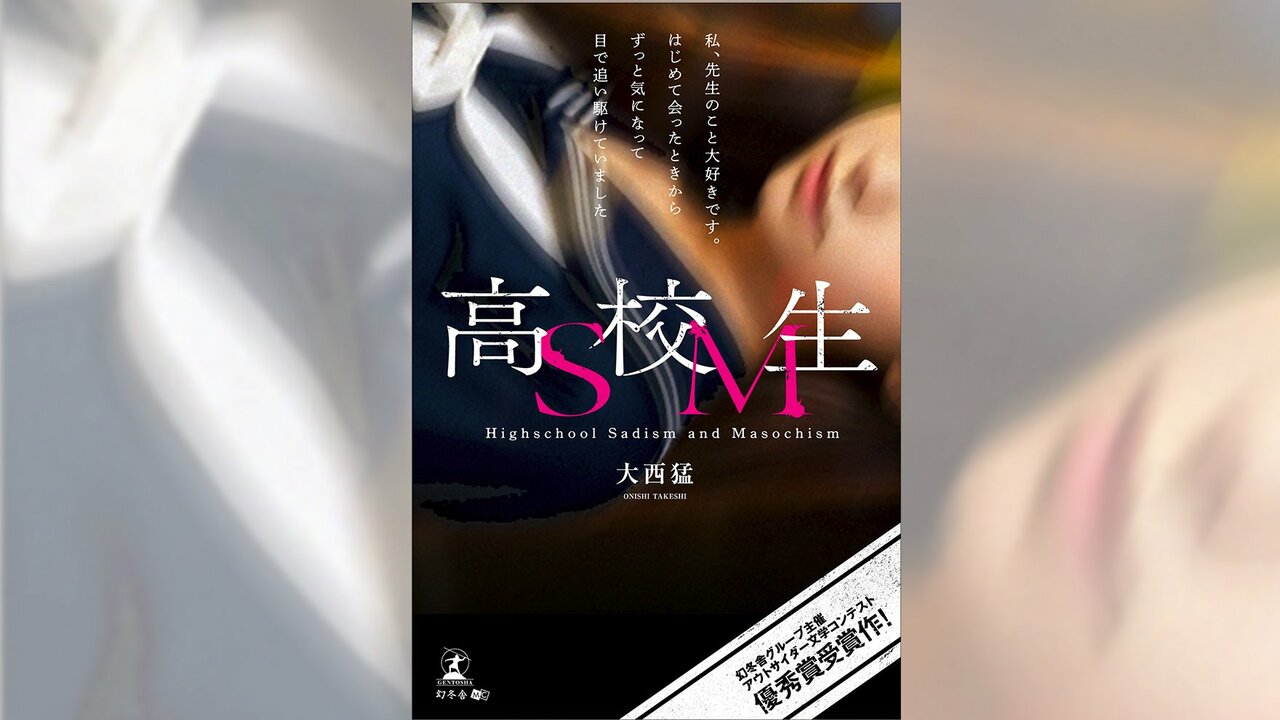1
あの人は私が通う高校の教師だった。
高校は県でも有名な進学校で、周囲を田んぼに囲まれた小高い丘の上にあった。
文武両道を掲げる校風で、広い敷地には野球場から陸上競技場、テニスコート、武道場まで整備されていた。特に野球部はかつて甲子園に出場した実績があり、春夏の予選会ともなると、学校中、さらには町の期待を一身に浴びるほど有名だった。
あの人とはじめて会ったのは入学して最初の授業である世界史だった。第一印象はなんてさえない中年のおじさんだろうだった。
背は百六十ある私と変わらないか少し高いぐらいで、教壇に立っても威圧感はなかった。しかも痩せているので、背広はぶかぶかで、ズボンは丈が合っていないために皺ばかりが目立った。
顔は後で四十五才とわかったときは驚いたくらい年齢を感じさせ、充血していることが多い目は生徒と視線を合わせることを恐れているかのように焦点が定まらなかった。そのうえ声まで小さく、自己紹介をしたときはその半分も聞こえないほどだった。
私の前の席の女子が思わず「キモイんだけど」と漏らした言葉はまさにあの人の印象のすべてを物語っていた。少なくともあの人を見てかっこ良いと思う人は皆無だろう。
しかし、私はあの人を見て、けして「キモイ」とは思わなかった。確かに、痩せて猫背気味の後姿も、ときどき剃り残しがある顎髭に手を当てて困ったように教室を見渡す顔も、かっこ良いと言うことはできなかったが、多くの女子が持ったであろう嫌悪感はまったく生まれなかった。それどころか私の目にあの人は特別な光をまとっていた。
私自身、けして美人というわけではない。髪はくせ毛だったし、ストレスがたまるとすぐにきびができた。足は長くてスタイルを褒められることはあったが、それは裏返すと他に褒めるところがないということだった。
目がもっと大きくて、鼻筋が通っていたらと思うことは何度もあった。でもそれが私だと受け入れて生きていた。
自分が地味だから同じような人に関心を持つのかもしれないが、私は物心ついた頃から、周りから孤立した、誰の目にもとまらないような男の子に心を惹かれた。