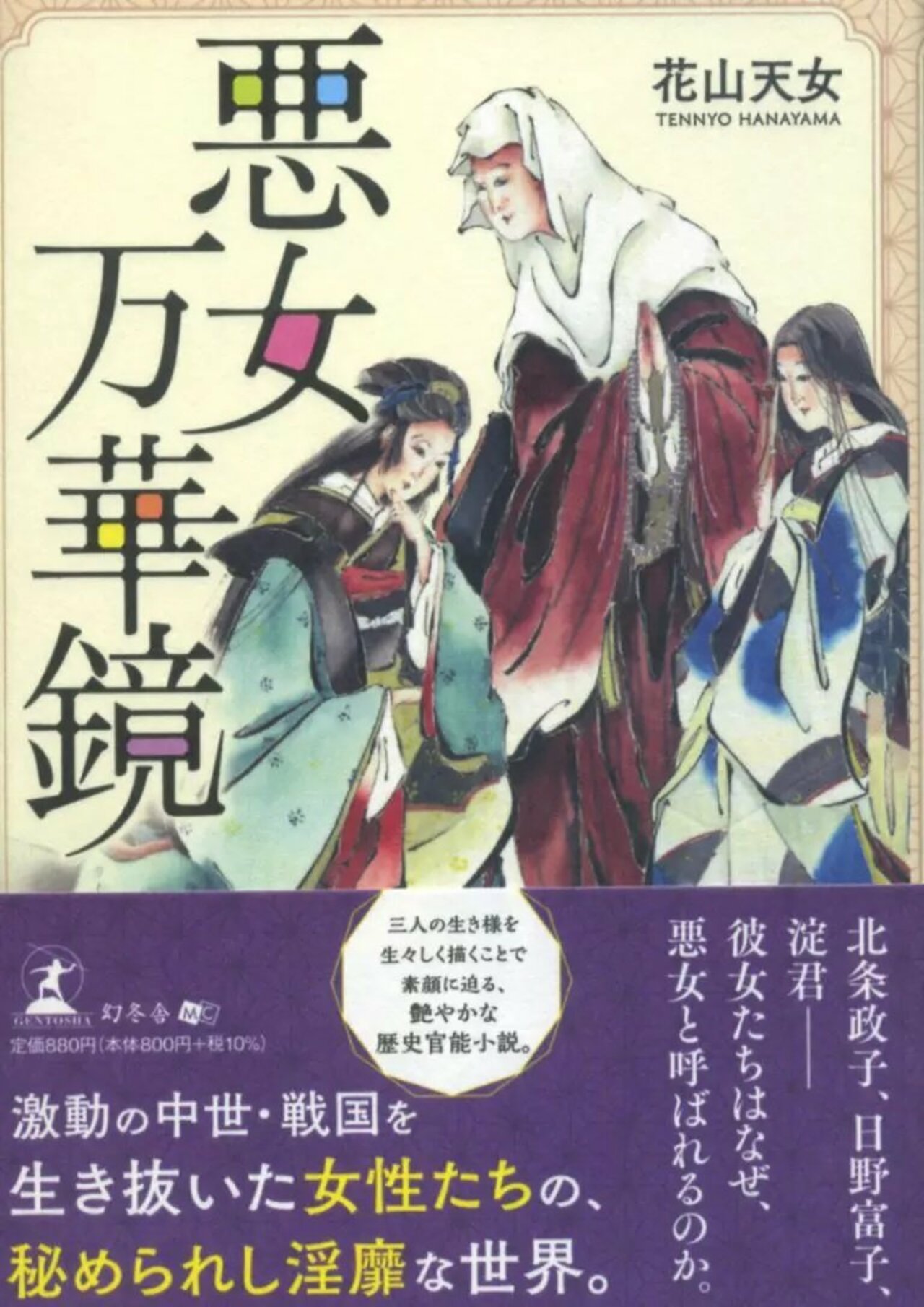そこで桓武は平城京は寺院だけの都にし、政治の中心を別の場所に移そうとしたのです。つまり、それらの寺と僧を置き去りにして奈良の都から逃げ出そうと考えました。ですがいまでも京に寺が多いのは、一つは皇族や貴族の住まいである門跡寺院(もんせきじいん)(妙法院、青蓮院、聖護院、仁和寺、大覚寺など)、そして後の豊臣、徳川時代に興された東西本願寺、知恩院などの新しい寺院です。
しかし、遷都となれば困るのは、これまでこの地で多くの特権を抱えて勢力を拡大してきた寺院であり、その基盤を失う皇太子の側近、そして平城京に愛着を持ち新政府の藤原一族に主導権を奪われていた大伴(おおとも)氏ら一族でした。
この寺院と大伴ら両者が、批判の矛先を遷都の実務責任者で、桓武天皇の信任厚い式家中納言藤原種継(たねつぐ)に向けます。
種継は式家百川の兄清成の子で政務全体を任されていた出来人(できびと)でした。物語の主人公薬子はこの種継の娘です。しかし、その種継が延暦四年(785)、新都長岡京(山城国乙訓郡)造営の最中(さなか)、現場で射殺される事件が起こります。
この実行者には大伴氏など早良の側近の旧豪などが多く、事件には早良親王の関与があるに違いないとされ彼は廃太子となり、淡路に流罪の途中、無言の抗議で自ら食を断ち山崎の地で果てました(後に崇道(すどう)天皇の尊号が贈られます)。
桓武は、これは百年ほど前の「壬申の乱」と同じ構図ではないかと宸憂(しんゆう)(天皇の心配)されたに違いありません。早良の死の裏には桓武の意向が働いていたに違いなく、種継殺害事件を逆手にとり早良廃しに結びつけたのでしょう。桓武はこの事件をうまく利用して、遷都の計画を益々強めていきました。