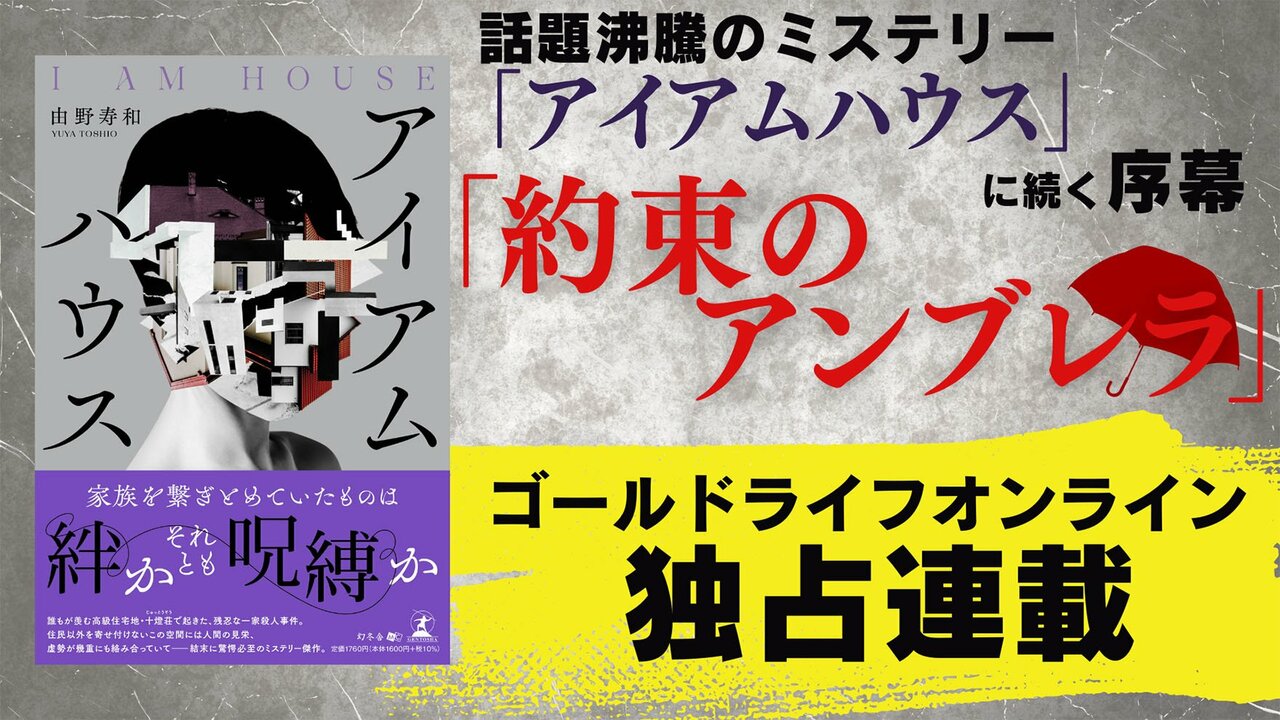「ねえ、ちょっと。仲山」
想像した娘の明るい声とは裏腹に、冷たく苗字を呼ぶ声が聞こえた。そう、惟子だ。彼女は出会った時からずっと、仲山のことを苗字で呼んでいた。
ベージュのトレンチコートにボブヘア、化粧は薄めで淡泊な表情を作っている。その隣には手を引かれて歩く女の子がいる。間違いない、凛だ。鮮やかな黄色いコートを着ておめかしをしている。顔はどことなく惟子に似て淡泊だが、目は少し自分に似ているような気がして、仲山は笑みを作った。
「おう、久しぶりだな。電車混んでただろ」
意外とうまく挨拶ができた。連絡は定期的に取っていたが、気まずくないはずのない元女房との再会にしてはなかなか爽やかといえるだろう。
「ええ、久しぶりね。あなたが娘に会いたいなんてどういう風の吹き回し?って最初は思ったわ」
「俺は父親だ。会いたいと言っても罰は当たらないだろう」
「ええ、そうだけど、あなたが父親として何かしたの? お金を振り込めばいいってわけじゃないのよ。親はお財布じゃない」
「ああ、わかってる。すまない」
と仲山は頭を下げた。
「まあいいわ。とにかく今日は凛をよろしくね。ドリームアイの申し込みチケットが当たったから、あなたにお願いすることにしたんだからね」
「もちろんだ。ちゃんと、ほら、俺と凛の名前で予約が取れた」
「よかった。一番人気だものね」
惟子は凛に向って笑いかけ、それから顔を上げた。
「夜八時に迎えに来るから、またここで会いましょう。あと……その時に大事な話があるの、どうしても話しておきたいこと」
それを言う惟子は、今までとは違ってどこか苦しげな表情だった。一体何があるのか。仲山は想像を巡らせつつも、今は頷くだけに留める。
「ああ、わかったよ。なあ、見ないうちに凛、随分と大きくなったな」
前を呼ばれた女の子は、惟子の陰に隠れて俯いた。母親は冷静に娘のことを語る。