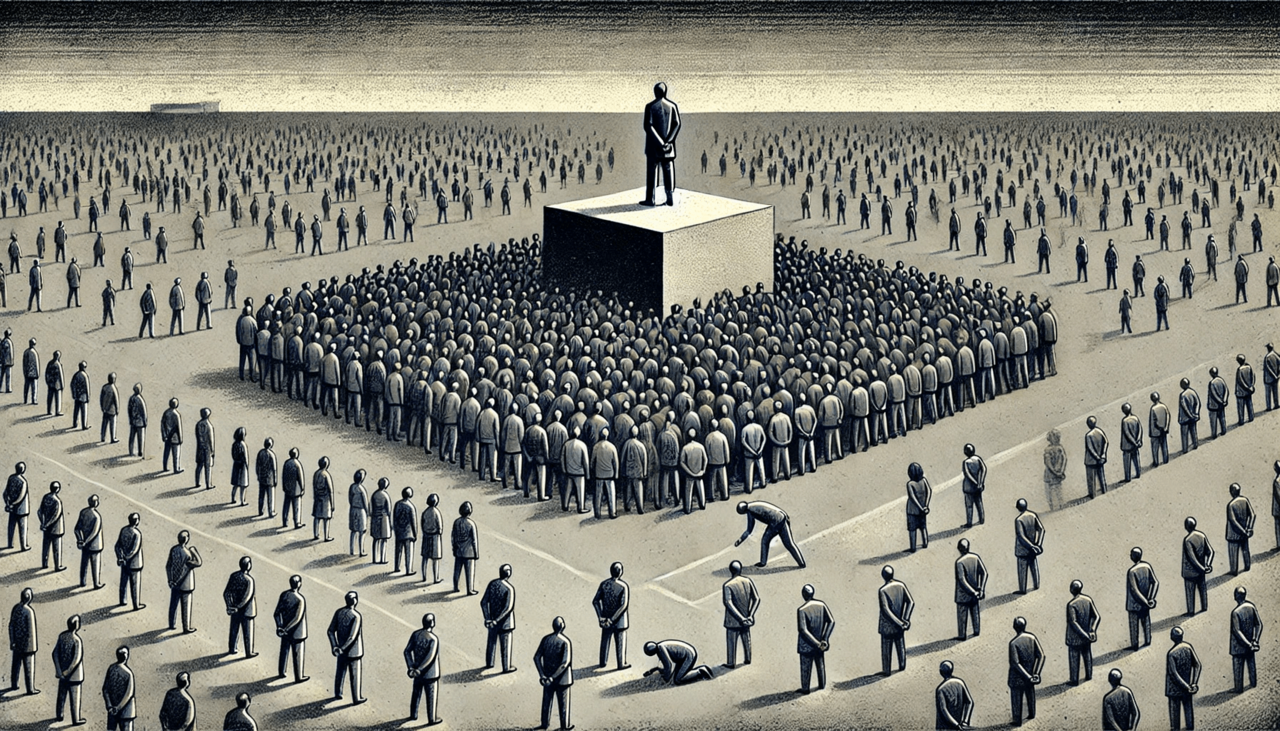第三章 望みどおりの人生
四
その日の夜、仕事を終えたわたしは、ランプの明かりのもとで、晴子の母親に宛てて手紙を書いた。薬充ミホや万由香李がしゃべっていることは嘘で、城屋の工場のことは、政治の争いに利用されているだけだと、はっきり書いた。
そして、晴子が楽しく過ごしていたことを、具体的に書いた。
晴子は給料日にキャラメルを買うのを楽しみにしていたこと。洋装店のショーウィンドーを眺めるのが好きだったこと。寮にときどきふらりと来ていた三毛猫をかわいがっていたこと。休みの日に遊園地に行ったこと。新国王戴冠式の夜、寮の窓から打ち上げ花火を眺めたこと……。
恋人がいたことは、書かなかった。晴子は家族に知られたくないと思う。晴子の恋人は陸軍の中尉で、彼女より三つ上の二十七歳だった。地方の旧家の息子なので、晴子は結婚は望んでいなかった。
晴子は、「弟が学校を卒業したら村に帰って、親の決めた相手と結婚するの」と言っていたが、本心は語らなかった。
晴子はほんとうにやさしくて、気立てがよかった。なにより、明るい人だった。
わたしは涙をぬぐいながら手紙を書いたが、書いているうちに、これまでさりげなく心の中にあった思い出が、じつはかけがえのない、大切なものだったと気づいた。
わたしは、薄汚い嘘に動揺している晴子の家族に真実が届いて、少しでも悲しみが癒えるよう祈りを込めて、手紙に封をした。
第四章 波紋
一
気がつくと、日が暮れるのがすっかり早くなっていた。朝も冷える。冬がはじまると、星炉さんの家の静けさは、ますます身に沁みるようになった。世間の風当たりが強くなったことで、よけいにそう感じるのかもしれない。
わたしはこの頃、店にいるとき、ときどき冷たい視線を向けられることがあった。わたしは日曜日の朝にパンを食べる星炉さんのために、家の近くのパン屋に買いに行っていたのだが、そこの店員も、わたしのことをいやな目で見るようになった。
そしてついには、「もう、うちに来ないでほしい」と言われてしまった。
そこの店に行けないとなると、ずっと遠くの店まで行かなければならない。もしかすると、そこの店員もわたしのことを知っていて、売ってくれないかもしれない。
わたしは困ったが、黛さんに相談すると、「パンはあたしが買ってくるから」
と言ってくれたので、助かった。