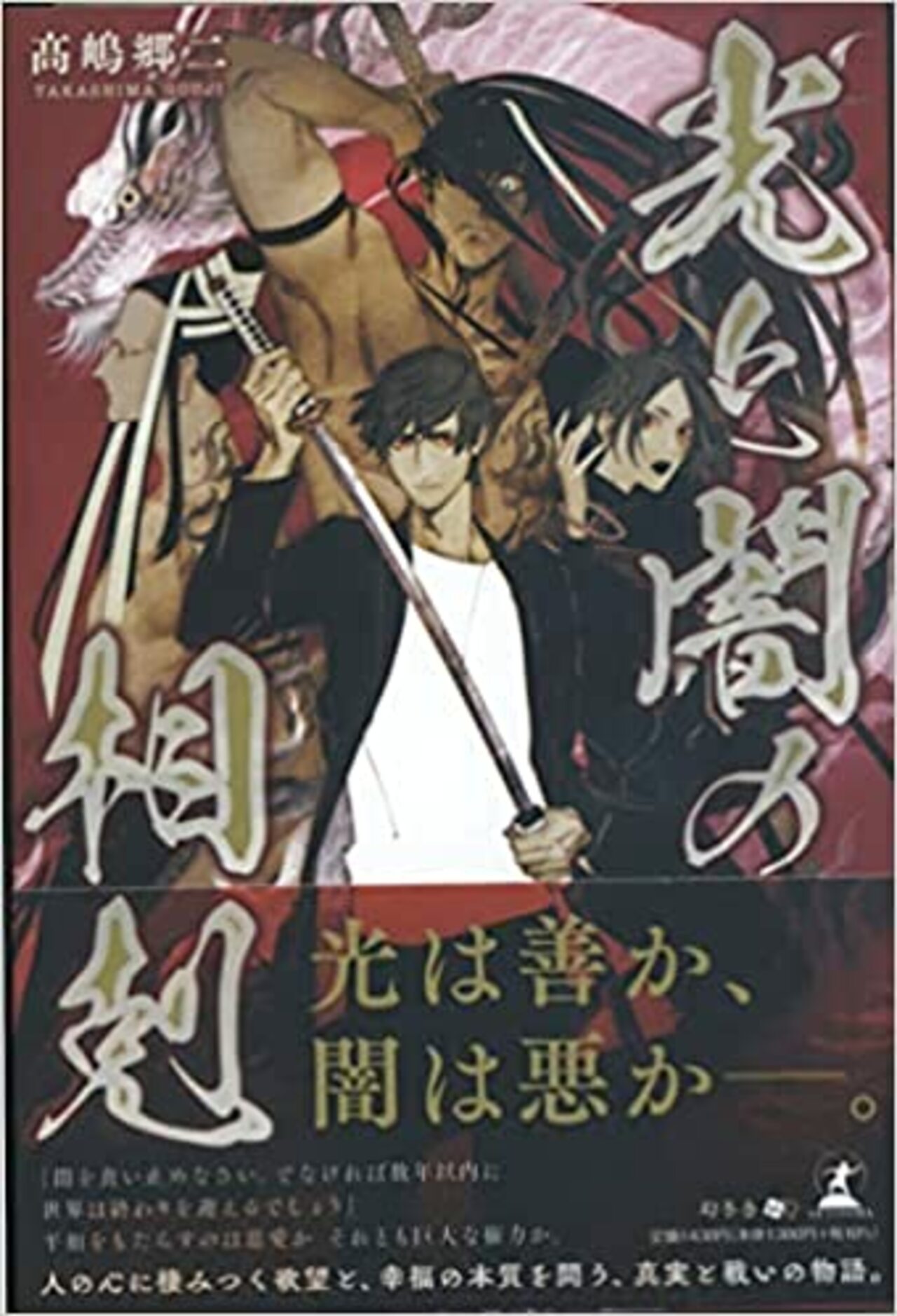太陽神の言葉に英良は小さく頷いた。
「弱きものが波に飲まれていく。地鳴りと共にだ」
英良は眠りから覚めたようにソファーから身を起こした。腹筋と背筋それに大腿筋に筋肉痛を感じた。異常な疲労だった。
回想の母
英良が十六歳の高校二年の夏休みのことだった。英良は母が入院している旭川市内の病院へ向かった。自宅から自転車で二十分ほどの所にその病院はあった。
病院はいつ来ても異臭を感じるが、英良はその臭いが嫌いではない。正確に言うと気にならないほうだ。その独特の臭い、院内では感染を防ぐために病室、診察室や待合室などあらゆる場所を消毒するために消毒剤を使っている。その消毒剤の臭いや治療や検査に使う薬品によって、日常生活では感じることのない薬品の混在した臭いを感じるものだ。
子供の頃から英良はいつも自分のことを変わったやつだと感じていた。人が嫌うものや事象を嫌わず、人込みを避け一人で行動することが多かった。友人を多く作らず、ガールフレンドもいなかった。多くの人間がやるような習慣的な行動は一切取らない。自分を変わった人間だと自負している。
英良は受付で顔見知りの女性職員に要件を告げて病棟に入った。その女性職員は瞳が大きく、はっきりとした二重瞼で化粧はさほど濃くはないものの美人だった。
身長は一六〇センチくらいだが、声はよく通り張りがあり、髪は長く、後ろでリボンのバンスクリップで留めていた。身体は太っておらず、胸もさほど大きくないが、乳房のふくらみははっきり見え、腰は良くくびれて骨盤は大きく日本人離れした体格をしていた。
会計の窓口には右手で杖を突き、大声で怒鳴り職員に苦情を言っている高齢者の男性患者がいたが、周りの人は関わるのを嫌い無関心を装い、日常生活とは全くかけ離れた場面のように自分とは異空間のような雰囲気で一線を画していた。
その男性患者の後ろには赤ちゃんを抱いた女性が距離を置いて待っており、横からはストレッチャーに寝かされた患者が通り過ぎて行った。