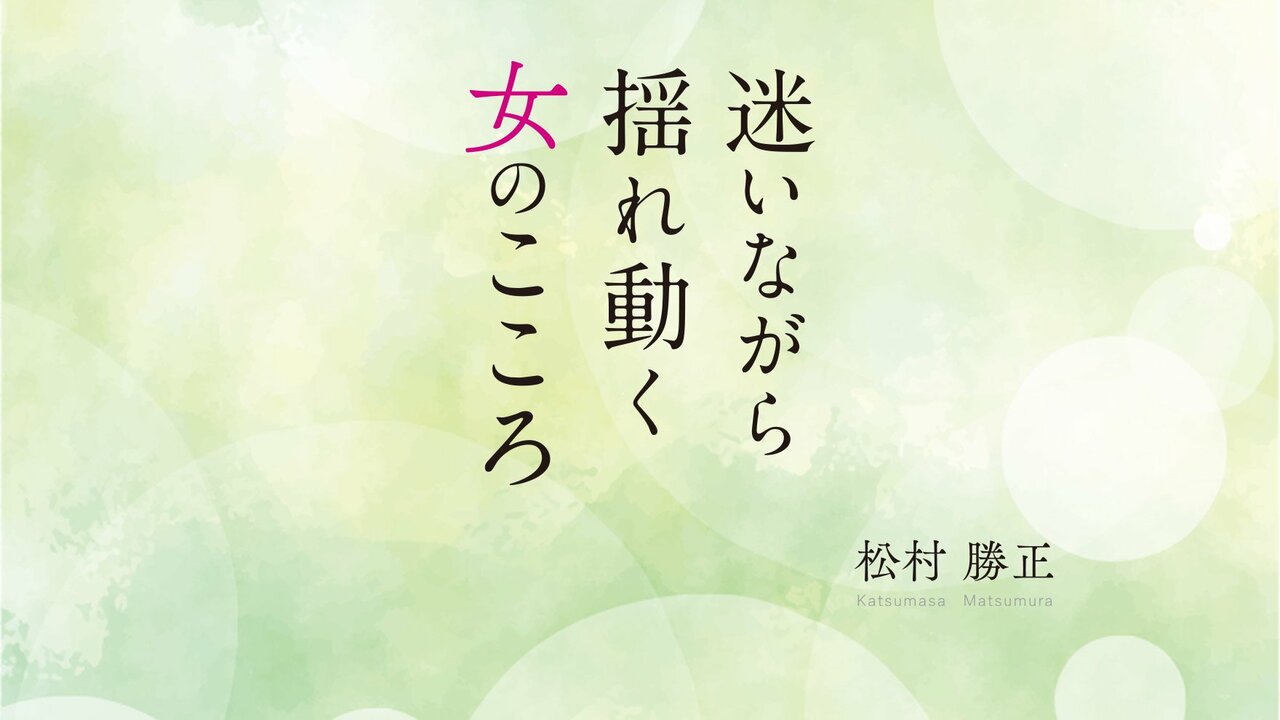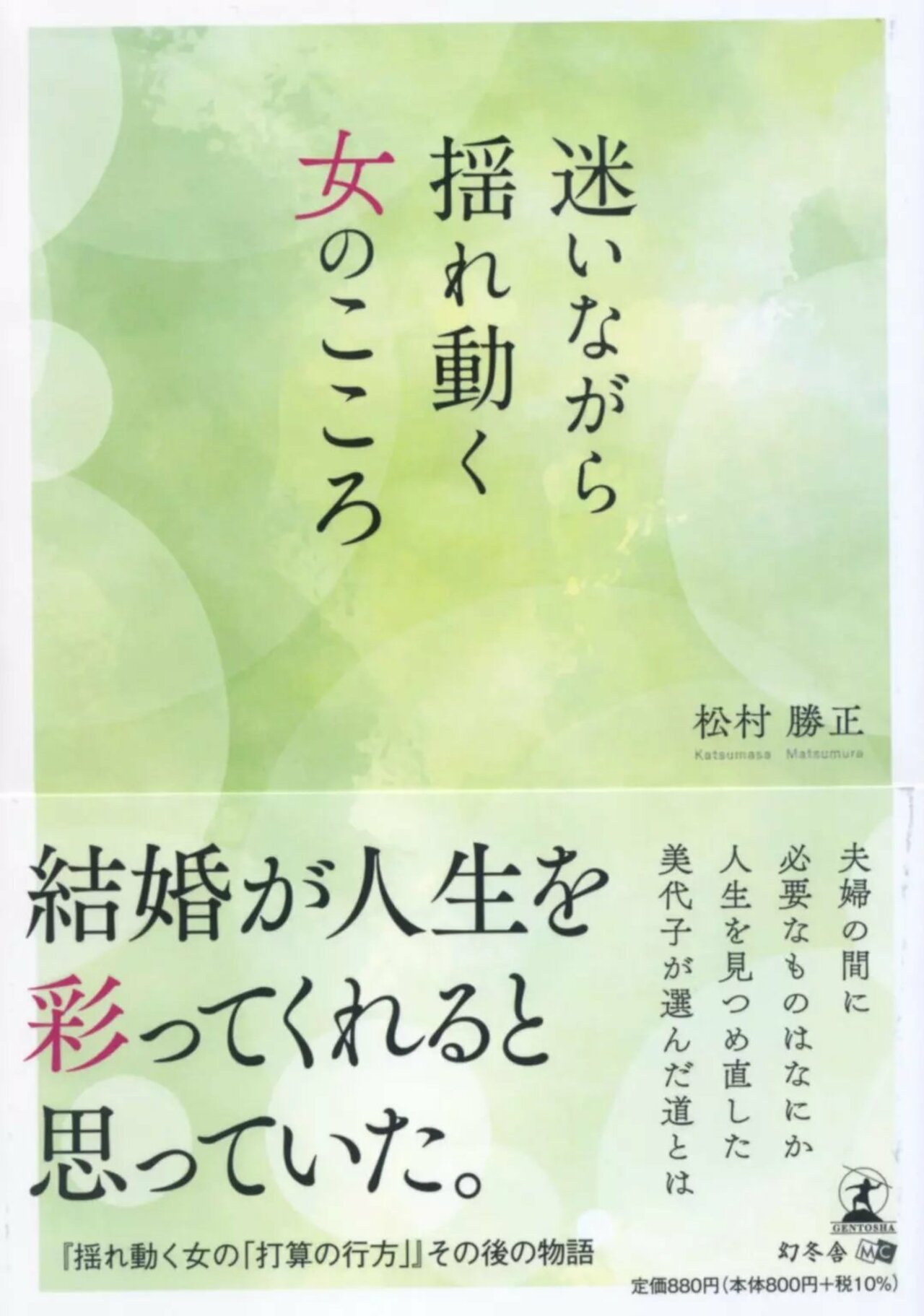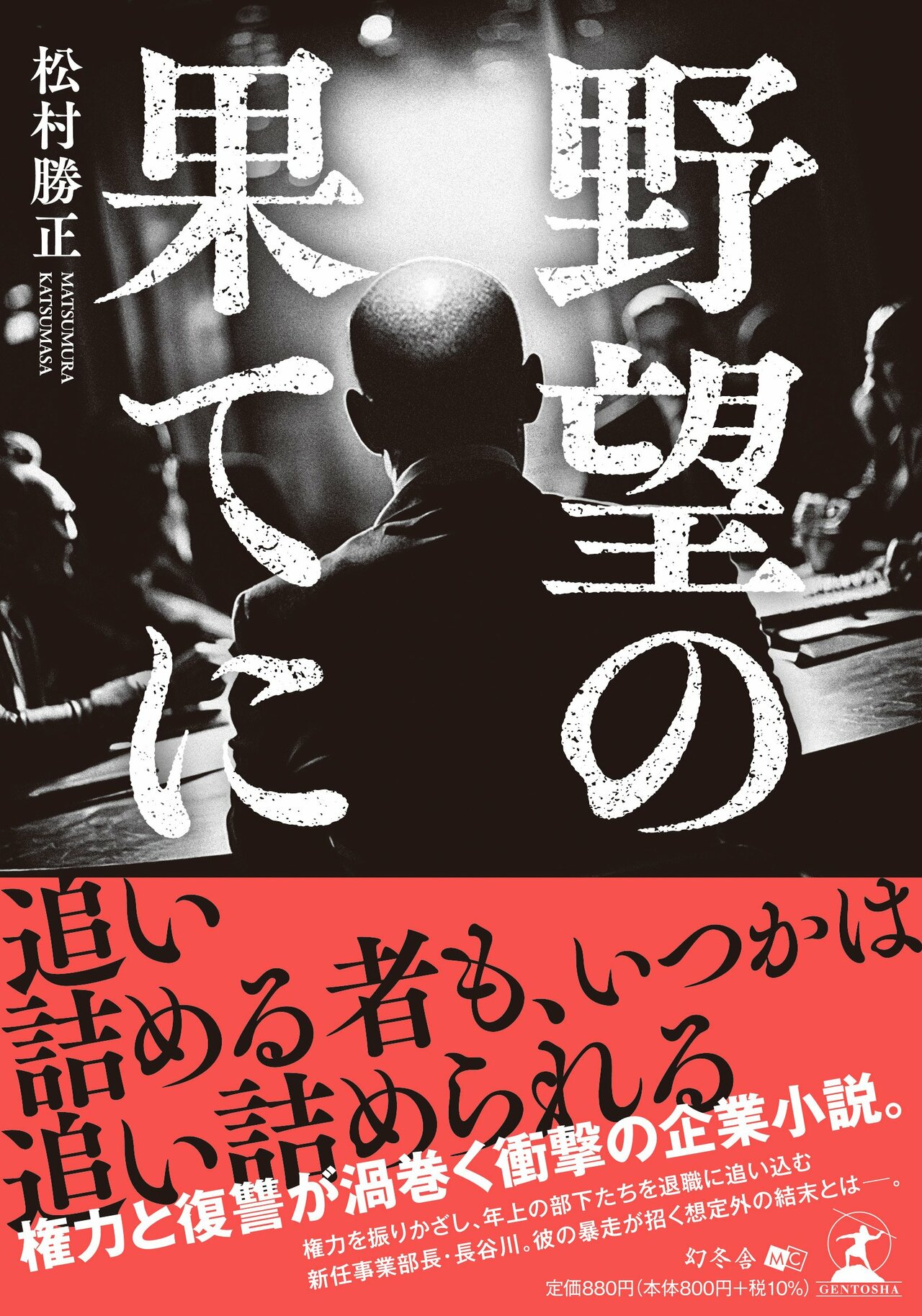迷いながら揺れ動く女のこころ
笑いながら「毎日同じ屋根の下にいて、男っ気がない生活してるのに、益々おばさんになる一方よ。からかわないでください。私だって美代子さんみたいにフィットネスをやって都会の空気を吸ってみたいですよ」
「ごめんなさい、そういう意味で言ったんじゃないですから」
「分かっていますよ」と言い、美月は台所に戻り、主人の事務所にお茶を入れる支度をした。美月は美代子が発した「色気」という言葉に引っかかる部分があったが敢えてそれ以上に反応をしなかった。
美月はこの前の美代子が主人の入浴介助をした日の夜のことは、自分の秘め事として閉まっておきたかった。
あの日以来、悠真さんも美月との距離を少しおこうと意識していることは感じられる。美代子さんは何も知らないはずだと信じていた。
美代子さんがジムに通うようになってから、週に三日は外出する日がある。その日に限って美月はいつもよりお化粧を念入りにして、皮膚の老化現象に負けないように少しでも若さを保つべく時間をかけた。男の人は得てして鈍感だから、少しの変化には気が付かないだろうと思いつつ、主人と接する時間が長いから介助の時の仕草にも気を遣うようになった。
主人は朝方事務所に入ると、トイレと食事時間以外、出てくることはまれだ。
八畳程度の広さがある事務所には、デスクとソファーがあり、くつろぐために四十インチサイズのテレビも置いてあるから、天国みたいな自分の城だ。仕事用と個人用のパソコンがあるが仕事用には長時間向かっていることが多いので、大きな画面にしているようだ。客先とはパソコンのメールでほとんど用が済み、たまに携帯電話のやり取りの声を聞くことがある。
美月は、午前と午後に、ほぼ決まった時間にお茶またはコーヒーを持っていくぐらいで仕事中は美月から声を掛けることはない。
*