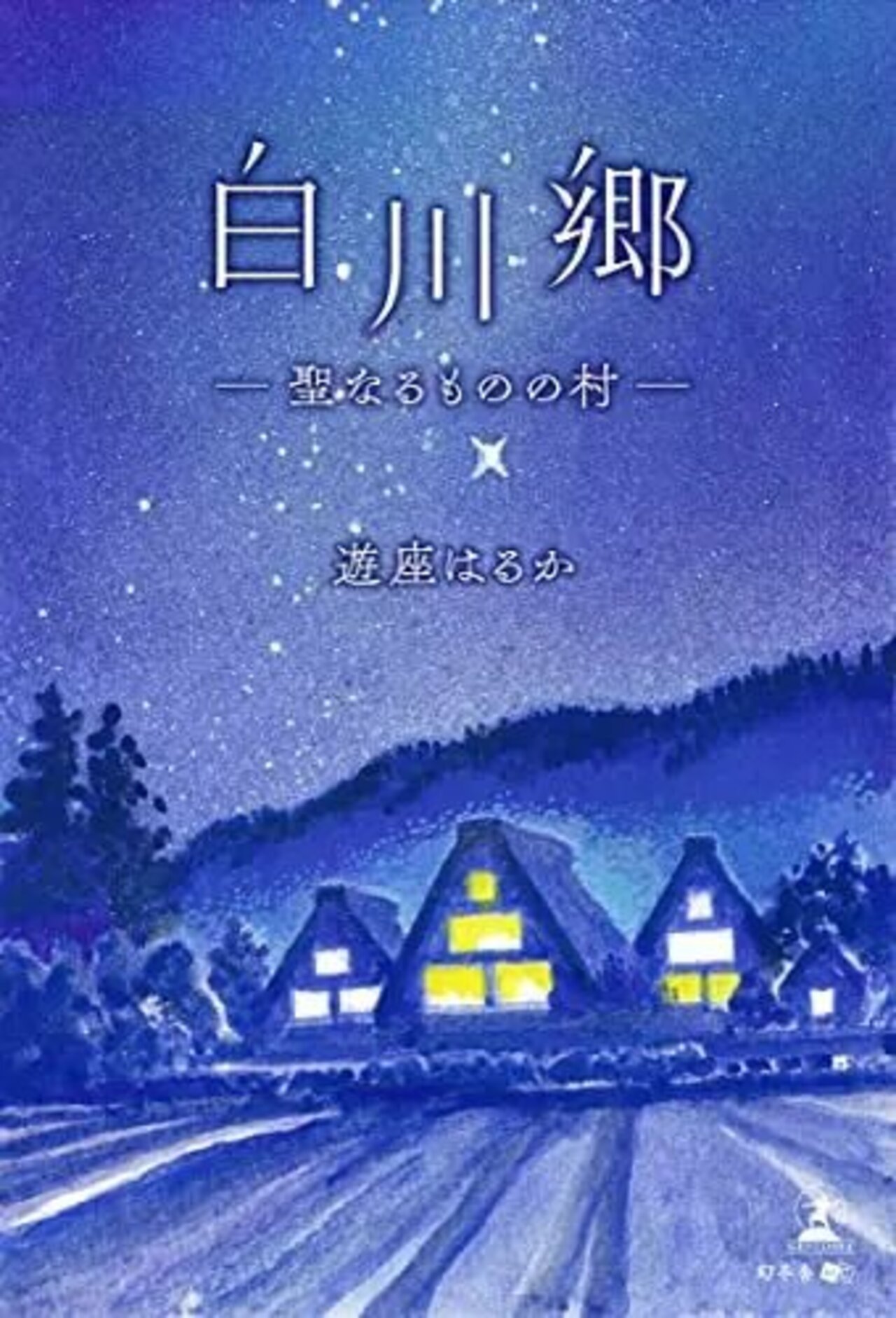数年前の、公開家屋になっている巨大合掌の家の葺き替えの写真を見ると、誰も命綱をつけていない。ベテランが、未熟な若者を仕込んでいって、やがてその若者が次の世代に技術を伝えていくから、村人ならばみんな出来るというのだ。が、篠原は自分の身に引き換えて考えると、非常に危険だと思うのだった。宴会の時、篠原は河田にそのことを聞いてみた。
「もし、落ちたら、どうするのですか? 保険とか、入っているのですか?」
「いやあ、落ちないて」
「でも、もし落ちたら大けがしますよね。死ぬことだってありますよ、あの高さから落ちたら」
「落ちんのやさあ」
河田もみんなも、笑っていて、保険に入る話など、誰も考えてもいないのだった。みんなで屋根の葺き替えをすることだけが目的で、あとは一切考えていないのだった。
村人は元から一人一人ではなく、屋根の葺き替えをする「一つの塊」という感じだった。都会の感覚ならばほとんど「献身」といってもいいほどの無償の奉仕なのだが、当たり前なのだった。
篠原は、どうしても信じられなかった。どうして他人の屋根のために自分の命を危険にさらすようなことが出来るのだろう。同じ東京出身なので、河田夫人の瑞江に面と向かってユイについて聞いたこともあった。
「奥さんは、東京で河田さんと結婚して、一年後に白川郷に来たのですよね? 凄い環境の変化で、大変だったんじゃないですか? とくにユイって、どう思いましたか? すぐに馴染めましたか?」
「いえ、全然。ユイだけでなく、村のすべてに馴染めなかったわよ。東京もんの掃除はザツだから、やり直しだ、なんて言われたり、聞こえるように悪口を言う人もいたしね。でもわたしにもいろいろあったの。ちょっと長くなるけど話そうか」