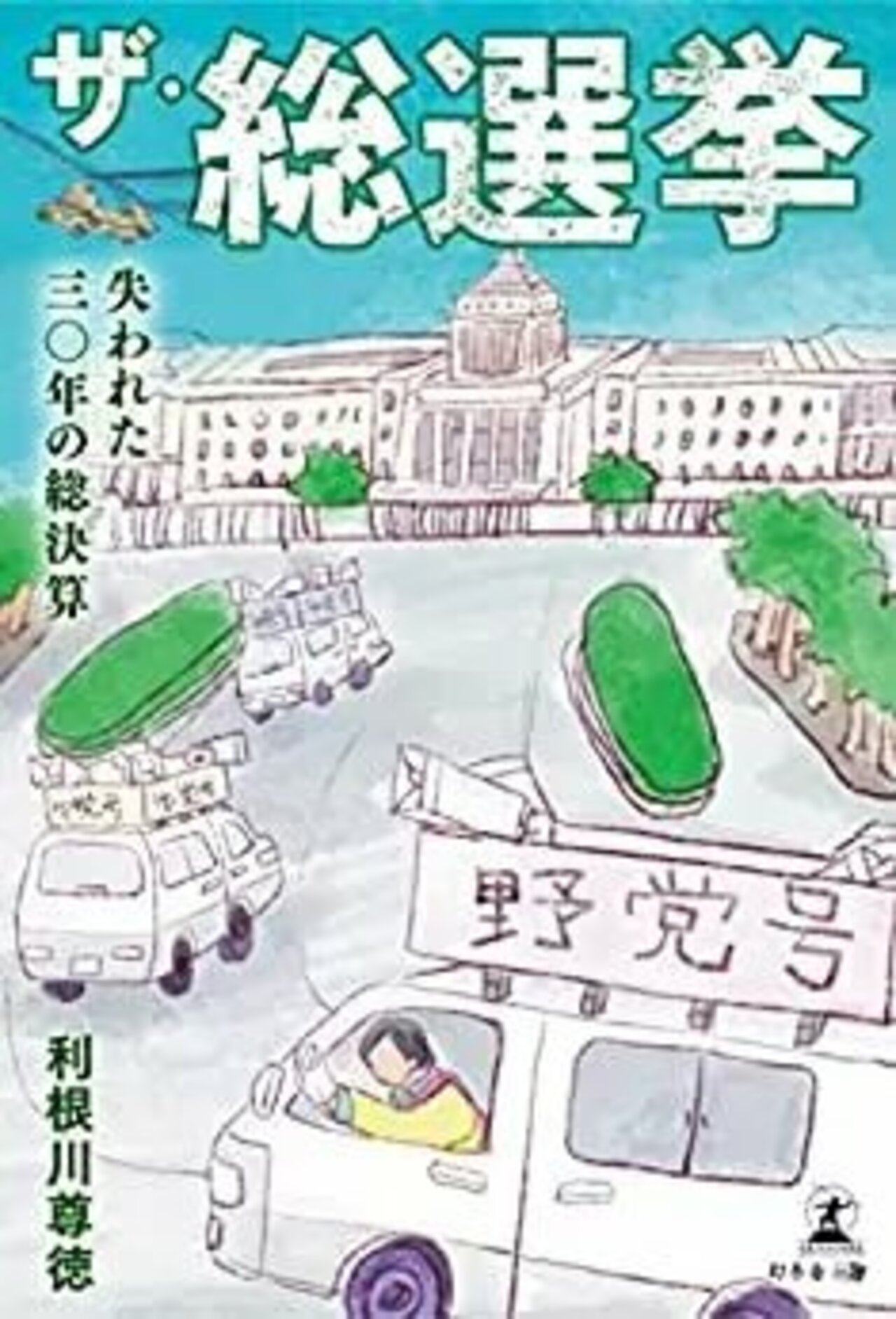第一章 「刑務所が足りない!」
「検事、桜田という女性警部が検事に面会を求めて、訪ねてきていますが?」検察事務官の冬木が団検事に伝えた。
「えっ、桜田? ……ああ、あの警視庁の権化みたいな桜田警子警部か?」と検事が冬木事務官に確認するかの様に言ってきた。
「そうです! その警視庁の権化みたいな名前の女警部で児童・母子福祉警察所属とあります」と事務官が答えた。
「俺、いない事にしろ!」といかにも訝しそうに団が言うと
「無理です。今更居留守は使えません。忙しいからとか……何か理由を付けて追い返されてはいかがですか?」と冬木は言った。程なくして団の検事室のドアがノックされた。
「失礼します」女性の割には野太い声で一声を発した後、ドアが開き桜田警部が入ってきた。居留守は使えないと観念した団が精一杯怪訝そうな顔をして、
「おや、桜田警部、私にアポなしで火急の要件でも?」と皮肉交じりに言うと
「私達が送検した殺人未遂と強制性交致傷事案を訴因変更して、単純傷害致傷で不起訴処分とは何事ですか? 私に、納得できる説明を求めます!」と険しい明らかに強張った顔付きで質してきた。それに対して団は、俯いたままで
「……やはりその件でしたか? ……貴方のお怒りはご尤もです。ですが……物理的に不可能なのです」と辛うじて聞き取れる程度の声でこう答えた。
「えっ? 何をブツブツ言っているのですか! 起訴権は検察官にしかない権能です。法の番人等といっておきながら殺意を持って刺したという被疑者の供述があるのに何故検察官がそれを否定して単純傷害致傷事件に訴因変更するのですか? 馬鹿げていると思いませんか? こんな不埒事、私は到底受け入れられません」と思いの丈をぶつけてきた。
「だから、物理的に無理なんだ! 物理的に一年間に開廷できる裁判員裁判の総数はおよそ一二〇〇件が限度、裁判員裁判を開くには一八歳以上の日本国民から無作為抽出で裁判員六人と予備人員を最低でも二人ないし三人選ばなければならない。
そして、一旦公判が維持されると判決を得るまでおよそ六か月を要するのが現状で裁判員への負担も大きいのが現実だ。
裁判員裁判が開始されて一〇年以上、裁判員の数を半減させるとか、死刑や無期懲役となり得る裁判に限定する等の改善策が急務なんだ! 最早物理的限界なんだ」と団が桜田に向かって真正面から反論してきた。
「だからと言って、公判前なのに殺人事件の被疑者を保釈した為自殺され、被疑者死亡による控訴棄却で、法曹界があれだけ世間から批判を浴びた反省は検察にはないのですか?」と桜田に問われると
「自殺された被疑者を保釈したのは検察ではない! 裁判所の決定だ! 責任は裁判所にある」と団が開き直りとも取れる発言をした。