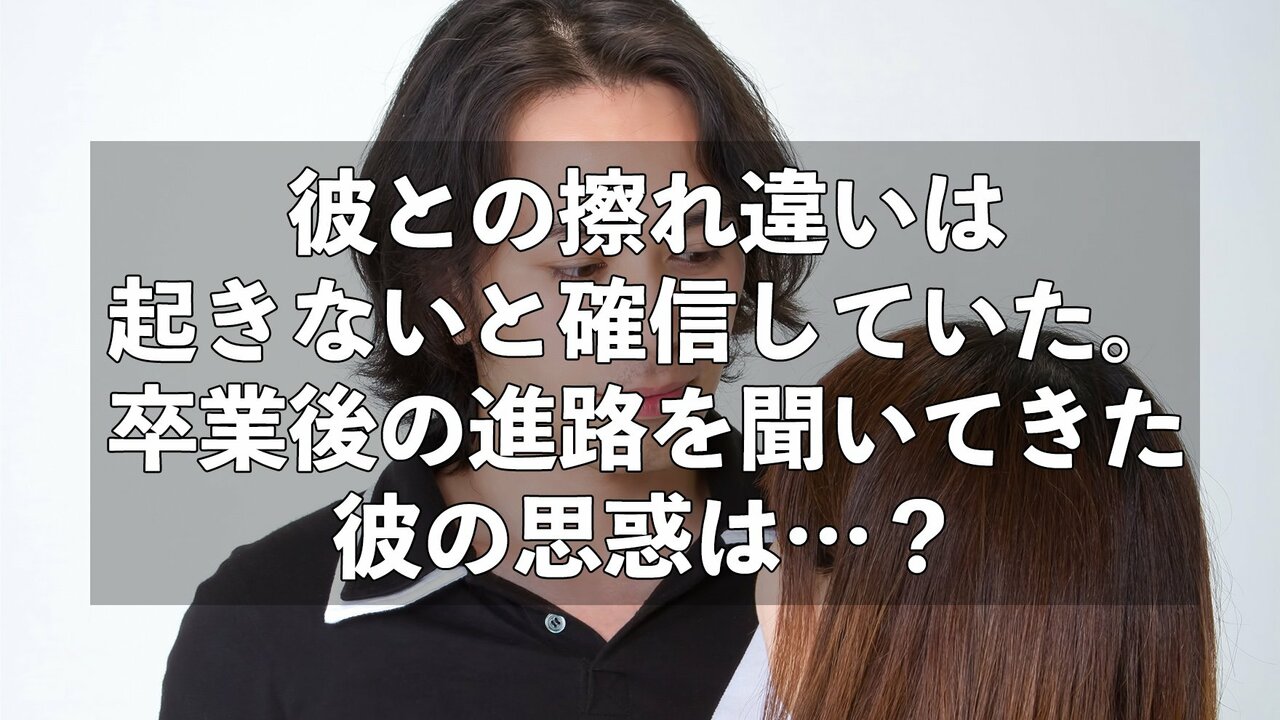ベスト・オブ・プリンセス
「あの、この飲み会って何時までですか」
「えっと、たぶん二十二時までかな」
「すみません、明日一限からでレポートもあるので、先に帰ってもいいですか」
次の日に一限から講義があるのは事実だったが、一刻も早くこの場所から抜け出したかった私は、慎二に嘘をついた。それに、こんな愛想のない雰囲気が漂う新入生なんて、彼もこのサークルも必要としていないだろう。そう思いながら、手早く上着や荷物をまとめだした私に、慎二は意外にも、大丈夫だよ、と先ほどより静かな口調で途中帰宅を許可し、明日早い人とか終電早い人は途中抜けしていいからね! と声高に宣言した。
「美夏ちゃんさ、このサークル入る気ないよね」
みんなが酒と秩序のない会話に夢中になる中、慎二は私を居酒屋の出口まで見送ってくれた。そのとき、私の心が伝わっていたことに少しの申し訳なさを感じた。そのことを慎二に詫びると彼は、みんなそんなもんだから。と言った。
「でもよかったらなんだけど、連絡先交換しない?」
学部違うけど選択科目とか、単位取りやすい授業とか教えるし。
そう言って慎二は青いプルオーバーのスウェットパーカーのポケットからスマートフォンを取り出した。会ったばかりの初対面の人間に連絡先を教えることに私は少し抵抗があったが、同じ大学であることと、彼が先輩であることを理由にその申し出を受け入れた。
その後、慎二から連絡があることは正直ないと思っていたが、彼は頻繁に連絡をしてくるようになり、休日にはふたりでの食事にも誘われるようになった。これまでの学生時代のほとんどを部活動に費やし、まともな恋愛をしてこなかった私ですらも、その頃には彼の思考がなんとなくわかるようになっていた。
そしてその年の十一月の終わり、私は慎二から告白を受けた。
そのとき私の中には、彼のことを好きだという確かな自覚はなかったが、異性から向けられた初めての恋慕に高揚していたのは確かだった。
後日、恋人関係になってから出かけたテーマパークのアトラクションの待ち時間に、私を好きになった理由を問うと、彼はぼんやりとした口調で、一目惚れだった、と呟いた。その答えに私は、こんな大した特徴もない人間のどこに魅力を感じたのか疑問を抱いたが、彼の照れくさそうな微笑みを前に、その胸中をぶつけることはしなかった。
慎二との恋愛関係は概ね順調に過ぎていった。周りの友人たち、特に学年が異なるカップルはどちらかの就職活動などをきっかけに会えない時期が続いて破局を迎えていたが、彼は卒業後の進路が決定していたため、その類のすれ違いは起きないと私は勝手に確信していた。
私の卒業後の進路について、慎二が尋ねてきたことはこれまでなかった。