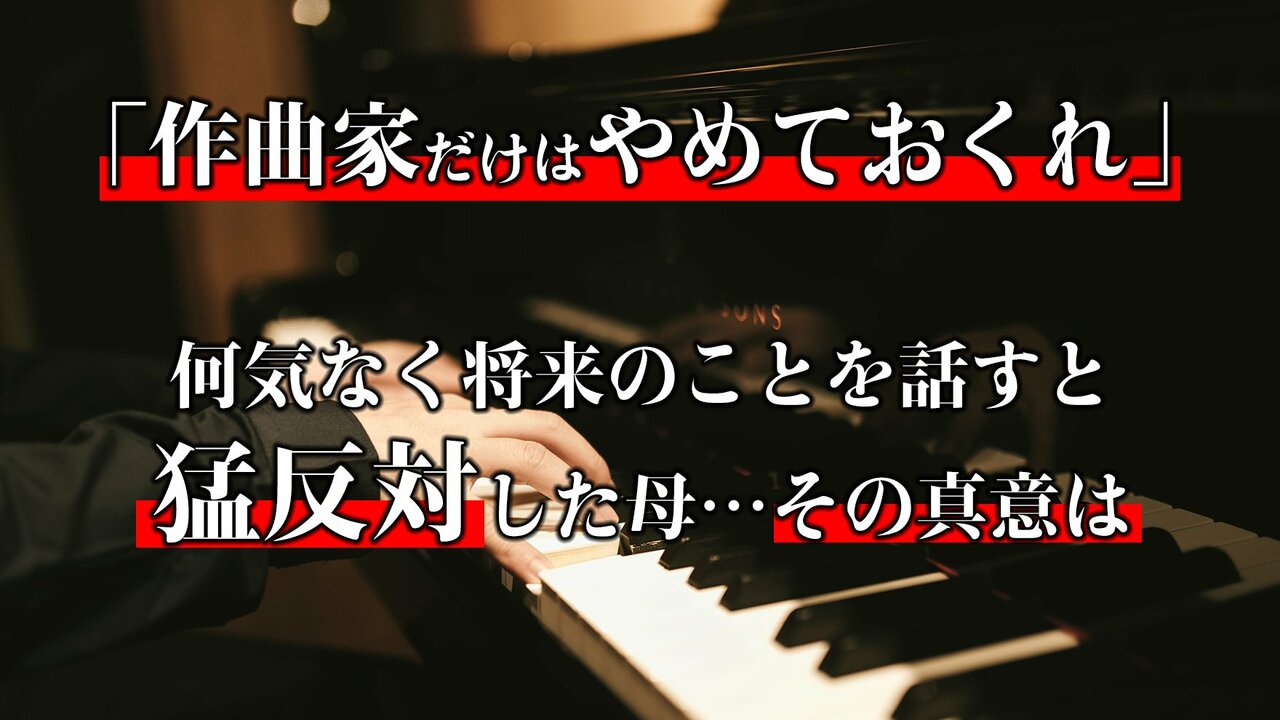第一部
五男 忠司 ── 素晴らしき音楽家
正吉と忠司は同じ部屋で学生時代を過ごした。正吉のために母・たまが買ったオルガンで、二人は学校の唱歌やイタリア民謡、ロシア民謡を弾いたり歌ったりした。これは、のちに正吉が映画監督になり、忠司がその音楽を担当することになったとき、大いに役立ったのである。
浜松第一中学校(現浜松北高等学校)を卒業した忠司は、すぐには自分の進路が決まらなかった。しかし、中学時代の旧友・尾崎宗吉の影響から、音楽学校に行きたいと思うようになった。
初めてその気持ちを両親に打ち明けたとき、両親は驚きもしただろうが、「どうしたら音楽学校に入れるんだ」と言ってくれた。そして、上京して音楽の勉強を始めた。一九三四(昭和九)年、忠司十八歳のときである。
忠司は諸井三郎に師事し作曲を学び、武蔵野音楽学校(現武蔵野音楽大学)に入学し、卒業している。その頃の恵介は、念願の松竹撮影部に入社し、一九三六(昭和十一)年には島津保次郎により助監督に引き上げられていた。
このとき松竹は大船に移転したが、蒲田時代から恵介のために母・たまが借りた一軒家があったので、忠司はそこから音楽学校に通った。ピアノが置いてあり、お手伝いさんまで雇っていたので、何不自由のない生活だった。
ある日、母のたまが上京してきたとき、忠司は何の気はなしに、作曲の勉強をしていて作曲家になることを話したことがあった。それを聞いたたまは、突然泣き出し「作曲家だけはやめておくれ。あんな頭を使う仕事をしたら長生きできない」と言った。
たまの頭の中には、若くして世を去った滝廉太郎とか、歌人の石川啄木、胸を病んでいた芸術家たちのイメージがあったのではないかと思うのであるが、そこまで心配してくれ、愛してくれた母のことを思い出すたびに目に涙が浮かんでくると、一九八四(昭和五十九)年、静岡新聞に連載した「わが青春」の中で語っている。忠司六十八歳のときに書いた文である。
話を当時に戻すと、恵介はこの家に、まだ助監督だった吉村公三郎や中村登、大庭秀雄などの撮影所仲間を連れて来た。忠司は彼らにかわいがられたことで、後年映画音楽の世界に入ると、松竹で監督になった吉村や中村や大庭らの監督たちが、映画音楽に忠司を使ってくれるようになったのである。