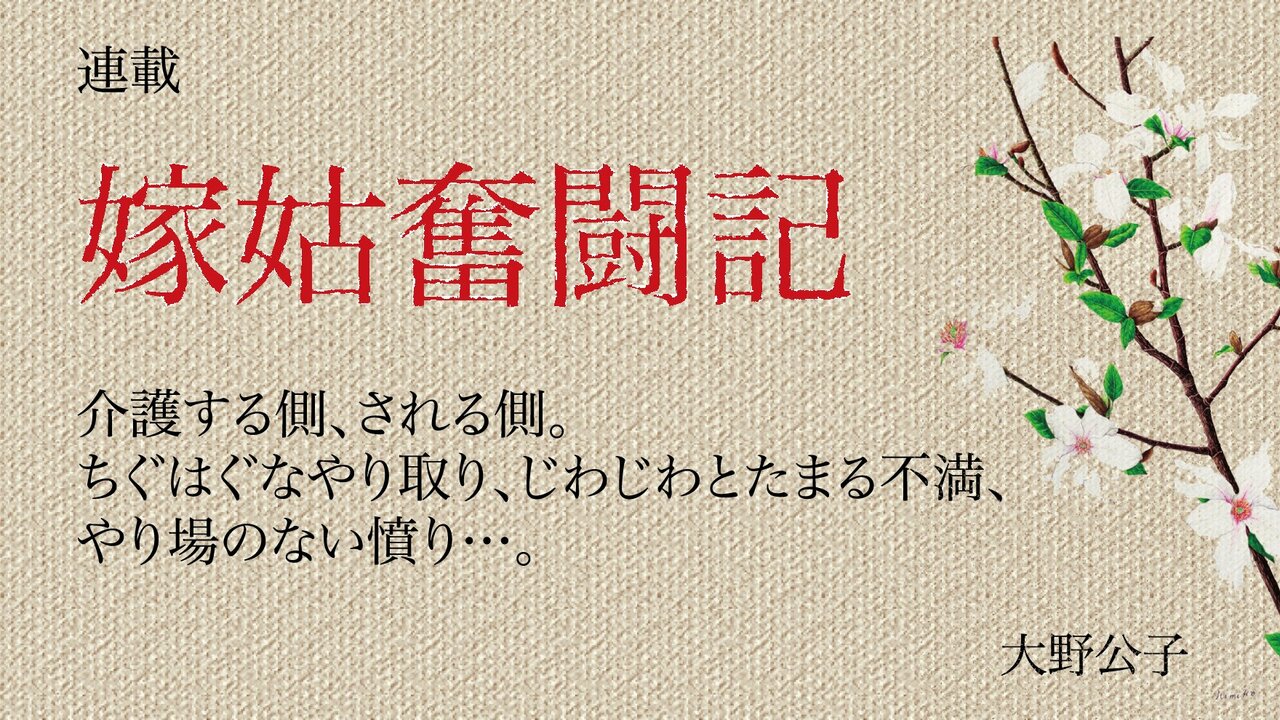第一章 嫁姑奮戦記
気分がまだ悪いと言う。血圧を測ってくださるが異常に高い。そのせいかもと言われる。動くと吐き気がすると言うので、用をたす時便器を当てるが出来ず、おむつにも出来ないので、仕方なくポータブルトイレに座らせるがまた吐く。赤茶色なので保健師さんに見ていただく。
夜中に、今度は大便がしたいと言うので便器を当て摘便してただく。その後は元気だが、妄想が強くずっと起きている翌日の胃カメラで多数の潰瘍が見つかる。薬やストレス等が原因だろうということだった。
ヘルペス、骨折、胃潰瘍、次から次と厄介な状況が加算されてくる。こうなると、最初の一日が悔やまれる。
今日から恐怖の七十二時間ぶっ通しの点滴だ。夕方から娘が付いてくれる。朝方とろっとした途端にまたもや針を抜き大変だったらしい。
もう、かれこれひと月になるのに精神状態は一向に改善しない。困ったものだ。午前中娘と代わった時は大鼾、目を覚ました姑に、「点滴抜いて血だらけになったそうやないの」と言うと、「赤ん坊が産まれてん」と嬉しそうに言う。多分先程の下の洗浄と血が結びついて妄想となったようだ。しばらくして姑を見ると、とても穏やかな顔をして胸の所をしっかり押さえている。
「何を持ってるの」と布団をめくるとタオルをしっかり抱き「赤ちゃん抱いてるねん」と幸せそうに言う。姑もどんなにか自分の子供が欲しかっただろうと思うと、胸がじんとする。彼女の魂は若い頃をさまよっているのだろうか。
日頃はおくびにも出さない姑の心の奥を見たようでショックだった。そういうことで、その日は姑が何をしようと叱る気になれず、優しい嫁だった。
翌日から夫が連休に入るので、その晩から代わってもらう。夫によると元気いっぱいで、点滴を抜こうとするやら動くやら妄想がらみのお喋りで全く眠らなかったらしい。翌日昼前に夫と交代する。
点滴を付けたまま車椅子でリハビリに連れて行く。近所の方が見舞いに来られる。看護婦さんにリハビリ室だと教えられたそうだ。しばらくお話しして帰られ、病室に戻ったらまた別の方が来ておられた。ロビーに姑を車椅子で連れて行き、そこでお話をする。
姑は絶えず点滴のチューブを引っ張り、ガードしてある包帯を外そうと躍起になっている。「これ一体何?」と聞くので、「ほれ、A医院でしていた点滴よ。その時はこんな引っ張ったり動かしたりしなかったでしょ」と言うと、「ああ、あれと一緒? 点滴言うんか」と言いながら、またいじる。
「この包帯みたいの何? 取ってくれへん」と言うので、「これは、おばあちゃんが点滴の針を抜かんように、ぐるぐる巻きにしてあるの。取ったら駄目よ」と念を押すが、そう、と言った後からもう取り外しにかかっている。
一時もじっとしていないし、理解出来ないのかすぐ忘れるのか、全く言うことを聞かない。揚句の果ては「さあ、家に帰ろか」と言って見舞い客を唖然とさせる。
「大変やねえ。あんたのほうが潰れへんか心配やわ」とため息をついて帰られる。
入院後ひと月もすると、シャワーの許可も出る。
娘に姑を頼んで夫と二人で大英博物館展を見に行く。現実を離れてしばし偉大な科学の世界を楽しんだ。
戻ってみると、およそひと月振りにシャワーを浴びた姑が清々しい顔で、お帰りと言ってくれる。シャワー室には娘とちょうど見舞いに来ていた姉が付いて行き、看護婦さんを手伝ったとか。
食欲も旺盛になってくる。以前は嫌々食べていたのに今はほとんど残さず、入院前より優秀だ。しかし、潰瘍の薬のせいか便がゆるく時々しくじり、その後始末に皆大変な思いをする。
外出許可が出たので、車椅子に乗せて病院の周辺や、近くの商店街に行ったりする。買物が好きな姑なので何か欲しがったり、あちこち見たがると思いきや、もう帰ろかとあまり喜ぶ様子もない。車椅子が恥ずかしいのか疲れたのか、おそらく両方だろう。
夫が付いている時、我が家まで車椅子で連れて帰って来た。五月というのに暑い日でおよそ三十分ほどの道のりを大汗かいて連れて来たのだが、姑はこれといって喜ぶ様子もなく、すぐ病院へ。
ひと月過ぎても夜は相変わらず動きまわり、妄想もきつい。