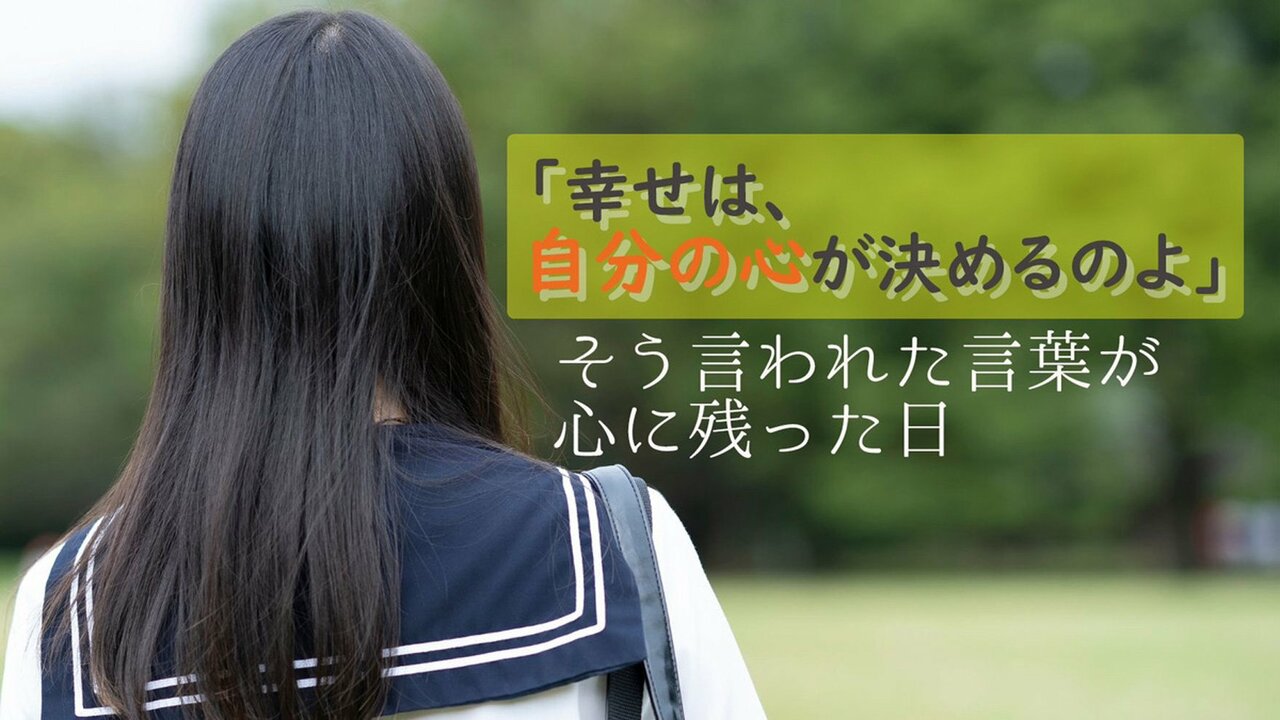第1章 山本果音
六.多重人格者
「保健室に何故、フラフープが?」と、最近よく聞かれる。
「フラフープのフーちゃんです。よろしく」
「プッ! 先生ネーミングセンスない~」
生徒には笑われたが、それだけでもバーバラにとってフーちゃんはありがたい存在だ。学校のゴミ捨て場で拾った、フーちゃん。壊れていない。きっと、誰かの思いが詰まっている。でも捨てられた。バーバラは一時的に、「この子」を預かることにした。せっかくだから、腰のあたりで、回してみる。
バーン、バーン……、あれ?
バーン、バーン……、あれ? あれ?
全然、回らない。もう一回。もう一回……。
「あ〜だめだ、こりゃ」
できると思ったことができないショックと、歳だからしかたないという諦めと……、気持ちが入り乱れた。何日経っても、フーちゃんは全く懐いてくれない。動画サイトを観て、コツを学んだりもした。そんな努力と居残り練習の甲斐あって、一週間でようやく、右回りだけはマスターできた。この間バーバラは、「ゴールデンエイジの頃にやっておけばよかった」と、何度も後悔したのだった。
ゴールデンエイジと呼ばれる時期、人は素晴らしい能力を発揮する。理屈抜きで、体が自然と覚えるのだ。その時期から何十年も経って苦労はしたが、やってやれないことはない。諦めずにチャレンジしてよかったと、バーバラは思う。そんなある日の放課後、ドアを叩く音がした。
「どうぞ」
入ってきたのは、今まで保健室にはほとんどきたことのない女子生徒だった。痩身で、とても綺麗な瞳のその生徒は「高三の神無月愛です」と告げる。
「ああ、神無月さん。どうしたの?」
愛は話を切り出しにくいのか、両手でぎゅっとスカートを握っている。
「バーバラ先生。あの、それですが」
愛がフラフープを指差す。
「あ、この子フーちゃん。よろしく」
「いえ、そうじゃなくて」
「うん?」
「それ、私のなんです」
愛の頬が赤らむ。
「え? ゴミ捨て場で泣いていたよ」
「実は、私が捨てたものです」
「そうだったの」
「はい。実は、新体操やめるつもりで捨てました。でもやっぱり、どうしても新体操やりたくて……」
愛の目が真っ赤になる。
「やっぱ、そうか。どうも私に懐かないと思ったよ」
バーバラは、フラフープを彼女の前に押し出す。
「はい、あなたのフーちゃん、お返しします」
そしてバーバラは、フーちゃんになったつもりで囁く。
「もう私を、離さないでね」
次の瞬間、愛の目から一筋の涙がこぼれ落ちた。何故かバーバラの目頭も熱くなる。愛は体育系の大学を諦め、奨学金の条件が揃った他の学部へ行くかどうか、迷っていると、正直に話してくれた。
愛の目から涙とともに、ポロポロと色んなものが流れているようだった。夕日に照らされた愛の涙を、バーバラはいつまでも忘れられないだろうと思った。のちに愛が、希望する大学に合格したと報告しにきた時には二人で喜びの涙を流すのだが、この時はまだそれを知る由もなかった。