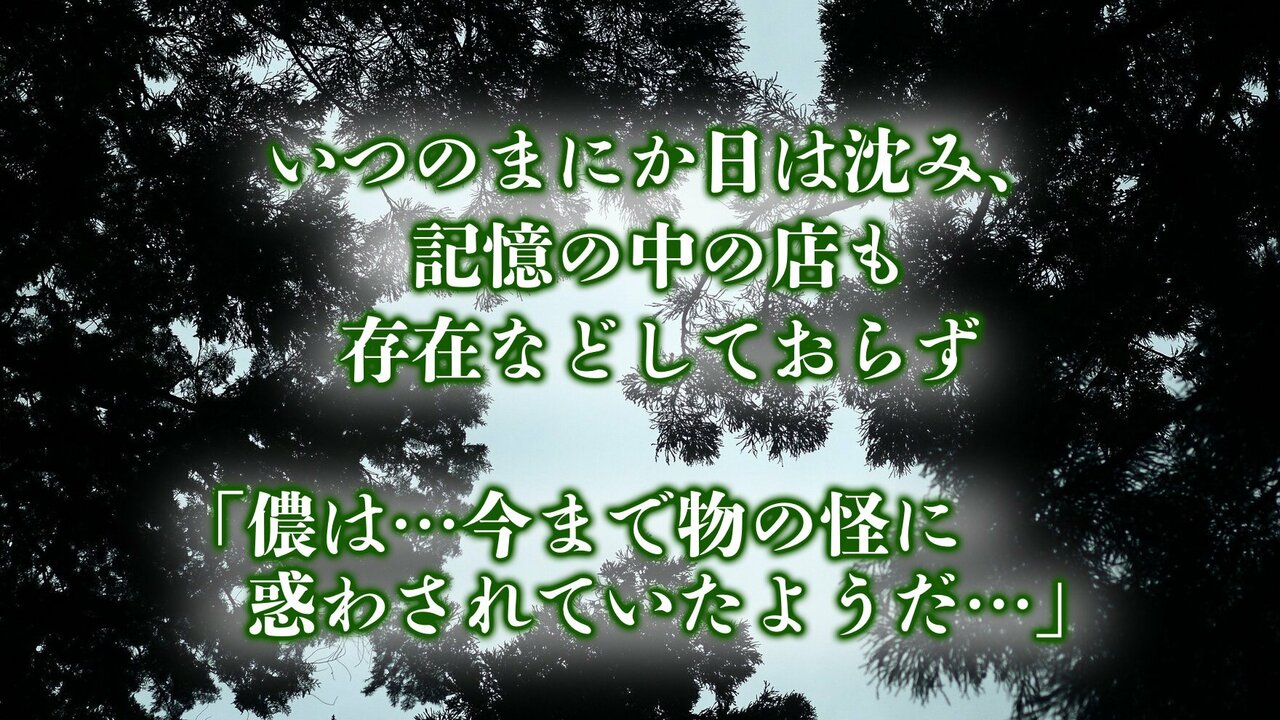一、羊の群
放心したように立ちすくむ李徳裕の顔を陽光が眩しく照らし、驢馬の鳴き声と荷車の車輪が軋む音、人足の掛け声で耳の穴が溢れかえった。往来の真ん中で呆けたように動こうともしない李徳裕の前を、波斯馬(ペルシャ馬)に乗った胡人が横切り、その後ろを十頭余りの羊を追う牧童が通り過ぎた。軽い目眩を感じながら李徳裕は瞼を擦り、混沌の西市の通りをふらふらと足を運び始めた。
「若君、若君」
「……………………」
「若君、何所にいらっしゃったのですか? お探しいたしました……」
耳鳴りのように近づく声で鼓膜が震え、立ち止まり視線を落とした。そこには額に汗した壮年の男が肩で息をしながら、李徳裕の前で膝を突いていた。

怪訝な顔で目の前の男を見ていた李徳裕が、思い出したように大きく目を開いた。
「おぅ、玄茗か」
「玄茗か、ではありませぬ、若君、一体何所にいらっしゃったのですか」
「そこの小さな店で玻璃の器を見ていただけだ」
「吾ら二刻余りの間、市の役人にも手伝わせこの界隈の店を探しましたが、若君を見付けられませんでした。不逞の輩に拉致されたのではないかと心配しておりました」
と、玄茗と呼ばれた従者が、額の汗を拭きながら李徳裕を睨んだ。
「何を言っている。儂が店の中にいたのはほんの四半刻だぞ」
「若君、ご自身の目で陽の高さをお確かめ下さい」
それ以上の言葉を並べることなく、玄茗は目を伏せた。手をかざして空を見上げた李徳裕が、納得のできない面持ちで玄茗に目を戻した。
「儂は…………今まで物の怪に惑わされていたようだ…………」
「若君がいかがお過ごしであったかは知りませぬが、市中に出た折は、この玄茗の目の届く場所にいて下さい」
と、叱る目を李徳裕に当てた。
「玄茗の言わんとすることは分かっておる。今後は気を付けよう」
李徳裕は店があったと思われる辺りに、恐る恐る目を当てて見る。視線の先には荷車が止められ、立ち動く人足の影になって、記憶の中の店は見えなかった。李徳裕には、なぜか無駄なことに思えたが、数歩戻って泳ぐような目で探したが、狭い間口に青龍刀の下がる店はない。
「やはり店はないか…………」
不安を裏付け、半ば予想していた結末だった。
「何かお探しでしょうか」
「いや、何でもない、玄茗、儂は百年いや、千年生きても食べきれぬ羊を持っているらしい。西域伝来の香料で味付けされた旨い羊肉料理を食べに行こう」
李徳裕は気持ちを切り替え、平静を装って歩き出した。
「陽も傾き腹も減った。何か美味い物を食して屋敷へ戻ることにしよう」
「私も若君を探し歩いて、疲れてしまいました」
西市の本通りを逸れた二人は、食欲をそそる油や肉が香ばしく焼け、煙の洩れる狭い小路へ入って行った。