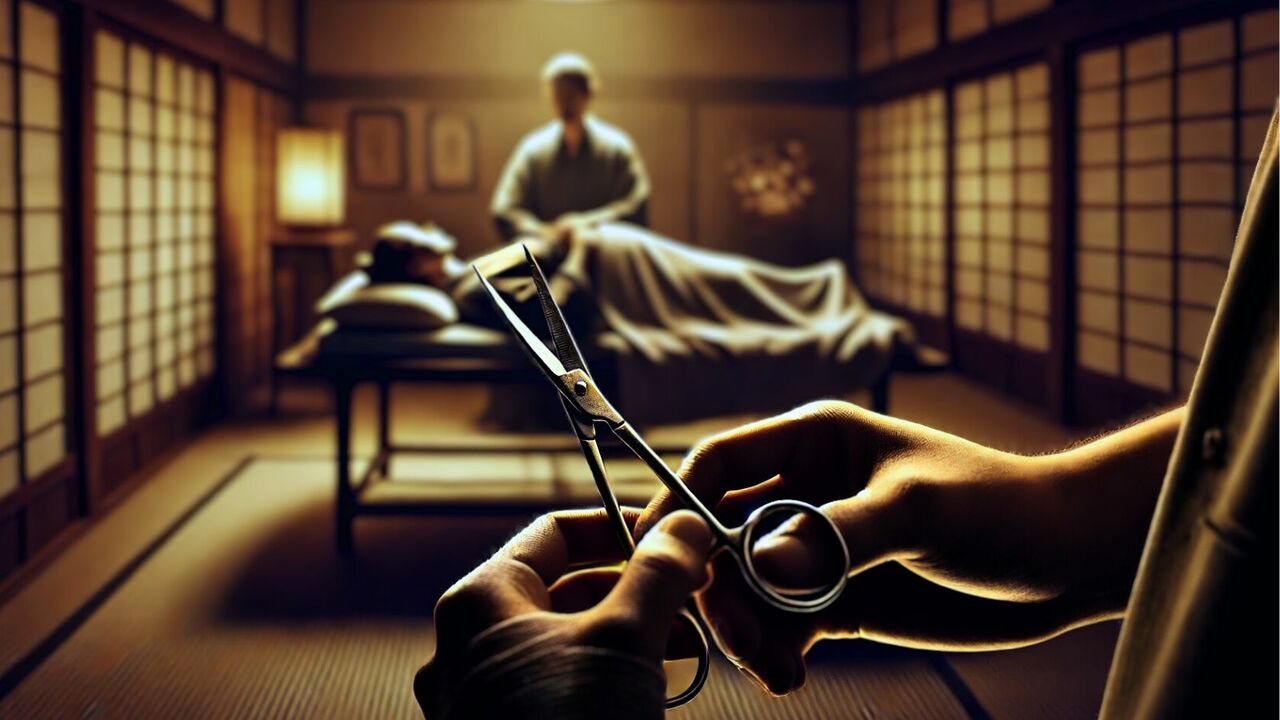「年が明けて、二月二十七日のことでした。今度はそのショイベ先生の家へ、僕とベルツ先生だけでなく、萩原先生も晩餐会に招待されたんです。そのとき僕は、萩原先生とショイベ先生が旧知の仲だったと、初めて知りました。もちろんそこでも、日本の思い出話に花が咲きました。ショイベ先生も、最初に日本の地を踏んだときのことを、懐かしそうに語られました。
明治十年十一月に横浜に到着すると、ベルツ先生に迎えに来てもらったそうです。その後もお二人は、互いに東京と京都の自宅を行き来していたとのことで、本当に仲が良さそうでした──」
万条も、そのことはかろうじて知っていた。
明治十二年の秋、ベルツが京都に来たときに見かけたことがあったからだ。ショイベの方も、明治十二年と十三年の春に東京へ旅行したさい、ベルツ宅に泊まったと聞いていた。万条は懐かしい気持ちでいっぱいになった。今日初めて出会った森から、恩師の名前を二人も耳にするとは思ってもみなかったからだ。
しかしそのあと、万条は複雑な表情で呟いた。
「でもうちでは、外国人の医学教師は、いつも一人だけだったな……」
「え、そうなのか?」
大御門がきょとんとした顔で訊き返した。
「ああ。他には、ドイツ語と基礎科学を教えてくれたレーマン先生がいただけだった。本来なら、京都の方がそうなるはずだったが……」
「都が京都から、東京に移ったせいか?」
「その通りだ。維新のあと、東京ばかりにカネと人材が集中するようになって、京都はすっかり寂れてしまったからな。文化の中心からも脱落して、おまけに税収も少なかったから、うちではそれが限界だった」
「こっちは、最低でも三人だったな。多いときには五人のドイツ人教師がいて、それぞれが自分の専門科目を教えていたけど──」
大御門が遠慮がちに言うと、万条は顔をしかめた。今頃になって、古傷が疼くように感じたからだが、そのあと万条は、二人にぽつりぽつりと当時の思い出を語ってやった。
ショイベが着任して間もなく、万条は京都療病院の医学校を卒業した。しばらく療病院で働いたのち、日本全国の医学校を転々としてきた。ショイベは結局、京都に四年いた。彼は確かに優秀で、しかも一生懸命だった。
とはいえ年齢がまだ若すぎた。また京都府は、高給取りだった彼を、やがて邪魔者扱いするようになって行った。ついには、使い捨てるかの如く解雇してしまった。ショイベの前任者は、マンスフェルトというオランダ人医師だった。長崎でポンペとボードウィンのあとを継ぎ、精得館の三代目教諭になった人物だ。
マンスフェルトは精得館を辞した後、熊本の医学校へ移った。任期切れでいったん帰国し、再来日のさいに京都へやってきたが、たった一年で療病院を去ってしまった。