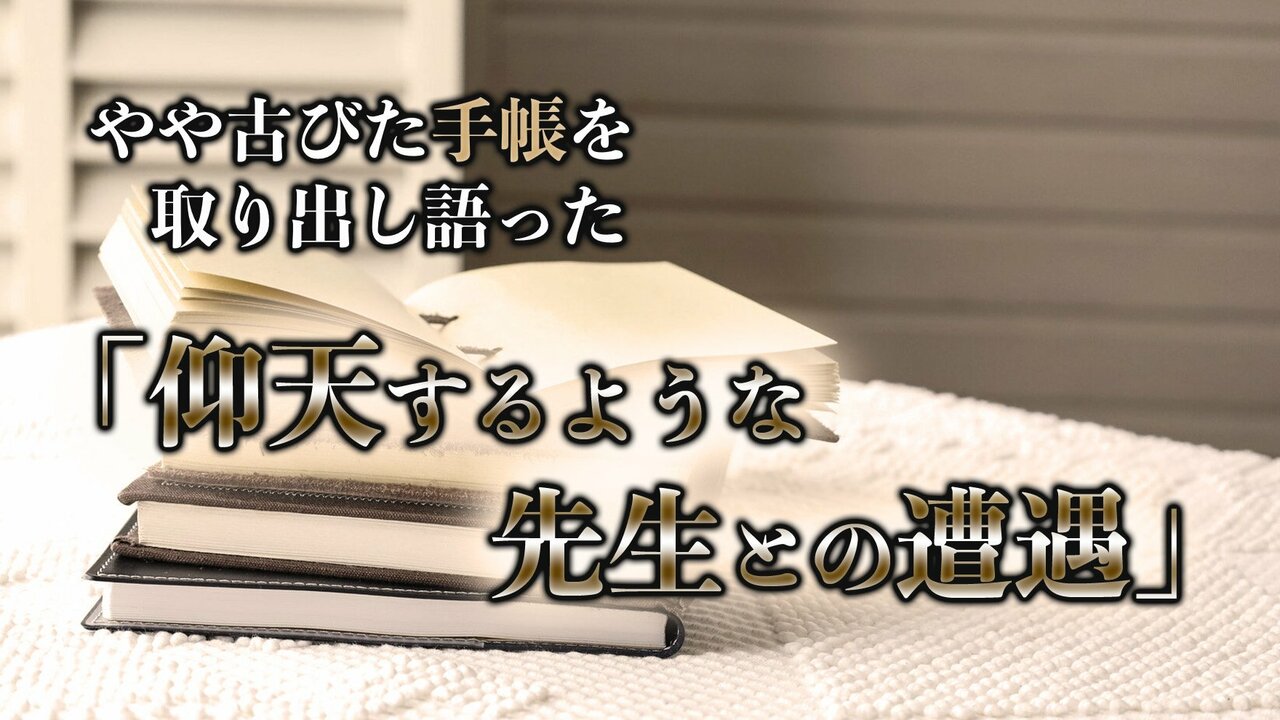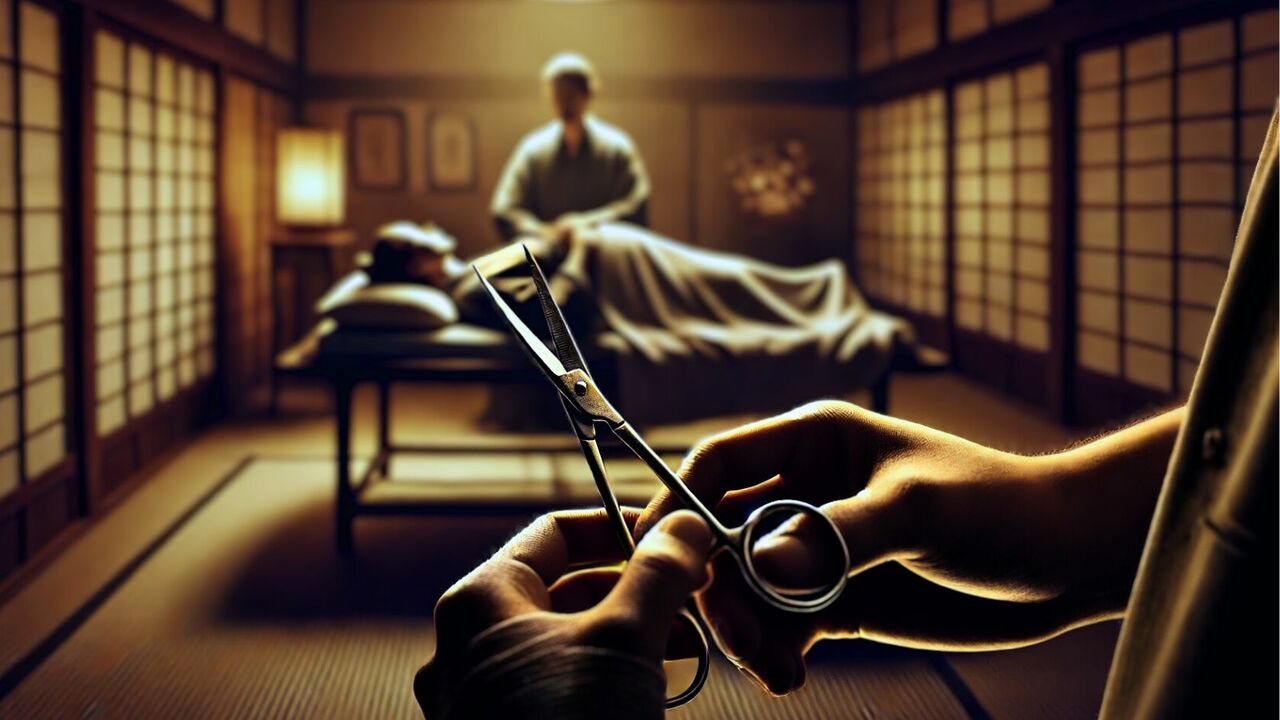序章
明治二十一年(西暦一八八八年)十月
「それから、デーニッツ先生からは、解剖学を教えてもらっていた。そう、萩原三圭先生が、ドイツから連れてきたドイツ人教師のことだ。本科生時代には、外国人教師は三人で、最後に内科のベルツ先生がやってきた。卒業後には、外科のスクリバ先生が着任した。お二人は、今も帝国大学で、元気に教鞭を執っておられる……」
大御門が立て板に水のように喋り、そのあともさらに続けようとしたときだった。
「ちょ、ちょっと待て……」
万条がうんざりしながら遮った。
「もうわかった。おまえが習った外国人教師は、みんな聞いたことがある。内科と外科の担当は常に別々で、しかも基礎医学だけでなく、予科にも専任がいたんだろ?」
「その通りだが──」
大御門がさらりと答えると、そのときまた、森が話に割り込んできた。
「ベルツ先生がご健在なのは、嬉しい限りですね。でも僕は、一度ドイツでベルツ先生とお会いしたことがあるんですよ」
「え、そうだったのか」
意外そうに、大御門が森の方を振り向いた。
森は洋服のポケットを探り、やや古びた手帳を取り出した。表紙には『独逸日記』と書かれており、森はそれをめくりながら語り始めた。
「僕がドイツに着いて二カ月後の、明治十七年十二月十五日のことでした。ライプチヒ大学のホフマン教授のお宅に、キリストの聖誕祭の前祝いで招かれたのですが、その晩餐会にベルツ先生がひょっこり現れたんです。僕は仰天しました。日本にいるはずなのに、地球の反対側でベルツ先生と、いきなり遭遇したのですからね。
それで僕は、慌てて訊きました。東京大学を、お辞めになったのですか、と──。するとベルツ先生は、笑いながら、『長期休暇を取って、一時帰国しただけだよ』と答えられました。
僕は安心しました。よく考えれば、ライプチヒ大学はベルツ先生の母校だったので、何の不思議もありませんでした。それからは、日本の話題で大いに盛り上がりました。でもその晩餐会では、日本で教えていたというドクトルが、もう一人おられたんです。名前は確か、ショイベというかたでした──」
その瞬間、万条は弾かれたように訊き返した。
「ショイベ先生?」
「ええ、そうです。ライプチヒ大学で、ベルツ先生の四年後輩ということでした。しかも、京都にいたとお聞きしましたが、ひょっとしてお知り合いですか?」
逆に、森に尋ねられ、万条は目を丸くしながら答えた。
「ああ、ショイベ先生は、俺が医学校を卒業する直前、京都に着任してきた」
「やっぱり……」
森は満足げに頷いた。そしてまた手帳をめくると、さらに話を続けた。