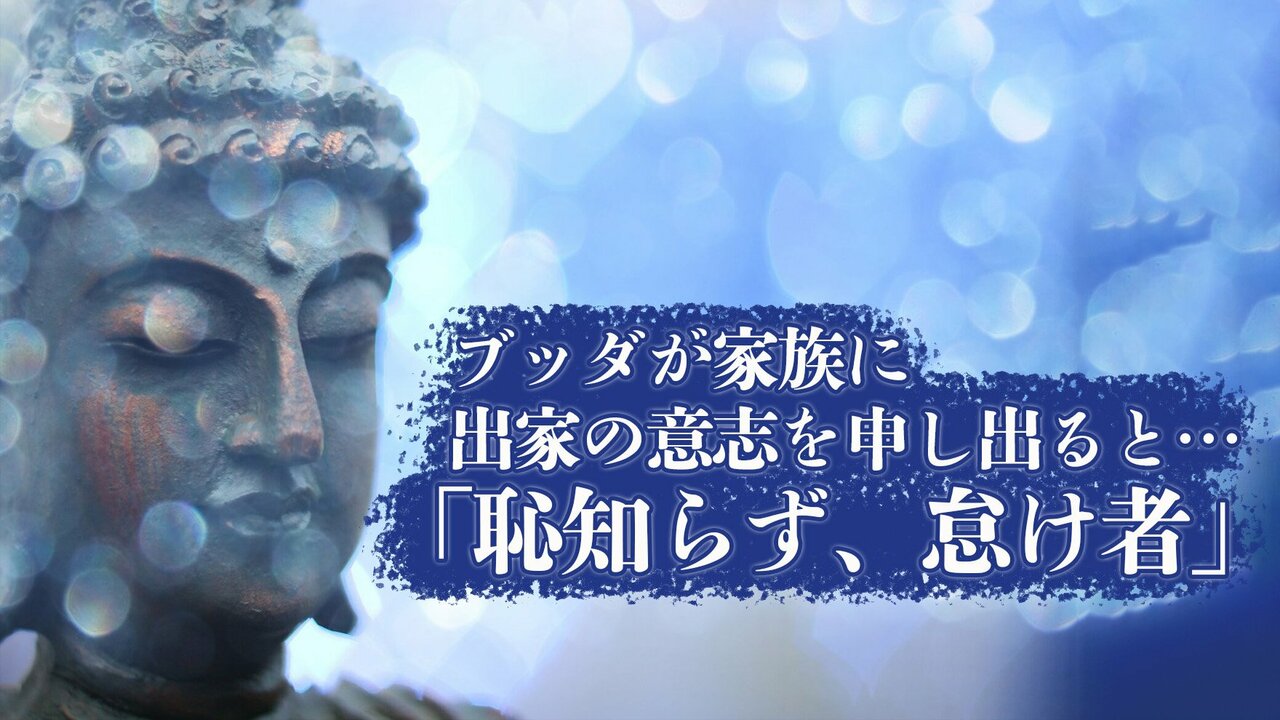第二章
二
中田は不意に、自分の意識がどこか一点に吸い込まれていくような静寂に包まれた。中田は自分に働きかけてくるものを感じた。それが何であるか、どこから来るものか、中田には分からなかったが、来るに任せた。止められるものではないということを中田は知っていた。
以下は中田の幻影に現われたゴータマの言葉である。
「わたくしの出家の決意が固いと知った妻のヤショーダラーは、わたくしを罵倒した。養母のマハープラジャーパティーは、呼吸を止めたかのように、わたくしを見詰めるばかりであった。父のスッドーダナの目は静かだった。
『そうか……やはり……出家に活路を見出すか……』
父はわたくしが父の役に立たないことは知っていた。父は語りだした。
『お前はよく喋る活潑な子だったが血を見ることが嫌いだった。武器をとって戦うことには向かない。
お前が8歳の時だった。ある朝、高い熱を出して意識を失った。毒を盛られたような、突然の病であった。熱は三日三晩続いた。お前の母のマハープラジャーパティーは食を断って、お前の足の裏を揉み続け、お前の意識が戻るよう祈り続けた。お前を診た医師は覚悟を決めるようわしに告げた。生みの母でも自分の命と引き替えに我が子を守るとは限らぬ。マハープラジャーパティーがいなかったら今のお前はここにいないかもしれぬ。
お前には、お前の生みの母の妹だが、マハープラジャーパティーという立派な母がいるのだ。お前は思っているかもしれぬ。〈子供は母に甘えて育っていく。自分は生みの母を知らない。母の胸に抱かれて満たされるということがなかった。〉と。
また、〈自分が生まれなければ、母のマーヤーは若い盛りに死ぬこともなかったのではないか。〉と。マーヤーは旅の途中での難産がこたえたらしい。生まれた者が死んでゆくのは、早い遅いはあっても、世の習いだ。』」