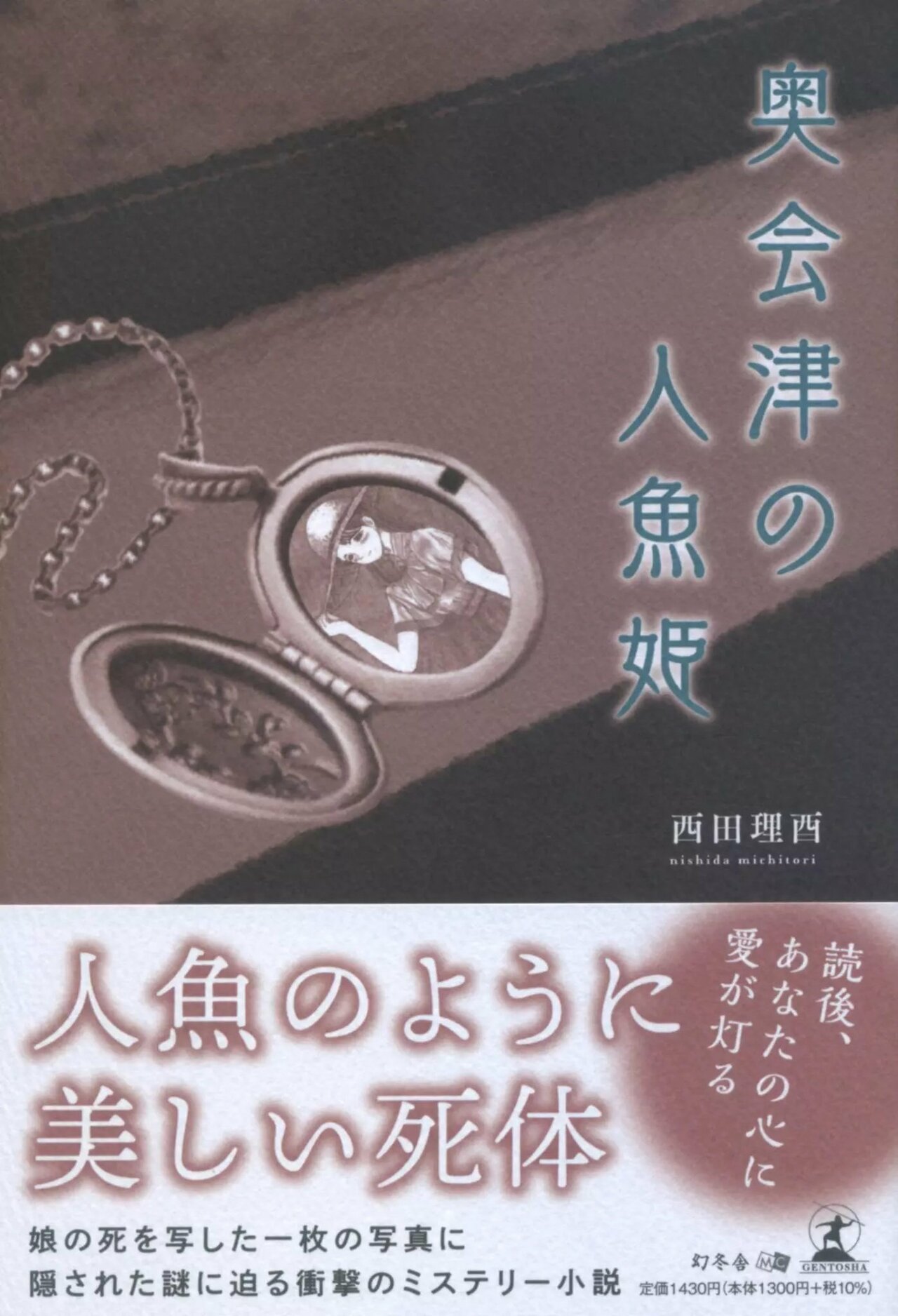「その時乙音は、麦わら帽子をかぶっていた。晩秋だったが、まだ日中の日差しは強く、肌の白い乙音にはとても必要なものだった。そして……」
と言うと、なぜか千景はそこで口ごもった。また咳が出かかっているせいかと、鍛冶内が心配して覗き込んだが、そうではない。千景は何かを恐る恐る取り出すかのような口調で話を続けた。
「湖の水際に乙音は立っていた。少し風が吹いてきたから、俺は冗談めかして言った。『ほら、気を付けないと大変なことになるよ』と。すると乙音は真顔でこう言った。『大変なことって何? ちぃちゃん』と。俺はその反応に違和感を感じながらも、笑いながら次の言葉を口にした。『風が吹いて帽子が飛ばされるってことに決まってるだろ』と。すると乙音はいたって普通の様子で、『そんなこと万に一つもありえないわ。だって私、麦わら帽子かぶる時には必ず紐で縛ってるから』と言った。
『え、紐で縛ってたことなんてこれまでにあったか?』。俺は動揺を隠し切れずに恐る恐るそう尋ねた。すると乙音は得意げにこう答えた。『ええ、お母さんの教えよ。私その言い付けを小さい頃からずっと守って、紐は必ず縛るようにしてるの。偉いでしょ?』と。『必ずかい?』。しつこいくらいになおも俺が尋ねると『縛らなかったことは一度もないわ』と乙音は答えた。
そしてそれを聞いた瞬間、俺の全身に電流が走った。それはこの一連のやりとりで徐々に膨らんでいった俺の疑念が、確信に変わった瞬間だった。なぜなら乙音が言ったその言葉は、俺が知ってる乙音が絶対に口にするはずのないものだったからだ。俺にとってそれは、天地がひっくり返るくらいの衝撃だった。
…………この子は乙音じゃない。いや、乙音のはずがない。絶対に違う…………。
俺は今目の前にいる娘の顔を、必死の形相で穴があくほど見つめた。だがその唇下には確かにほくろがあった。でも乙音のはずがない。この子は一体誰だ……。乙音じゃないとすると、ひょっとしてこの子は汐里なのか……?」
そこまで言うと、千景は両手で顔を覆った。そしてそのまま動かなくなってしまった。