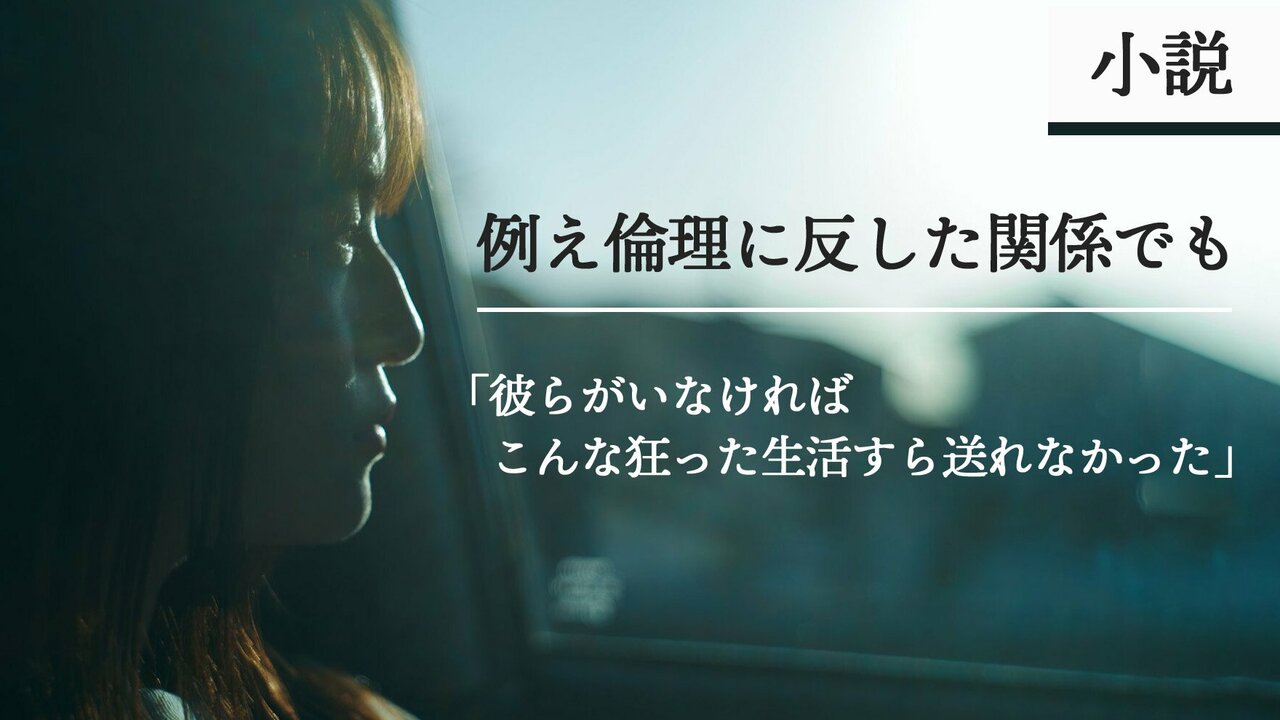飛燕日記
翌日の仕事終わりに、ショッピングセンターの駐車場で再びマキさんと待ちあわせた。
「また会っちゃったね」
彼は、まずいなあ、はまっちゃうよ、と繰り返しながら車を走らせ、ゲートをくぐった。
ホテルの部屋には窓がなかった。巨大なベッドが狭い空間を圧迫し、テレビは壁にかけられている。生活スペースとしてはアンバランスだったが、ほとんどをベッドですごすなら最適な配置だろう。角にはスロットマシーンが置かれていた。
シーツの冷たさが心地いいのは、重ねた体が熱いせいだろう。天井の鏡はベッドを映してもまだ余り、そこにさらされた二人は知らない人間のようだった。
焦点を定めずに傍観していると、自分が景色の一部になっていく。まぶたを下ろすと、呼吸するように漏れる声に色彩が浮かびはじめる。ゆっくりと目を開けると、鏡の中の少女と目があった。
一重の目は、胡乱なターコイズブルーをしていた。笑うでも泣くでもなく、曖昧に開かれた口から白い歯が覗いている。ストレートパーマがとれかけた黒髪がベッドに広がった。
指で濡れた場所をほぐされて、舌の根が甘くなっていく。熱の塊が入りこんでくる異物感はなんとかやりすごしたが、内側をかき回される感覚に我慢できず、声を上げた。
少しずつ、ほろほろと、今まで築いてきたものが崩壊していくのは、惜しくもあり、快かった。マキさんは、こちらの姿も目に入らないように一心不乱だ。呼吸が乱れ、限界が近いことを知る。あと少しで戻れなくなる。そう思うとぞくぞくした。そして、その瞬間がきた。
彼が腰を強く打ちつけて果てると同時に、私も達した。まぶたの裏に水色の光が砕け、なにも見えなくなり、聞こえなくなる。
甲高い耳鳴りは、しばらくすると収まっていった。枕元の薄明るいランプを見て、ここが自分の部屋ではないことを知る。一時間半が経っていた。シーツも、投げ出した手足も、なにもかもが濡れて重い。
汗に濡れたマキさんが、頬をシーツにつけて眠っていた。