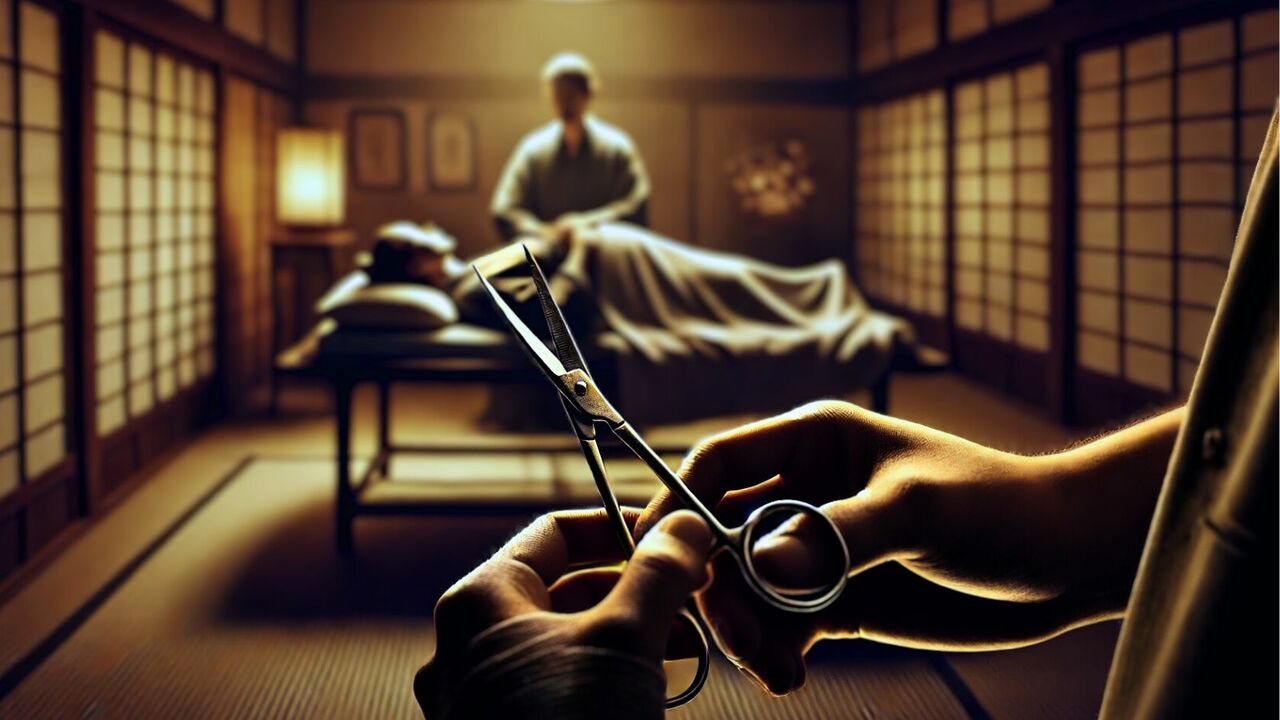林研海は幕府御典医林 洞海の息子で、文久二年(一八六二年)に榎本武揚らとともに、幕府からオランダに派遣された留学生の一人だった。帰国していたポンペのもとで、最新の西洋医学を学ぶのが目的だったが、明治元年(一八六八年)十二月のことだった。研海が日本に戻ったとき、幕府はすでに跡形も無く消えていたのだ。結局、研海は明治政府に出仕することした。そして後には、軍医本部長なども歴任するなど、重責を担うようになった。
「ですが、明治十五年のことでした……」
そこまで話したとき、森は顔を曇らせた。そして沈んだ声で続けた。
「林 研海先生はロシアへ向けて出立したさい、途中のフランスで急病死されました。それを伝えると、ポンペ先生は絶句されました。無念の表情を浮かべられたまま、会話が途切れてしまったので、先生が少し気を取り直したところで、僕の方から尋ねました。日本にいたときのことを、何かお話ししていただけませんか、と。
するとポンペ先生は、寂しげにこう答えられました。『もう、あまり覚えていない。日本で過ごした五年間は、夢のようだった……』そのあと、遥か遠くを見るような目となりました──」
森が語り終えると、万条はしんみりと呟いた。
「ほう……。あの、ポンペ先生と、そんなやりとりがあったのか」
ポンペは日本じゅうの医者にとって、伝説と呼べるほどの人物だった。いわば日本の医学の父とも呼べる人物で、万条も興味が尽きなかった。
「当時の日本人医師たちは、みな御雇い西洋人教師に、本当に世話になったからな」
大御門が納得したように言った。
「そうだな……」
ゆっくりと万条も頷くと、大御門は思い出に浸るように語り始めた。
「俺の場合、予科ではシモンズ先生から、ラテン語とドイツ語を習った。ワグナー先生からは、物理、化学、数学を教わった。本科では、まずミュルレル先生とホフマン先生に、それぞれ外科と内科を学んだ。彼らが契約満了で帰ると、シュルツ先生、ウェルニッヒ先生が、入れ替わりやってきた……」
大御門は次々と、外国人教師の名前を挙げていった。彼が東京に移り住んだのは、明治維新の直後からだった。天皇が京都を去り、東京を新しい首都に定めると、公家はそれに付き従うほかなかった。大御門も、一家で東京に移住することになった。
そして初めての土地に、右も左もわからなかったという。そんな中、大御門は一人で生きて行く手段を見つける必要があった。公家の三男坊として生まれ、家を継ぐことはできなかったからだ。そのさい大御門は、医者になることを選んだ。帝国大学医学部の前身となる第一大学区医学校が、明治五年に開校することを知ったのだ。