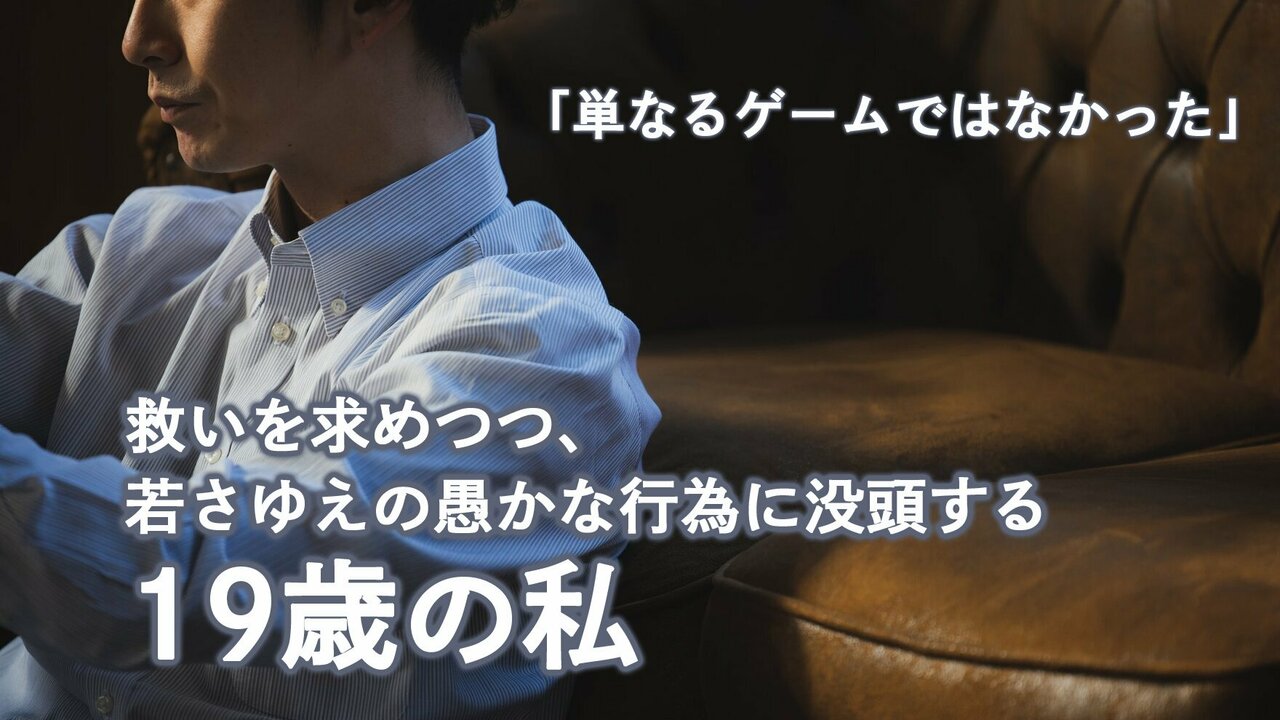第一章
2 七月三十一日挑戦開始
当時の私がたくさんではないにしろ新旧分かたず宗教の本を読んでいたのは、人生にも世の中にも幻滅し、救いを求めていたからに他ならない。救いを求めつつ、若さゆえの愚かな行為にも没頭していた。それを証明するように、日記の続きはこうなっている。
『……ぼくは今日借りていく本を決めたにも関わらず、その後しばらく図書館にいた。ある少女との出会いが、ぼくを足止めしてしまったのだ。
最初、美術のコーナーにいたぼくと、なにかの本を探していたのか、ただぶらついていたのか不明だが、その少女と目が合った。歳は小学生の高学年くらいだろうか。その割には少し大人っぽいフンイキも持っていた。次にぼくが文学のコーナーにいたところ、またその少女がやってきて、ぼくと目が合った。彼女はニコリとした。
更にぼくが借りる本を抱えて、本棚の間を受付に向かっていたら、偶然正面でばったり出くわした。身長はぼくの肩までしかない。少女はまたおかしそうにニコリと笑った。迷路のような図書館の中で、そうやって鉢合わせすることが、ゲームみたいで面白かったのかもしれない。
するとぼくもそのゲームに面白さを見出してしまった。用もないのに本を探すふりで、棚の間を歩き回り、少女に出くわすと、意味もなく親指をつき立て、あいさつする。少女もまた、親指をつき立て、ぼくのまねをするようになる。そんなゲームを繰り返していた。
しかしそれは、ぼくにとって単なるゲームではなかった。ぼくは少女にうまく笑いかけることができない。ぼくは明らかに、性的な興奮を覚えて少女を追い回していたのだ。
ぼくは女の人が苦手である。大学のアホな女連中も、ヤマンバギャルや援交のコギャルどもも。古風な女らしさを捨て、金のために、自由な欲望のままに、自分に正直にとか、今を生きてるとかいうやつらを見ていると、死ねばいいと感じる。
それなのにぼくは欲望の塊でもある。ミニスカルーズソックスの女子高生を憎みながら、犯したくてたまらない。片手にナイフ、片手にチンポコを握りしめているのだ。だから図書館に来るのだって、実は出会いを求めているところもないわけじゃない。ぼくのようにうまく生きることができないさびしい女が、やはり出会いを求めて来ているのではないか、という予感がして。そういう女と知り合い、図書館の死角で犯すというモウソウは、ぼくのお気に入りである。
出会いを求めながら、それが全く実現しないぼくにとって、たとえ子供であっても、ぼくに興味を持ってくれる存在は貴重であり、妙な興奮を覚えてしまった。喉がカラカラになりながら少女を探してさまよい、今度出くわしたら声を掛けようと決意する。もし仲良くなったら、ぼくはどうするつもりなのだろう? 図書館の死角に連れていき、どうするつもりなのだろう……?