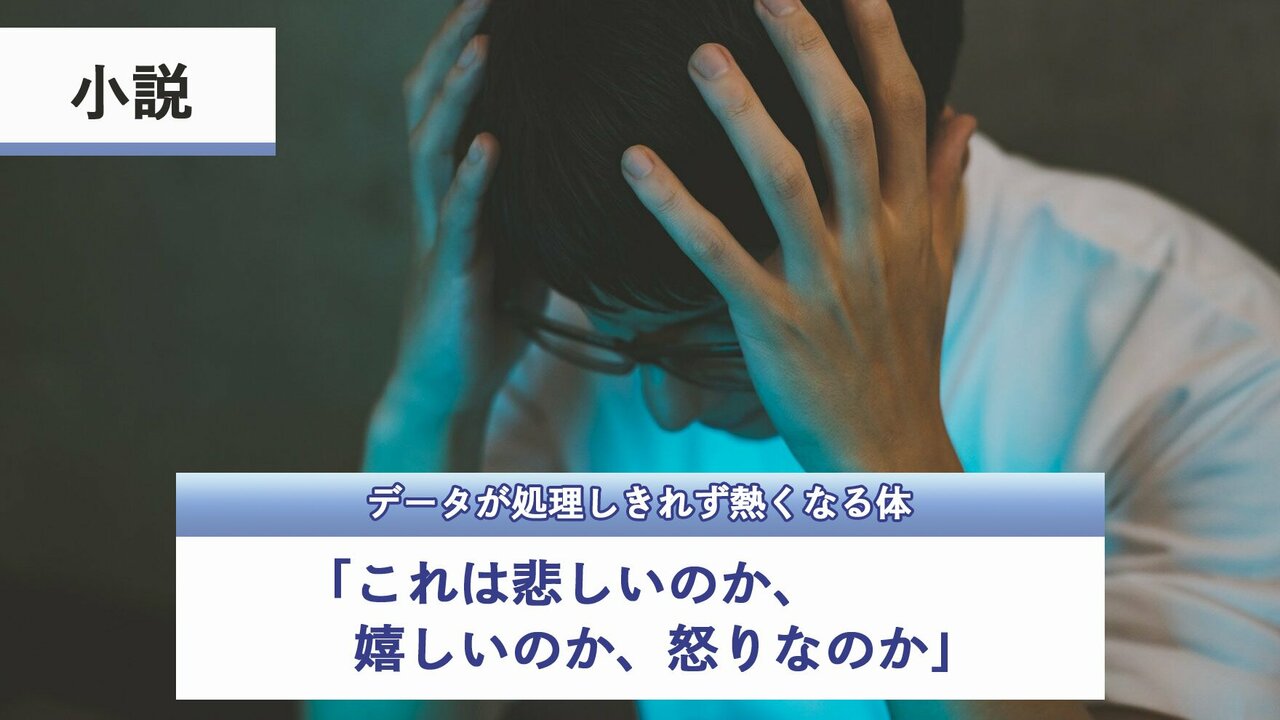『誤作動』
やはり雨が降ってきた。始めは小ぶりだったので、二人とも油断していた。
「傘持ってない」僕が言うと
「大丈夫だよ」彼女は楽しそうに言う。
しかし雨は本降りになった。
「大丈夫じゃなかったね」
「うん、走ろう」
僕たちは手を繋ぎ、走った。歩いても走っても結果は同じだとしても走った。二人とも笑いながらずぶ濡れになりながら。
花は散り緑の葉が眩しいほどに生い茂る頃、僕は博士に呼ばれた。来も一緒だった。分厚く巨大な建物の中は暗くひんやりとしていた。
以前は感じることのなかった感覚。僕は自分の体についている手を見つめる。掌、手の甲、博士は低い声で何か言っている。硬いソファーに座り来が熱心に話を聞いていることだけは理解できた。僕はもう何もかもどうでもよかった。僕は初めから存在すらない。なんのためにここにいるのかさえ解らない。
しかし一つだけ気になることがあった。僕は最後にするべきことを考える。彼女を一人ぼっちにさせたくなかった。これは僕のエゴだろうか? 多分そうなのだろう。
僕は明日になったらこの壊れそうで小さな住居から出なければいけない。もう、ソファーに座って外の景色を眺めることもない。
真っ暗な部屋の中、余計なデータが処理しきれず体が熱くなった。
夜明けも近づく頃、家の中に誰かが入ってくる音を感じる。彼女だった。僕が呼んだのだ。僕は彼女に気づかれないように、自分自身を起動させる。
「何かあったの?」
彼女の顔はひどく歪んでいた。
「会いたくなって」
「……」
「最近、佐々おかしいよ」
「僕は変わらないよ」
彼女の目から液体が流れる。これは悲しいのか? 嬉しいのか? 怒りなのか? 追いつかない。
僕は彼女を抱き寄せる。
「体、熱い」
彼女が言う。
僕は無数の生命を彼女の中に残し、そのもとを去った。僕は彼女のことを忘れる。でも生命は彼女のことをいつまでも覚えているだろう。
作業用に作られた最も人間に近いとされるアンドロイドSASA9R。人間に不必要に近づかないようプログラミングされていたのに僕は進化しすぎてしまったらしい。進化は危険とみなされるこの世界に、僕はもう存在できないのだ。
僕に興味を持たせた彼女を恨むとともに抱きしめていたいと思う記憶を最後に、僕は終わった。