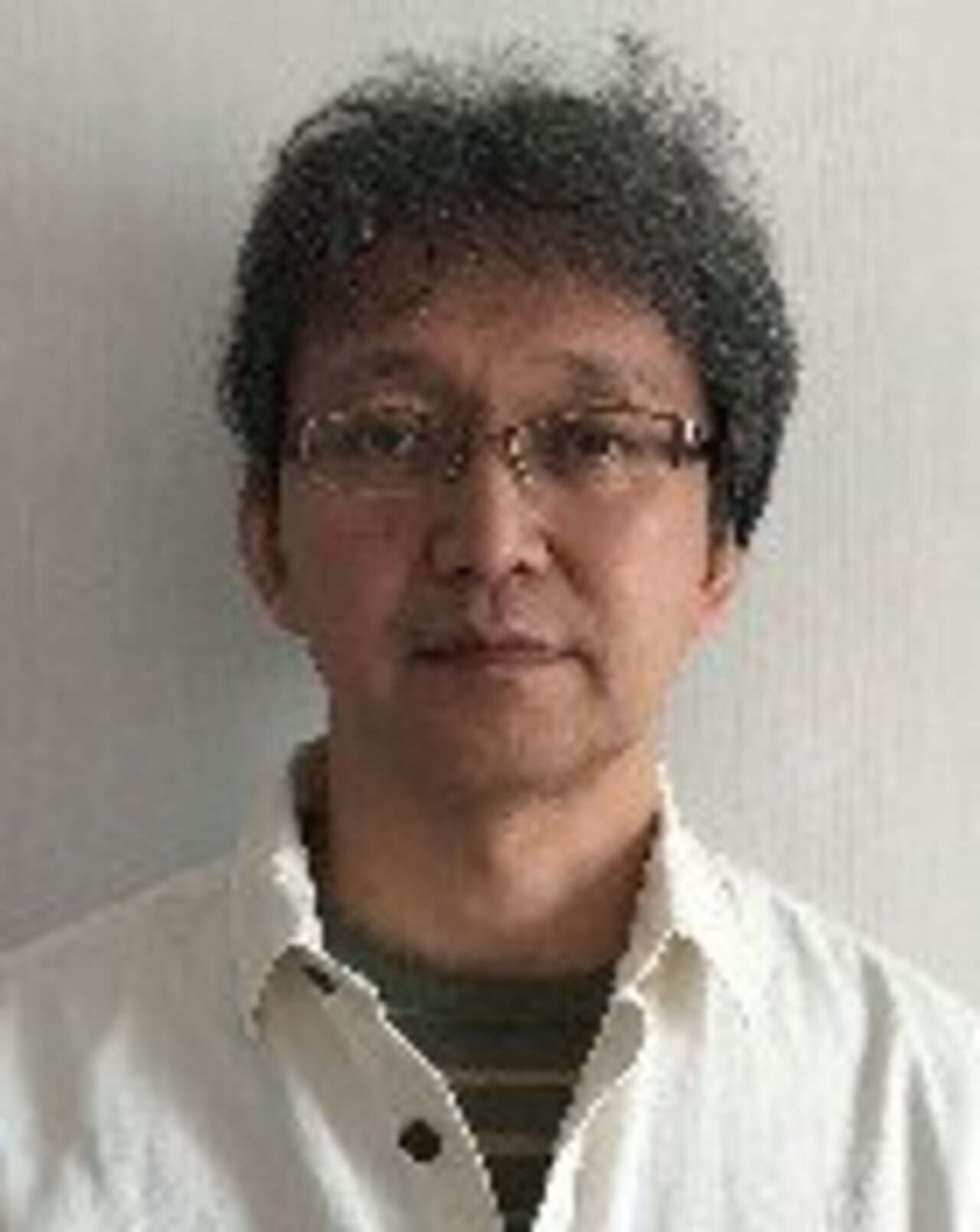和枝がO型から試弾を始める。ショパンのバラード4番。静まりかえった蒼い水面を漕ぎ出すように音の波紋が広がっていった。どうやら「単なるお試し」のつもりではないらしい。のっけから気合を入れ、コンサート張りに弾いた。その感触が消えないうちに今度はB型も試弾、同じくバラード4番を。
このB型の譜面台には「1960年代製700万円」と印刷された名刺大の値札が置かれていた。廉にとってはこんなに間近でスタインウェイを見たり、音を聴いたりするのは初めてだった。彼は三十歳の時に都心の新聞社に転職し、以来、編集記者一筋でやってきた。彼にとっては「人生に不可欠なのは音楽」だった。ピアノの経験こそなかったが、中学・高校と吹奏楽部、大学ではオーケストラに入りクラリネットを吹いてきて、音にはしっかりした思い入れがあった。
さっき試弾が始まった瞬間に「これは普段、家のレッスン室で和枝が弾くピアノとは全く別物」という感触は得ていた。こぼれ出した音の粒とその連なりの美しさに、少し大袈裟だが「イデア」という言葉さえ頭に浮かんだ。
濱中インポートは元々、管楽器専門の輸入業者として知られているが、ピアノにも力を入れ始め、ちょうどこの頃スタインウェイの正規特約店になっていた。応対してくれたのは社長の成田さんで、終始ゆったり構えていて、ありがたいことに、こちらから質問しない限りセールストークを差し挟むようなことはせず、和枝の試弾をじっと静かに見守ってくれていた。
ただ、音色への興味はあったとはいえ、廉にはスタインウェイを買おうなどという発想は端からなかった。音響効果を計算し尽くしたかなりの広さを持つ空間じゃないと、置くことさえ無理なのでは? 特に目の前のB型は全長二メートルを優に超す。
「とてもわが家の十二畳の防音室に収まる代物じゃない」と。
「でもどうなのだろう。この新しい音との出会いはあまりにも鮮烈過ぎやしないか」。
バラード4番を聴きながらの自問自答が始まった。
「まあ落ち着こう。買えるとか買えないとか、そんなことはひとまず脇に置いておいて、和枝が『これこそが探していた音』というピアノが見つかるまで自分はとことん付き合っていこう」
とだけ心に決めた。