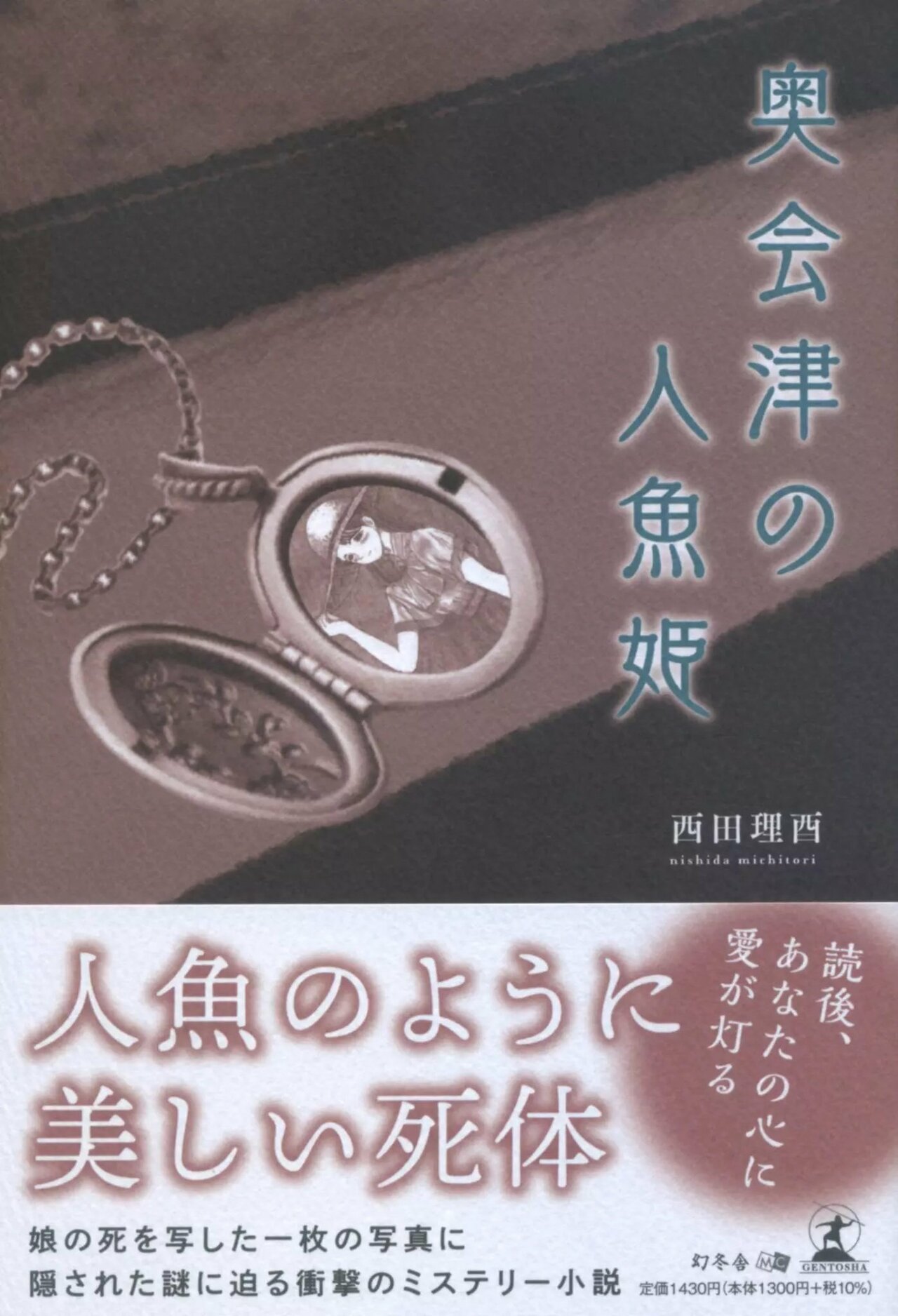「ちぃちゃん、ごめんね……。ごめんね……」
千景のもとに来た乙音が、何度も何度も謝りながら、宝物でも扱うように、千景の頭を自分の胸の中に抱えた。千景は自分に対する情けなさと、汐里への済まない気持ちとで、頬まで伝う涙を流しながら、乙音を強く抱き締めていた。あの夜が分水嶺だった。
霧ヶ峰の山頂の水が、わずか1mmの差で太平洋と日本海とに別れて注ぎ込むように、あの夜の出来事以降、乙音と汐里の運命は大きく変わってしまった。
「汐里は……?」
「ご飯は自分で食べるかいらないって」
あの日以来、汐里は千景と一緒の空間にいることを避けるようになった。
「気にしなくていいよ、ちぃちゃん。汐里は私と繋がっているから」
乙音はそう言ったが、汐里はだんだん、千景のみならず、乙音からも離れていくように思われてならなかった。あれほど積極的に手伝っていた、家事やめぶき屋での仕事にも一切関わらなくなり、たまに顔を合わせた千景には、とげとげしい言葉を口にすることもしばしばで、千景のことを「ちぃちゃん」ではなく、「あの人」と他人行儀に呼んで、目の敵にするようになった。
「俺にはいまだに信じられないんだ。あの優しく、思いやりのかたまりのようだった汐里が、さげすむような冷たい目で俺を見下し、『近くに寄るな』とか『いつか後悔させてやる』とか、ことあるごとに口にするようになったことが」
千景は遠い目をして、大きな息を一つ吐いた。
「あれが同じ人間だということが……」
自分の中にある迷宮に迷い込んで、出口に辿り着けずにいるような千景の様子に、場の空気を変えようと、鍛冶内は違う話題を振った。
「その頃、仕事はどうしていたんだ?」
これまで一方的に話していた千景は、鍛冶内に声を掛けられて、今まで厳しかった表情をほんの少しだけ緩めた。
「皮肉な話だが、汐里との一件があって、俺は頭をぶん殴られた思いだったよ。考えるまでもなく、汐里が言ったことはいちいちその通りだったからな。そしてそれからの俺は、自分で言うのもなんだが、生まれ変わったように一生懸命よく働いた。汐里はともあれ、乙音が献身的に手伝ってくれてたこともあり、めぶき屋はあの頃、結構繁盛していたよ。
俺は汐里に言われた、『みんな捨ててしまう』を打ち消すために、毎日が必死だった」