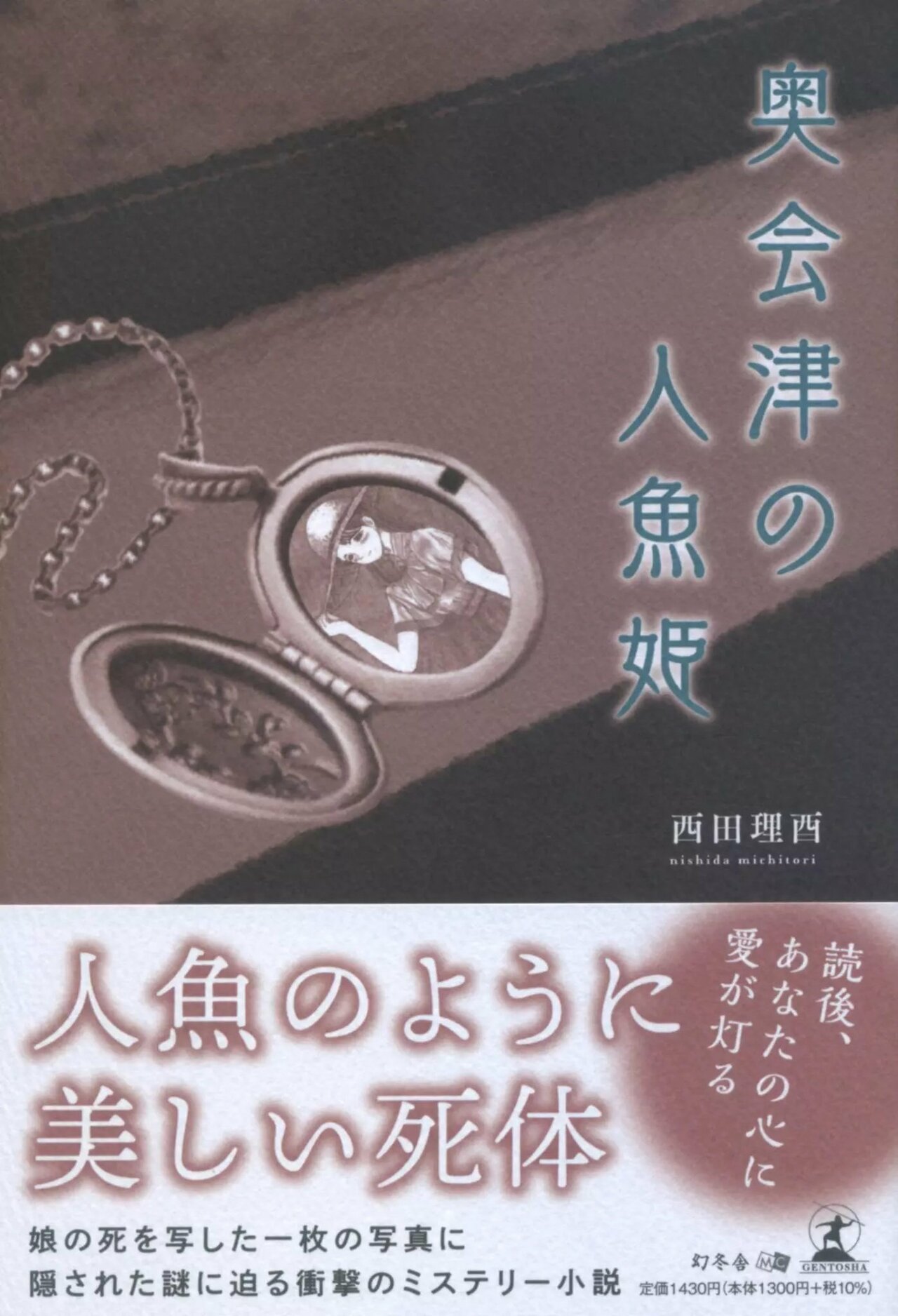(2)
その夜はもともと何かがおかしかった。酒を飲んでも自分を見失うことはないと、常日頃自信を持っていた千景だったが、その夜に限っては、少量の日本酒で既に自分を失ってしまっていることをぼんやりと感じていた。
ふと目をやると、囲炉裏ばたの自分の向かい側に乙音と汐里が並んで座っている。暗い顔をしてこちらを見つめているその両手は、二人とも強く握られていて、膝の上で固定されているかのようだった。
「ちぃちゃん……」
おずおずと乙音が口を開いた。そういえばここしばらくの間、乙音や汐里とはろくに会話も交わしていない。そんなことを思いながらも、咲也子のことで頭が一杯だった千景は、二人のほうを見ることもなく、酒の入った湯のみを口に運んだ。
「私たちのお願いを聞いてもらえる……?」
思い詰めたような口調で、乙音がさらに言葉を続けた。
「お母さんが亡くなって、ちぃちゃんが悲しいのは、私たちにもよくわかるわ。私たちにとってもお母さんは唯一の肉親だったから」
千景は変わらず無反応だった。
「でも私たち気付いたの。いつまで悲しんでても、何も良いことがないって」
「さぁこは……」
乙音が話しているのを気にすることもなく、ぼそりと千景が口を開いた。
「さぁこは、こうなることを知ってたんだろうか………」
すると今度は汐里が大きな声で言った。
「ちぃちゃん、こうなることってどういう意味?」
「こうなることとは、こうなることさ。さぁこが死んでしまうってことに決まってるだろう」
「ちぃちゃんは……」汐里が涙ぐみながら言った。
「お母さんがガンを患っているのを黙って、ちぃちゃんと結婚したと思ってるの?」
千景は何も答えなかった。
「ちぃちゃんはひどいわ。お母さんは絶対にそんな人じゃない」
「悪いが乙音………いや汐里か。どちらでもいいが、俺を一人にしておいてくれ」
だがこの日の汐里は、なおも千景に食い下がった。
「ねぇ、ちぃちゃん。私たち三人で頑張っていきましょう。私も乙音もまだ働ける年じゃないから、ちぃちゃんに負担かけるとは思うけど、二人ともめぶき屋の仕事を手伝うわ。もちろん家事も一生懸命やるから」
「悪いけど、今日は一人にしておいてほしいんだ」
そう言うと、千景は湯のみの酒をぐいっと飲み干した。しかし一升瓶からお代わりの酒を注ごうとした瞬間、手元がおかしくなって湯のみの酒を囲炉裏の灰の中にぶちまけてしまった。