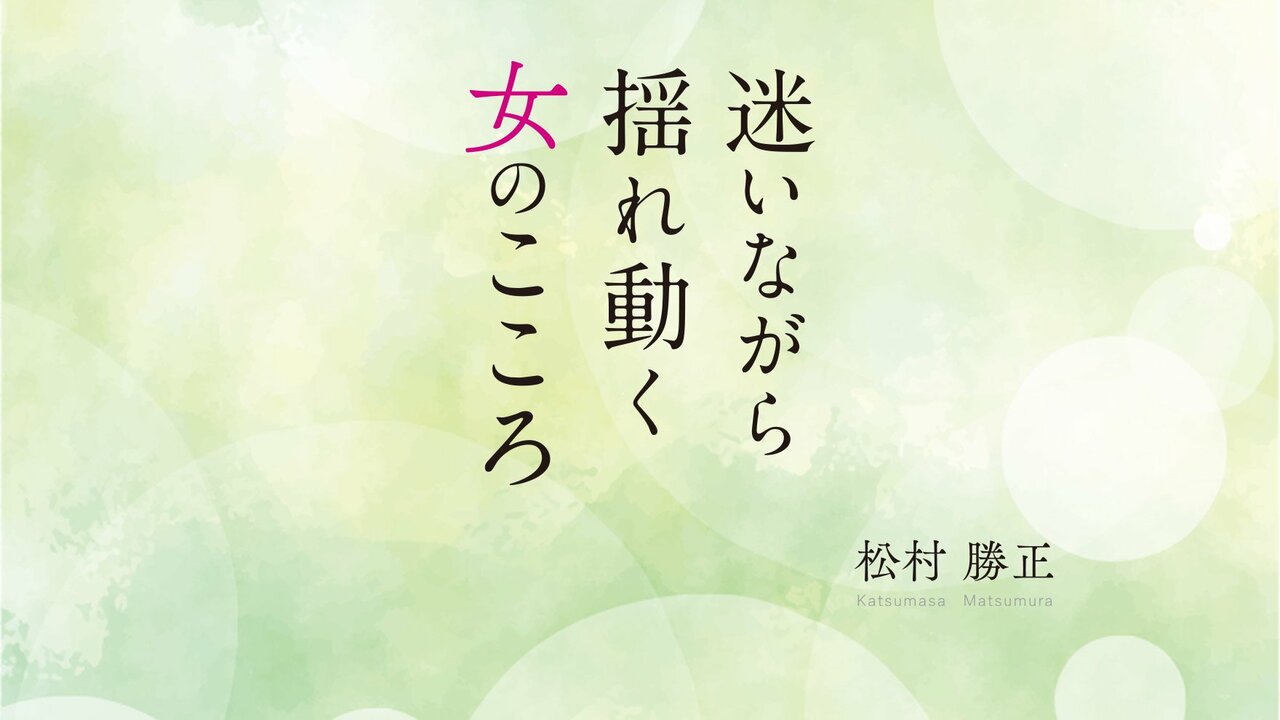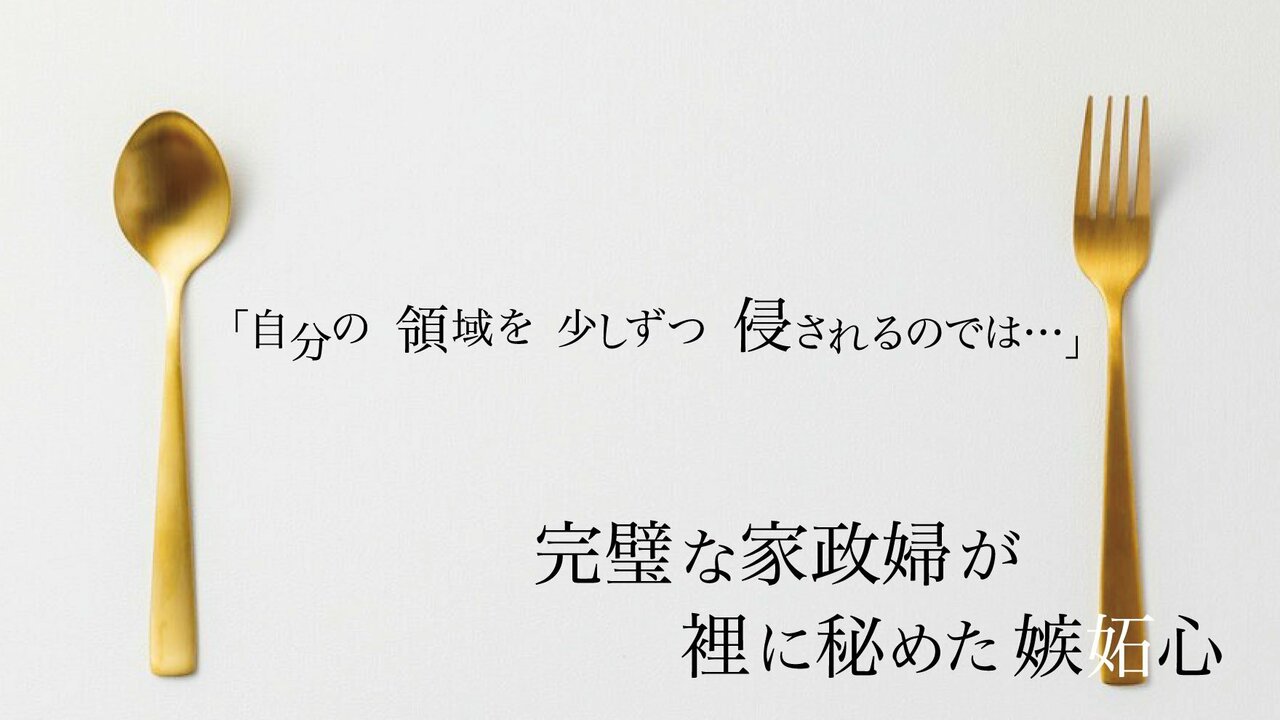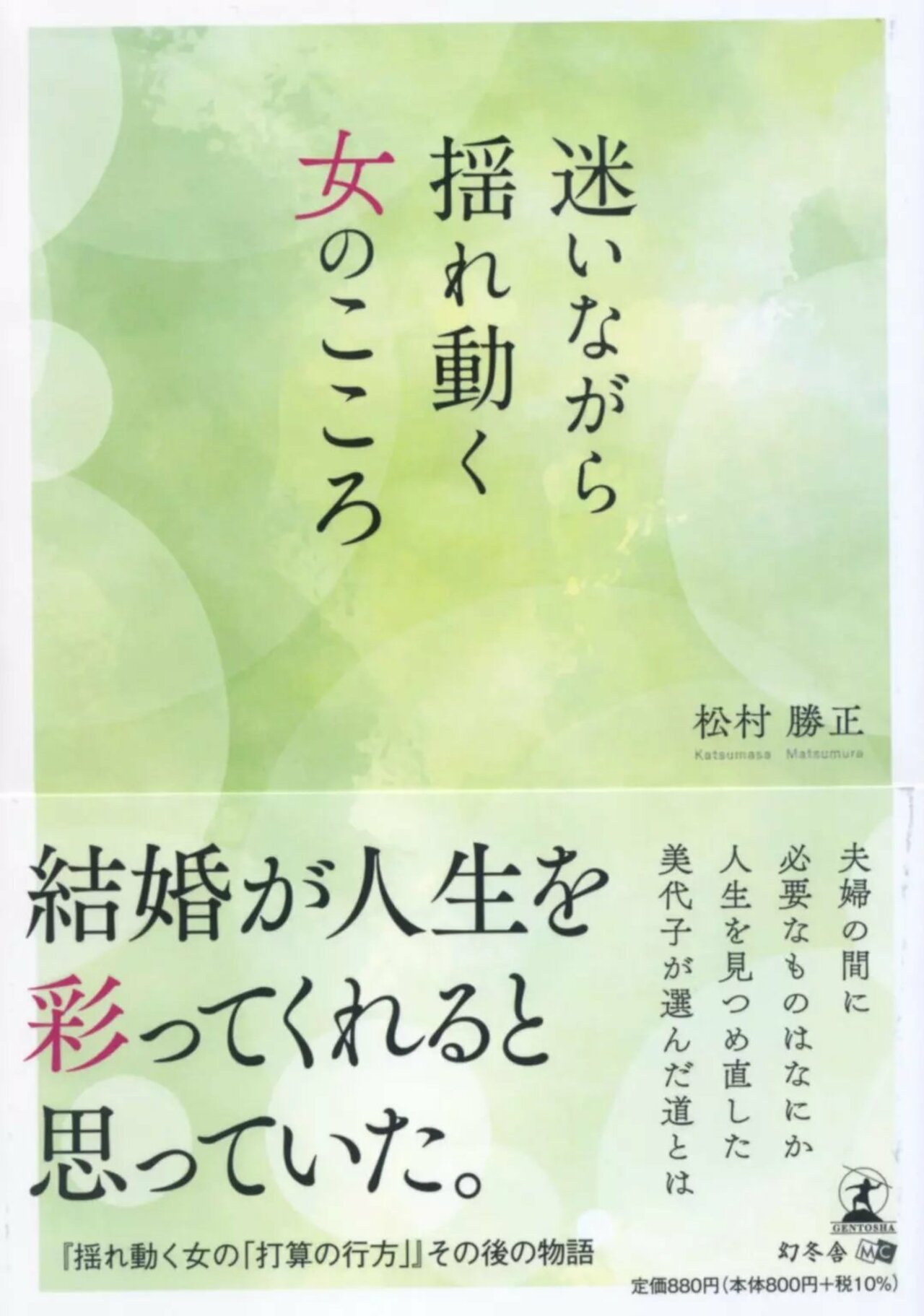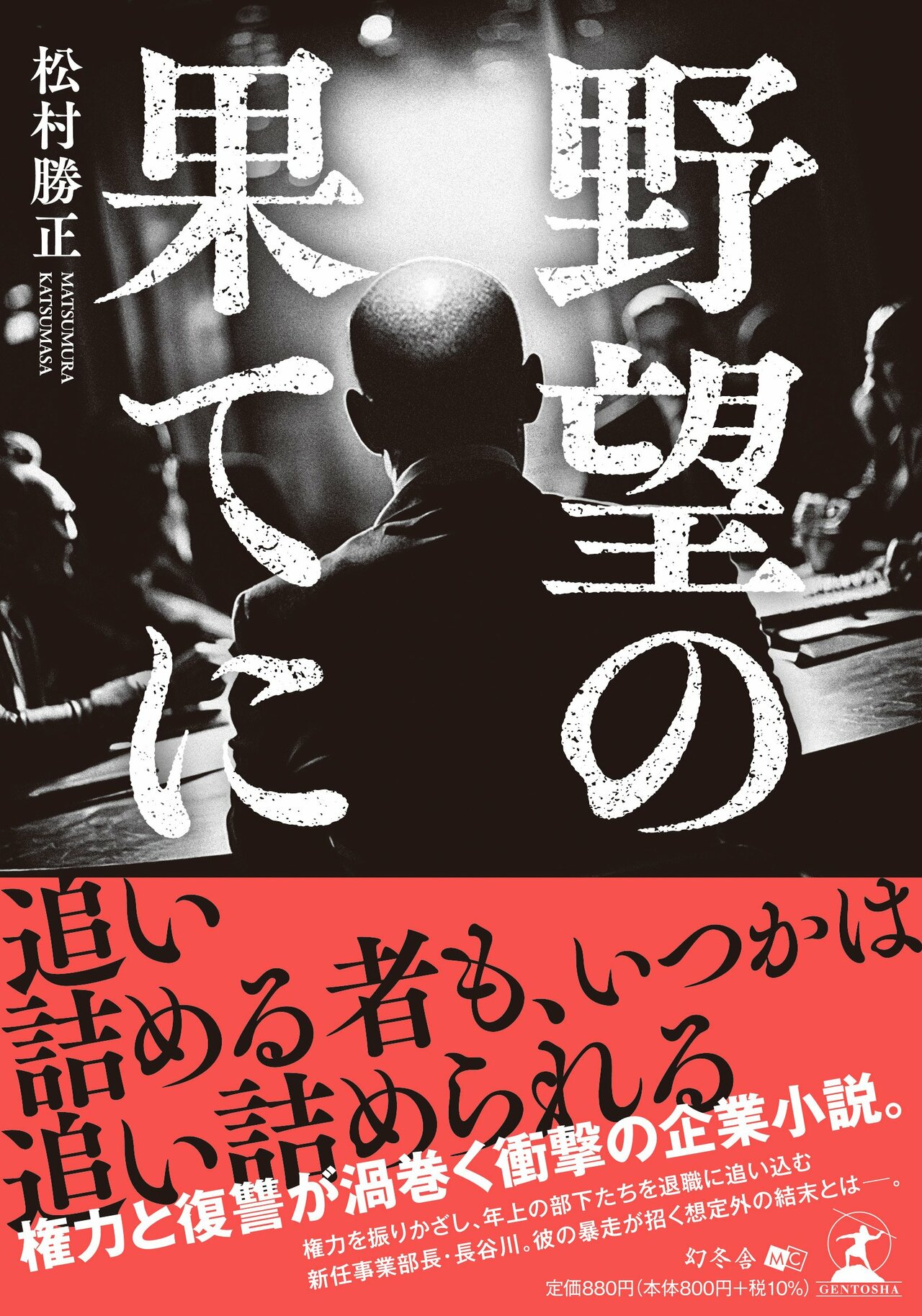迷いながら揺れ動く女のこころ
美月が悠真の車いすを押して食卓まで来た。
「私の事務所までいい香りがしていたよ。早く食べたいね」とテーブルの指定席に陣取った。
「匂いだけは本物に似ていること間違いなし」と美代子が匂いを強調した。まだ試食してないから味の方は、食べるまでの楽しみということか。悠真が最初に一口、「これは旨い、おこげも抜群の出来だよ」と言い、美代子と美月の二人を見た。
そしてさらに「これが、我が家での美代子の処女作か」と感心したように「大したもんだよ、これからも珍しい物を作ってくれよ。ほら、先日話していたブイヤベースなんかも美代子の舌が記憶している間に食べたいね」と美代子のやる気を引き出そうとしていた。
黙って聞いていた美月は、内心少し動揺し、目が泳いでいるようで「美代子さんの料理には見ていてセンスを感じますわ。私は田舎育ちだから昔ながらの和食しか作れません。母がいつも作っていたのは畑で採れた野菜が中心でした。私も美代子さんに教えてほしいわ」と悠真に同調する言葉を言った。
「今日のパエリアは食材が高級で、新鮮なのが決め手です。私はレシピに忠実にやっただけです」
美月がさらに持ち上げるように「美代子さんの味覚、舌と鼻が一流なのですよ。外資系企業に勤務されていた証ですよね」
美月は美代子さんに対する敵対心はないものの、どこかで自分の領域を少しずつ侵されるのではないかと、不安心理と妬みが交錯している自分と戦っていた。
山形家に家政婦としてお世話になって以来、専門職の家政婦として悠真さんに尽くし、山形家を陰ながら守ってきた。先日の風呂の介助といい、今日のように台所まで侵食され、悠真さんの胃袋まで干渉されることに、少なからず嫉妬心を覚えた。
悠真さんから美代子さんと結婚すると話を聞いた時、「嫁さんには趣味に生きてもらえばいいんで、風呂の介助や台所の一切は美月に任せる」と聞いていたから、悠真さんの身の回りの世話も弟のように接してきた。ラグビーで鍛えた胸厚の体も多少昔より肉が落ちてきたとはいえ、入浴時にタオルでごしごし擦るのも美月には異性に接する楽しみの一つでもあった。
悠真は大皿に盛られたパエリアを米粒一つ残さず平らげて、満足した様子で「美味しかったよ。レストランの味だったね」とほめちぎった。普段、悠真は美代子との会話が少ないので、食事時三人が顔を合わせ、とりとめのない会話がお互いの絆を確かめるいい機会だった。まして美代子の手料理を食べるなんて想像もしていなかったから、余計、口数も多く華やいだ食事時になった。