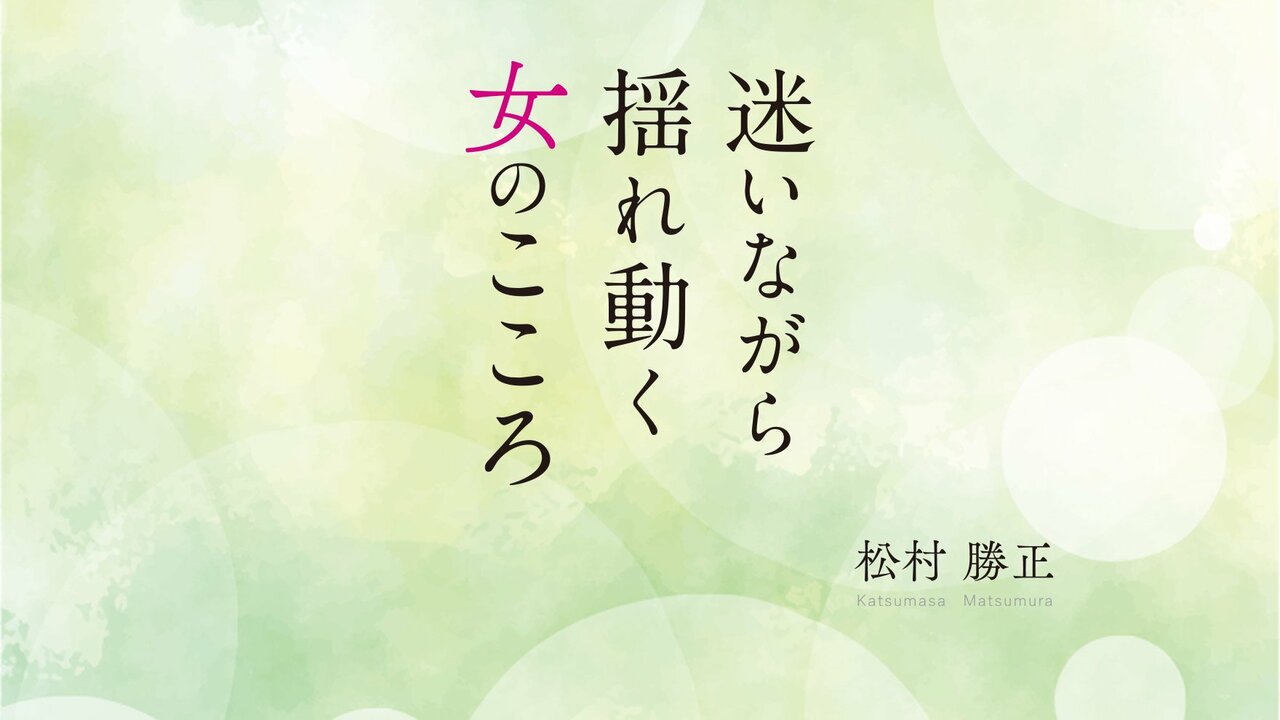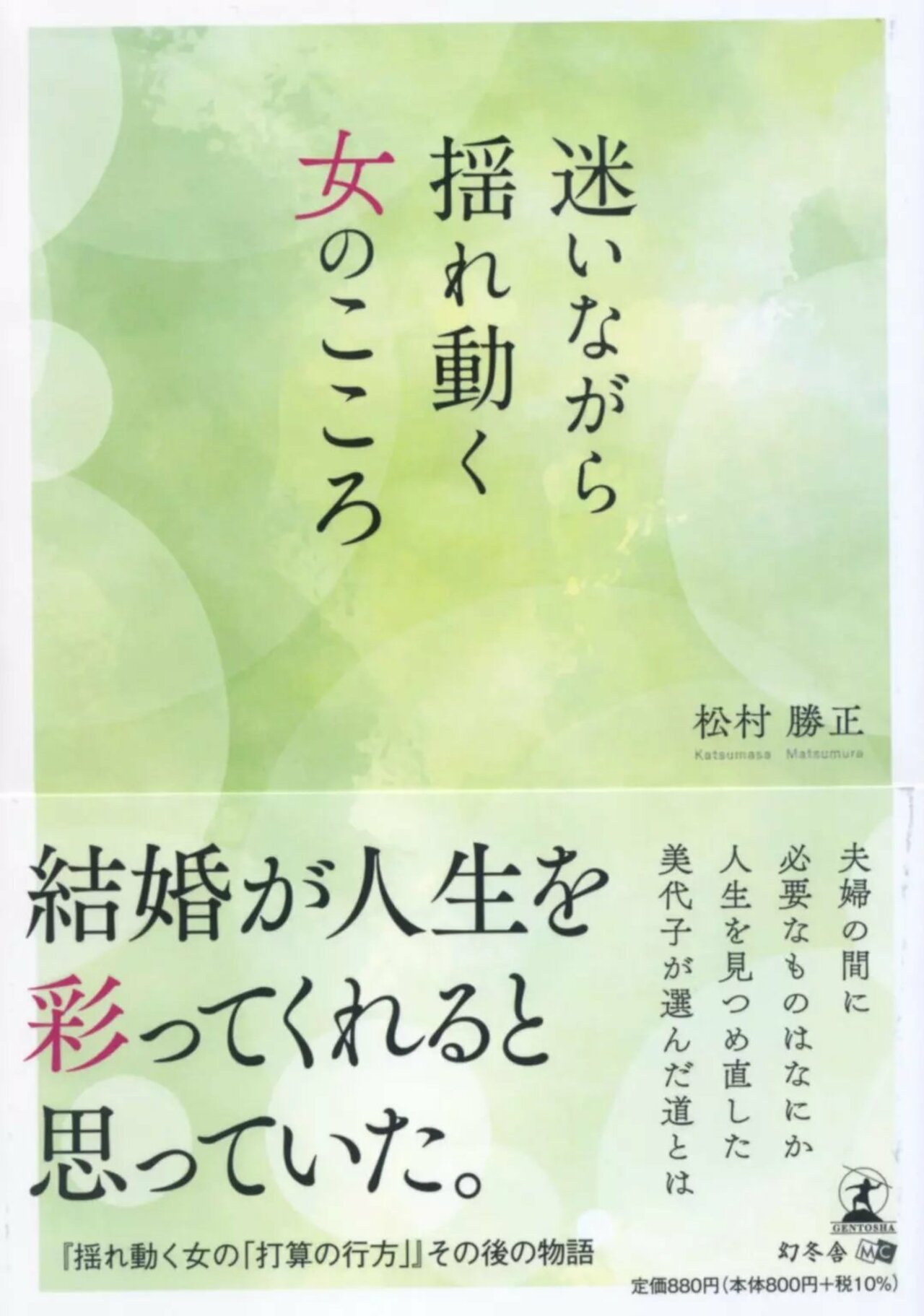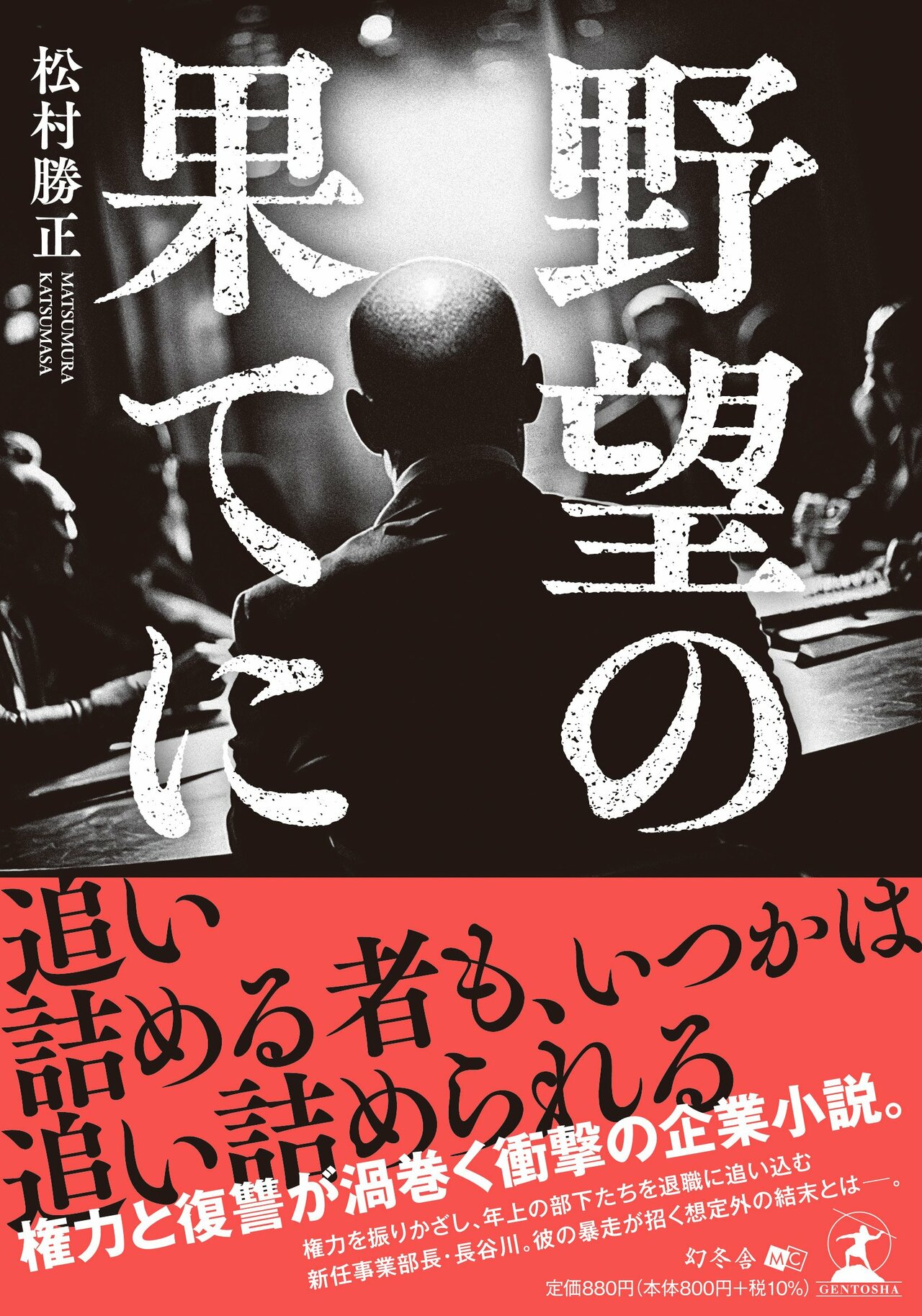迷いながら揺れ動く女のこころ
四方八方から飛び交う市場独特の掛け声や買い物客たちの行き交う足音で、二人はしばらく無言でいた。市場の入り口に差し掛かった所で、美代子が「美月さんは毎日大変ね。私、昨日主人の入浴介助をしたでしょう。初めは軽く考えていたのね。でも無理だと悟ったわ。やはり美月さんにお願いします」と軽く頭を下げた。
「長い時間かかっていたもんね。介護の仕事は一時の思い付きで出来るほどそんなに簡単ではないからね。私も山形家に家政婦としてお世話になった当初は失敗の連続でした」
「昨日はシャワーヘッドの扱いで、私がお湯を浴びてしまったの」と時間がかかった一端を話した。
美月は美代子が入浴介助をギブアップしたことで、自分の役割の存在を認めてもらったことを嬉しく思った。昨晩は二十年余り、悠真さんの介助をしてきて、仕事を奪われてしまったことでいささかショックを受け、美代子達が入浴介助の間、風呂場の方角に耳を傾けながら気にしていた。
主人に対しては、家政婦としてお世話になったときから姉弟の関係で特に仕事と割り切り、異性を意識することはなかった。しかし昨晩、初めて悠真夫婦の存在が気になり、美代子に対する小さな嫉妬心が芽生えた。
美代子は介助の仕事を美月に返すことにしたことで、何か重い重しが取れたように、晴れ晴れとした表情になった。
「美月さん、今晩はびっくりするくらいの本場のパエリアを作りましょう。正直なところ私は結婚前もほとんど台所に立ったことが無かったの。でも、味覚には自信があります。会社勤務時代から友人と美味しい料理を食べ歩いていましたから。先日パソコンでパエリアのレシピを“本場のパエリア”で検索して、大事なポイントはメモに取りました」
話を聞いていた美月は「羨ましいですね。私なんか福島の片田舎だから、美味しい料理を食べ歩くことなんか夢のまた夢でした」と少し美代子の方を見て、すねた顔をして見せた。
「ごめんなさい。そんなつもりで言った訳じゃないんです」
「分かってますよ。でも東京での外資企業勤務に憧れますね」
美月は自分が高校生の時に両親が亡くなり、肩身の狭い生活を強いられたことなど、話すことが辛かったのでこれまで封印してきた。美代子とは生活環境も違いすぎるので、過去を思い出すことが自分を生んでくれて、一生懸命生きた両親に対して申し訳ない気持ちで一杯だった。
瞼を閉じて、何かを思い出すように、数秒間の沈黙を要した。小中学生の少女時代を過ごした福島の田舎の風景が、秒速で浮かんできた。一人っ子だったので両親は愛情たっぷりと接してくれて、いつも食事時には笑いが絶えない毎日だった。
美月はどうしてか子供の時を過ごした幸せの絶頂期しか思い浮かばない。両親が病弱だったので、高校三年生の時、相次いで亡くなったときは、あまりのショックで涙も出なかったことを覚えている。溺愛してくれた両親の死を受け入れることが出来ず、今日までことあるごとに両親と会話している自分がいて、寂しく思ったことはなかった。