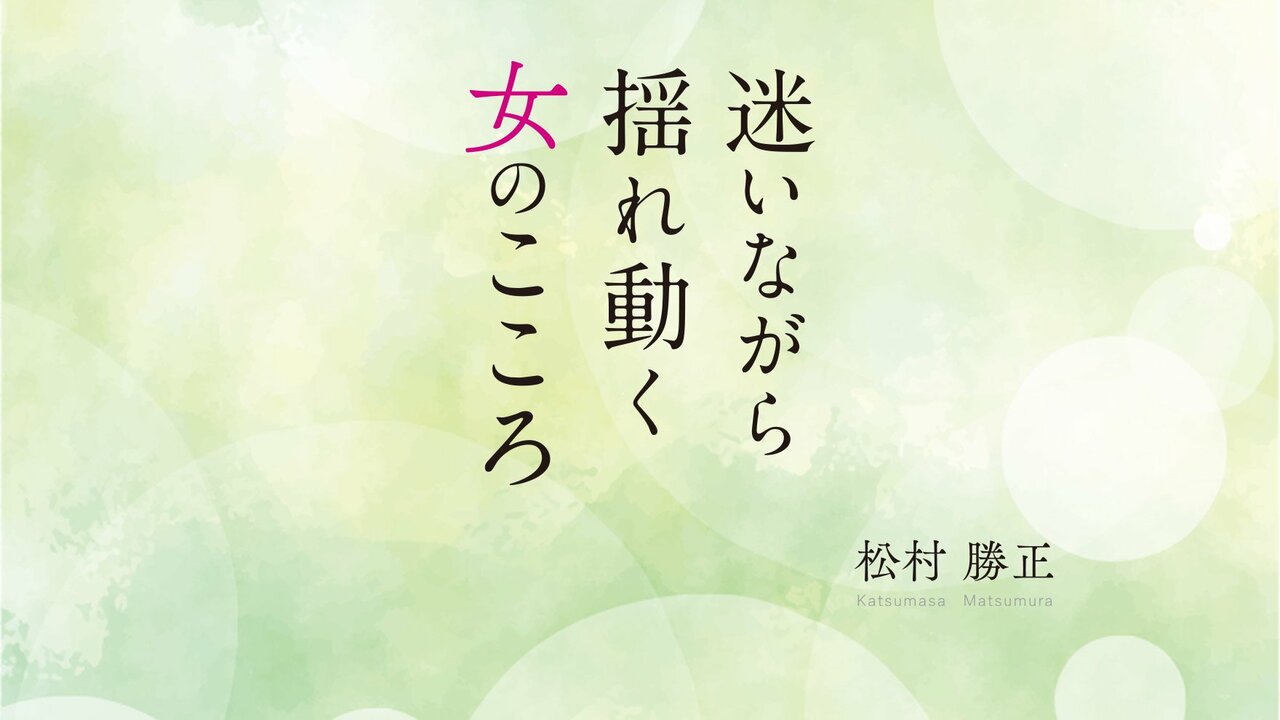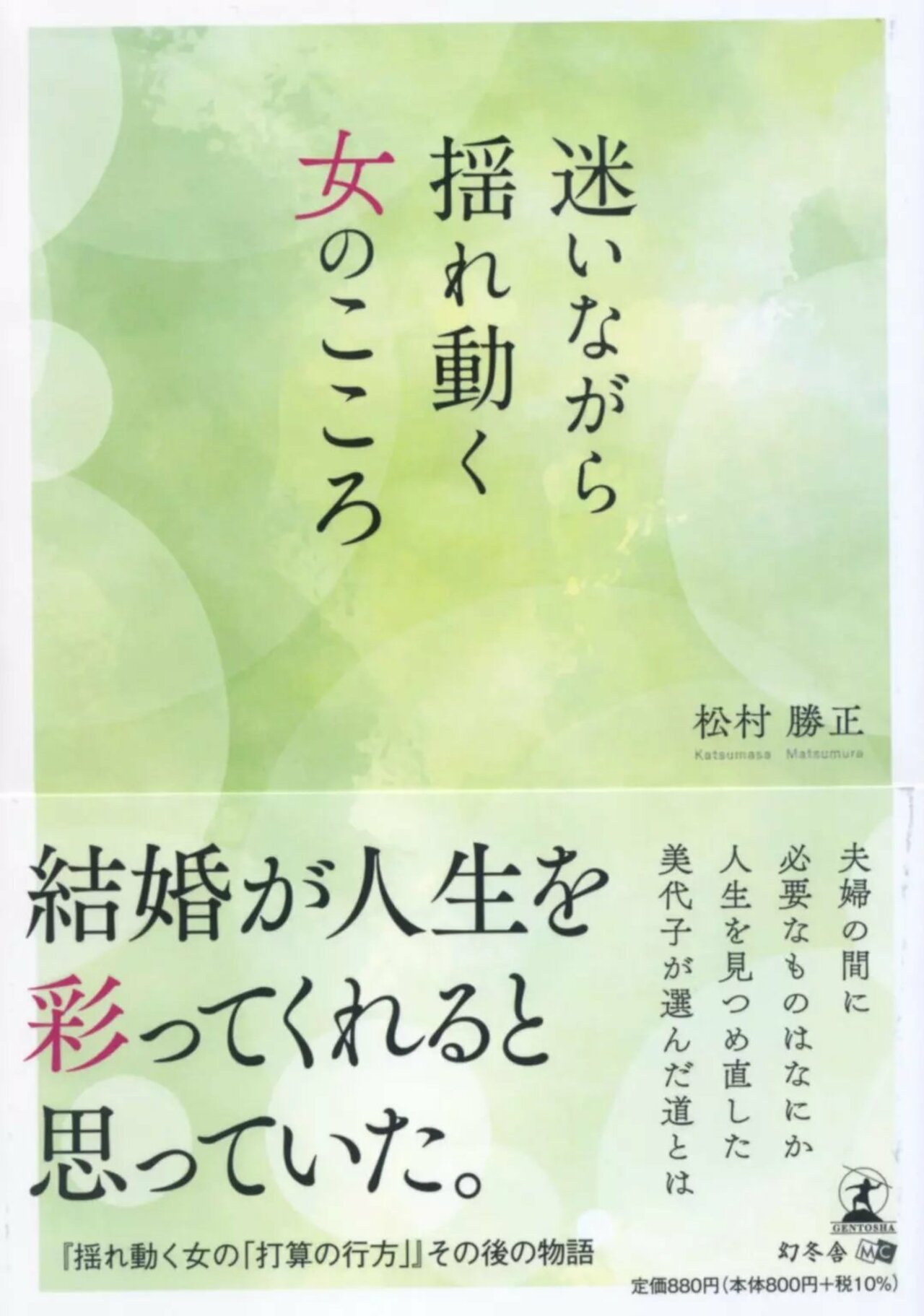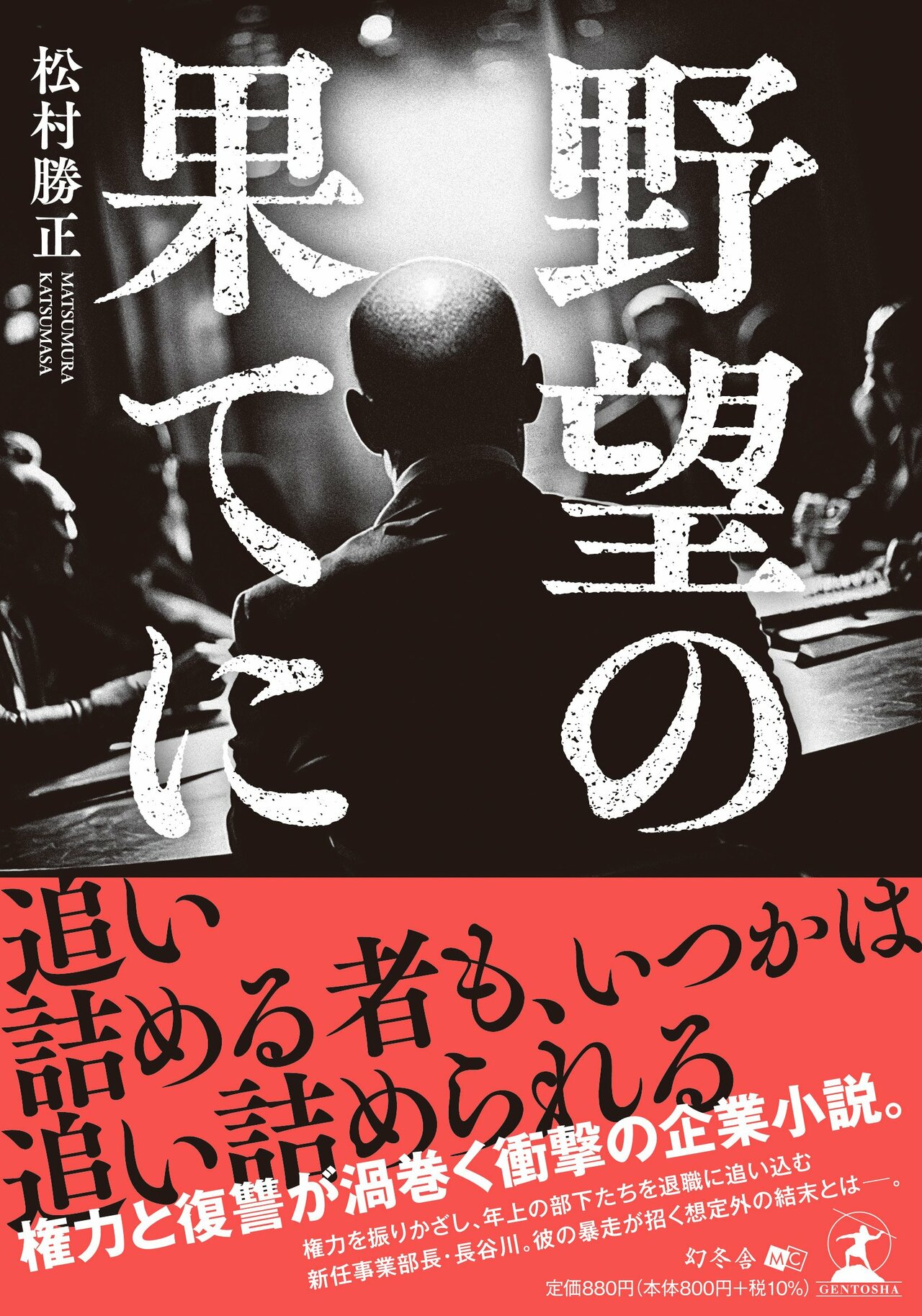迷いながら揺れ動く女のこころ
風呂場の外から「大丈夫ですか」という美月の声がした。
美代子は風呂場のドアを少し開けて
「何か?」
「いや、あまりにも長い時間経っていたので、つい心配になりました。大丈夫? 代わりましょうか?」
「すみません、何しろ慣れないものだから。もうすぐ上がります」と慌てて返答した。
悠真が「美月が心配したんだね。彼女は毎日のことで慣れているから素早いんだよ。それに今日は美代子がシャワーヘッドのお陰でびしょ濡れになったから、まさか美月は君が一緒に風呂を使っていることなど、知らないからね」
「美月さん、変に思っていないかしら。介助だけならすぐ終わると思っていたでしょうから」
「何も気にすることはないよ」
美代子は悠真を浴槽から車いすに移動させ、素早く身支度を済ませて自室に戻った。部屋に戻るなり、ベッドにうつ伏せに倒れ込むように体を投げ出した。
しばらくの間、時計が止まったように時が流れた。美代子は夢の中にいた。
大学を卒業して、入社した英国資本の海運会社で、夏の一日をワゴン車二台に分乗して、会社の同僚十二名で千葉の内房海岸で遊んだ時を思い出していた。独身の男女は皆、眩しいぐらい輝いていた。
普段職場では、挨拶程度で会話をしたことが無い男性も参加していて、解放された夏海の砂浜でバーべキューをしながら、笑い転げている面々が浮かんできて、すぐに場面が切り替わり、マザコンの健吾も美代子の側にいた。
その時ハッとして目が覚め、浅い眠りについて夢を見ていたことに気が付いた。おもむろにベッドから起き上がりデスクの上に置いてある小さな鏡を見た。入浴介助で普段使わない筋肉を使ったせいで、両方の肩が少し重く感じ、自分で両肩を軽くもんでほぐした。
それより、美代子は気になることがあった。美月が風呂場で「大丈夫ですか」と呼びかけたことだった。
美月が山形家に家政婦として来てから二十年、介助の仕事は美月の持ち場で誰も侵害しない仕事と自負していたこと、それを美代子の気まぐれで奪われたことに対する嫉妬心ではなかったか。
自分が主人に対して何かお世話するということが美月の心を傷つけたのではないかと思い始めていた。
今日一日やってみて、自分には到底無理だと分かったから、明日美月さんとパエリアの食材を買い出しに行った時に話してみようと思い、これ以上深く考えないことにした。