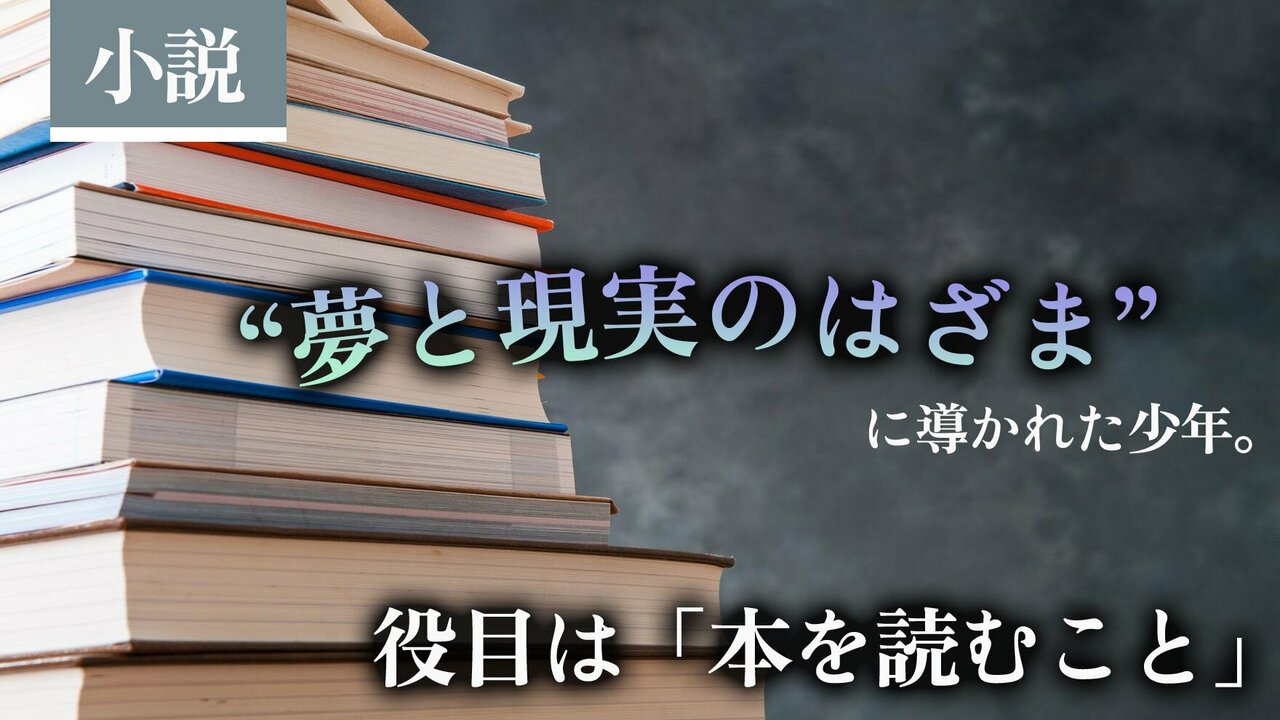僕は、今まで人の目を気にして生きてきた。両親の記憶はほとんどない。気づくと、僕は施設にいた。唯一ある思い出が両親からの虐待だとわかったのは、中学生に上がる頃だった。
施設でもいじめを受けていたこともあり、今では相手の表情ひとつで何を考えているのかわかるようになった。
間違いない。エドワードは何かを隠している。僕の脳内で、サイレンが鳴っている。今は、彼を信用してはいけないと。
「では、僕の役目が“本を読むこと”なのはなぜなのですか?」
「それは、君が真っ先に本を手に取ったからだ。ここの本は、誰もが夢中になって読めるわけではない」
彼は、そこでコーヒーを一口含んだ。
「誰もが長所と短所を持っている。長所を伸ばす方が効率的で、人生も生きやすくなるだろう?」
そう言って、真っ直ぐ僕を見た。確かに、長所を伸ばして活かす方が、きっと効率は良いのだろう。しかし、長所だけでは生きていけないのが現実だ。
僕は、お互いのコーヒーカップを見つめた。二人のコーヒーカップは、すでに空になっていた。
「おかわりでもどうだね?」
「いただきます」
なんとなく、お互い微笑み合った。
まだまだ謎は残るけれど、少し一歩を踏み出したような気がした。とりあえずは、コーヒーの香りに酔いしれることにしよう。どれぐらいの時間が経ったのだろうか。エドワードが立ち上がった。
「私は、今から少し出かけないといけない。君は、ここで本を読んでいたまえ。なぁに、ちょっとした買い物だ。誰かが来ても、気にしなくて良い」
「わかりました」
彼は微笑むと、颯爽とジャケットを肩にかけ、扉を開けて出て行った。