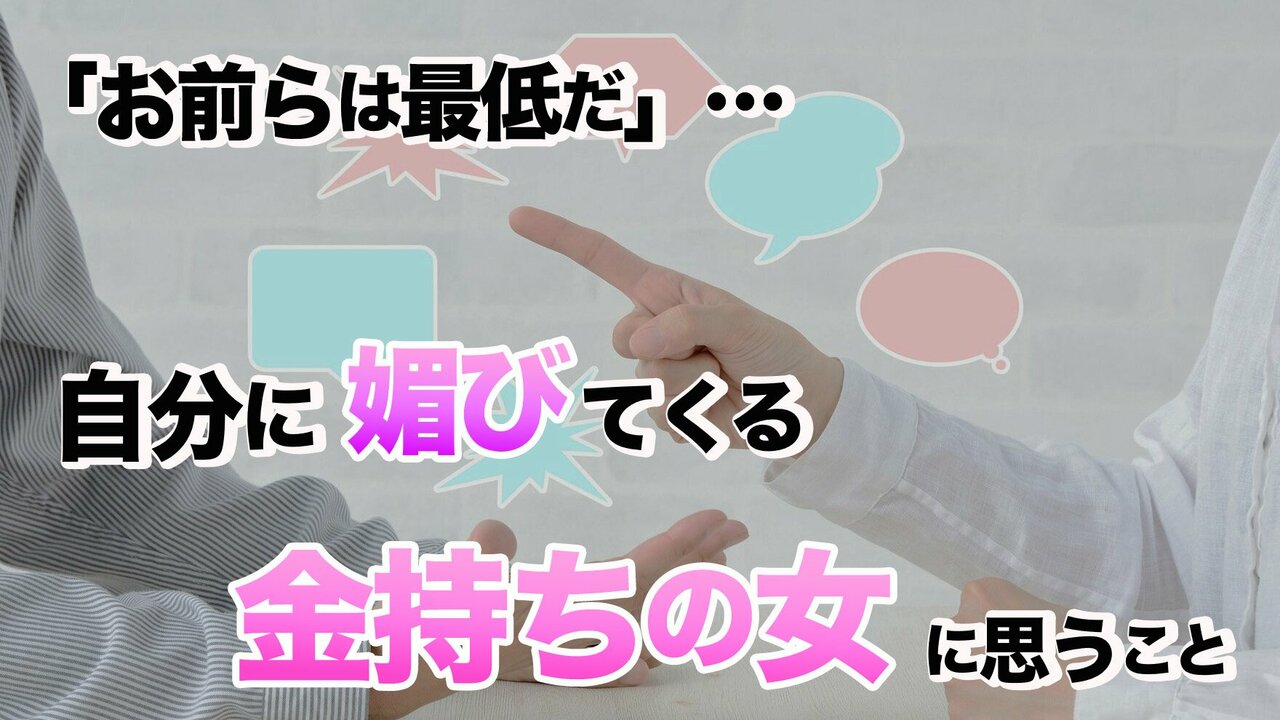ひるあんどん
新村は人当たりがよく、上手く人を動かす。この頃は、脚本と一緒に、テレビの監督にも手を出し始めたようだ。シナリオ教室もそれなりに流行っているんだろう。しかし、根はお人好しで、それほどあこぎには出来ないから、ワリを喰うことも多いらしい。
国道に出ると、歩道にさっきの高城が立っていた。派手な赤い外車が高城の前に止まって、女が顔を出し、高城が乗り込んでいくのが見えた。
細い路地を曲がると薄闇が戻り、喧噪が静寂に入れ替わる。高等遊民か。確かにあの家もりょうの父親の別荘だ。やはり、木戸から入るのが自分には似合いなんだろう。
さっきの居酒屋の匂いが身体から漂った。
ふいにあの居酒屋は本当にあったんだろうかと思った。若い頃からこんな感覚があり、これに襲われると居場所をなくしたような気分になる。サルトルの『嘔吐』を読んだ時、主人公が覚えた外への違和感は、これと似た感覚なんだろうと味方を得た気がしたが、サルトルはこの違和感を煮詰めて哲学に高めた。凡人の自分は煮詰めるどころか、感覚のままで、今もうろついている。
そんなことを父に言ってみたら、それは一種の神経症かもしれません。私にも外への違和感があります。現実よりスクリーンの中のほうが好きですからと答えた。
父は弁士だった。映画を作る才能はないが、伝える才能はあるから弁士になったのだそうだ。なって良かったかと聞くと、続けているから多分そうなんでしょうと、他人事のように言った。
父はそれなりに名の知れた弁士で、スクリーンを見ながら、饒舌に情感豊かに、映画の中で繰り広げられる人生を自分の人生のように生き生きと解説した。普段無口な父とは別人のようだった。父は自分の人生を他人事のように生きた気がする。そして子供にも、犬のトムにも、誰にでも敬語を使った。父の敬語は、馴染めない現実から自分を守る一種の防波堤のようなものだったのかもしれないと、この頃思う。
空を見上げると月があった。上弦の月だ。
「上弦は上が欠けてる。下弦は下だ。言葉と反対だ。しかし、月が昇った直後と沈む直前では、この月の上下は逆になる。ただ、人間の生活時間帯に見える形をそう言うだけだ。それと上下は、上旬と下旬。したがって上弦は上旬。下弦は下旬に出る」
逆になるのが面白いと思って、なんとなく覚えている。死に神とあだ名のあるあの痩せた理科の教師は、片方の肩が下がっていた。結核で肋骨を何本か取ったせいだという噂だった。教師はいつも、窓の向こうの校庭を見ながら授業をした。生徒のほうを見ることはあまりなかった。見たとしても視線は人間を素通りするように流れた。
あの教師も久と同じ違和感を世間に持っている気がして、嫌いではなかった。月の横に星が一つある。寄り添っているように見えるが、あの間には膨大な距離があるのだ。
遠くで波の音がした。歩くたび、月と星が一緒について来る。自然はただあるだけで、何も語らない。断末魔、蝉の声は、一声だった。