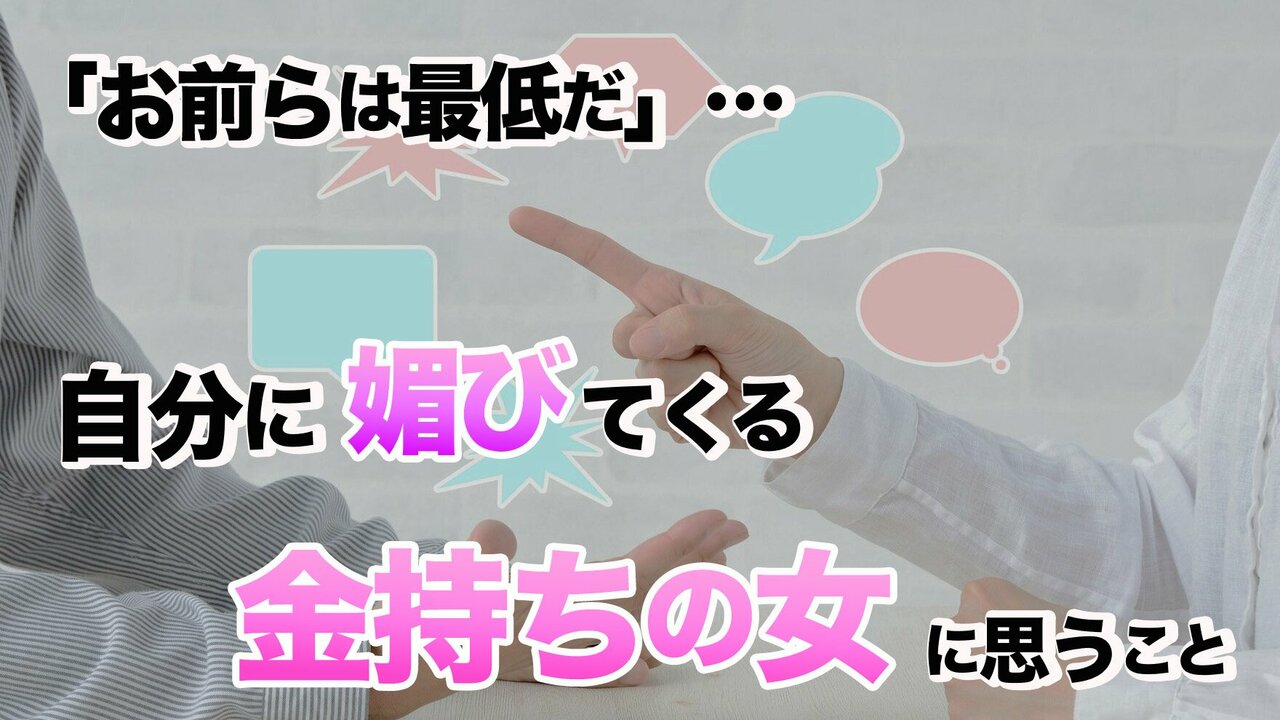2020年 夏の風子
「ふうちゃん、相くんの食事、お願いします!」
同僚の真野さんが園児の食事を食べさせながら怒鳴った。多動症のはじめくんが叫びながら駆け回っているので、どうしても職員たちの声は大きくなりがちだ。体温調節が上手く出来ない相助は小さな身体に毛布を巻きつけ車椅子にちょこんと座っている。滅菌消毒をもう一度丁寧にし、風子は車椅子の相助の前に座った。
相助は他の子より身体が弱くちょっとのことですぐ体調を崩すので、特に気を使う。
「さぁ、相くん、ご飯、食べますよー」
相助が顔を歪めながら、細い首を小さく振った。拒否の意味だ。彼は食欲がない。エプロンをつけさせてゆっくり流動食を相助の口に持って行くが、匂いが気になるらしく、顔を曇らせ、口を開けようとしない。
相助は絶えず細かく動いていて口の開きも小さいから、食べ物を口に入れるだけでも、一苦労だ。それでも食べさせるのは、食べさせないと口の機能や飲み込む力が落ちるから。相助の食事は訓練の一種でもある。
風子は弟の幸多で慣れているから、ということで、食べさせにくい相助の食事を担当することが多いのだが、食欲があり過ぎるほどあった幸多と相助では、勝手が違う。
「さあ、食べようね」
考える隙を与えず、口に入れるのがコツ。こちらの迷いや焦りが相手に伝わると、悪循環になる。相手の反応を気にしないで、淡々と。
「お口を動かすよ。よいしょよいしょ。運動です」
目を見ず機械的に。風子自身が口を動かして、それに相助が気を取られて、口の力が抜けた瞬間にほんの少しの流動食を流し込む。飲み込んだら目を合わせ、笑ってほっぺをぽんぽん。
今日の相助はいつもより飲み込むのが早い。吐き出すこともない。
「上手上手、すごいねえ」
相助の口が動き、少しずつ、彼の体内に血肉になる食べ物が落ちていくのを見ながら、ほっとすると同時に、罪悪感に似た何かが胸をよぎる。
相助にとって食べることは苦痛ですらあるらしい。その彼の意思に関係なく、ひたすら食べることを強要するような介護士の時間。構築するすべのない時間。自分はこの仕事に向いていないのかもしれないと思う瞬間だ。
「次はしんちゃん、お願いします。しんちゃんは吹きこぼすから。これ敷いて」
真野さんが古新聞を渡した。新聞を広げてテーブルに敷いた時、死亡欄が目に入った。
「脚本家、山下久氏、享年九十」
山下先生が死んだ? いつ? 二〇一六年。四年前の新聞だ。
喪主は養子の真さん。ということは、奥さまのりょう先生はその前に亡くなっているということか。
幸多と逗子の先生の家に行ったのはもう二十年以上も前になると、窓辺に立っている幸多の大きな尻や丸い肩を見ながら、風子は思った。
あの時、幸多は十二歳。風子は十九、専門学校に通っていた。今、幸多の背丈は百七十センチをゆうに越えている。あの前もあの後もずっとこの幸多と一緒に生きて来た。