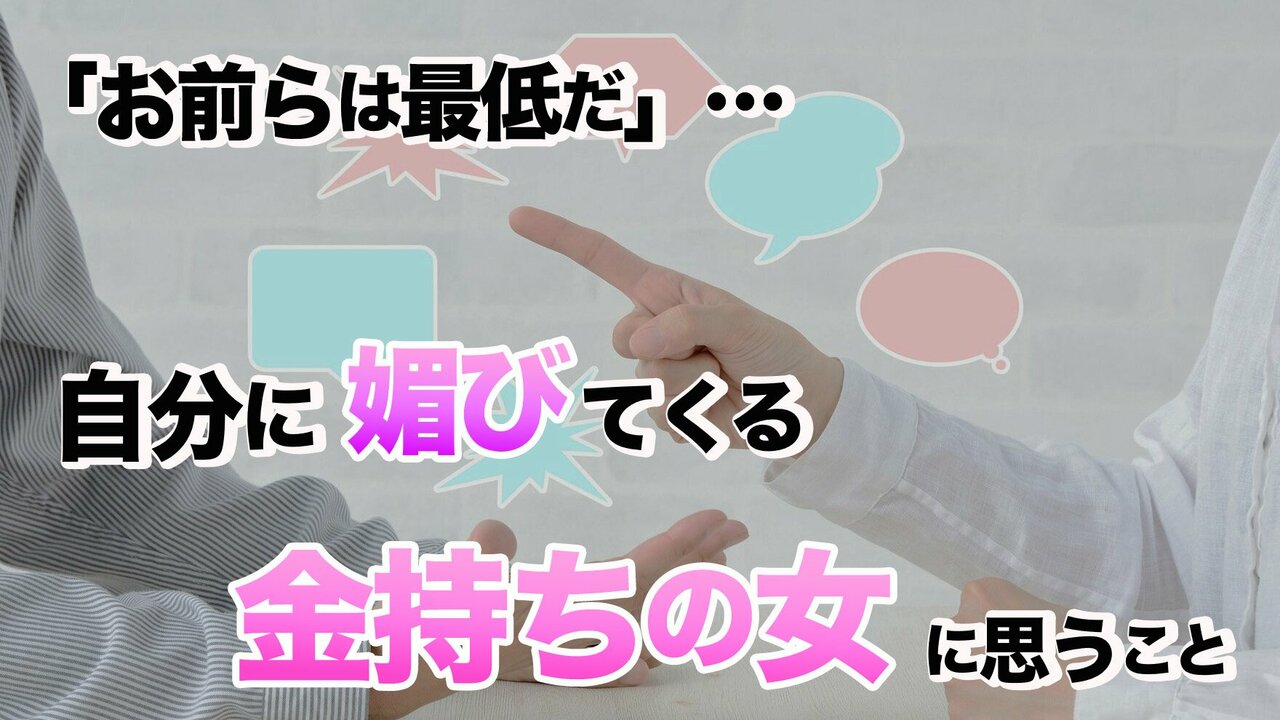蝉の寝言
木戸が大きな音を出す。それを押しとどめる気分でそっと閉めて、玄関の戸を開けると、りょうが立っていた。
「よく分かったね、勘か」
「計算です。電車、何本もありませんから」
それもそうだ。
「やりましたね」
「うん。でも、後悔する手のことじゃない」
それならいいというように、りょうがお茶飲みますかと言った。
いらないと答えて仕事場に戻りながら、新村の言う通り、勘のいい女房も疲れると思った。
部屋に入り、明かりをつけないまま暫くじっと椅子に座ったままでいた。闇の音がする。いや、これは闇の音ではなく、耳の中の音だ。自分の中から湧いてくる音。怒りは鈍い痛みのようにまだ収まらない。
切り替えようと明かりをつけ、机に向かったが、何も浮かばない。
諦めて立ち上がり、大きく窓を開けた。小さな月があった。樹の影が月明かりにぼんやりと浮かび上がっている。池の水が月光を弾いて光った。月の光を浴びて、あの時光ったのは……。
首を振り眉を寄せ、記憶を振り払おうとしたが払えない。渡辺だ。今、自分はあいつと同じ目をしているだろう。暴力と暴言の違いはあっても、あいつと同じことを自分はしたのかもしれない。あれを暴言とは思わないが、正論も振りかざし過ぎると人を傷つける。
自己嫌悪で喉が渇いて、りょうに茶を入れて貰えば良かったと思った。
「やっぱり、飲みたいと思ったでしょ」湯飲みを持って、りょうが入って来た。
「夜だからほうじ茶です。少し熱めにしてあります。熱いほうが身体にはいいんですよ」
茶の香りが鼻の先で揺れ、それを含むように一口飲んだ。
「旨い」
りょうが自分の描く絵本の中の少女みたいな笑顔を見せた。開けた窓の外から、ジジッと焼かれるような短い蝉の声がした。
「あれは蝉の寝言です」りょうが言った。