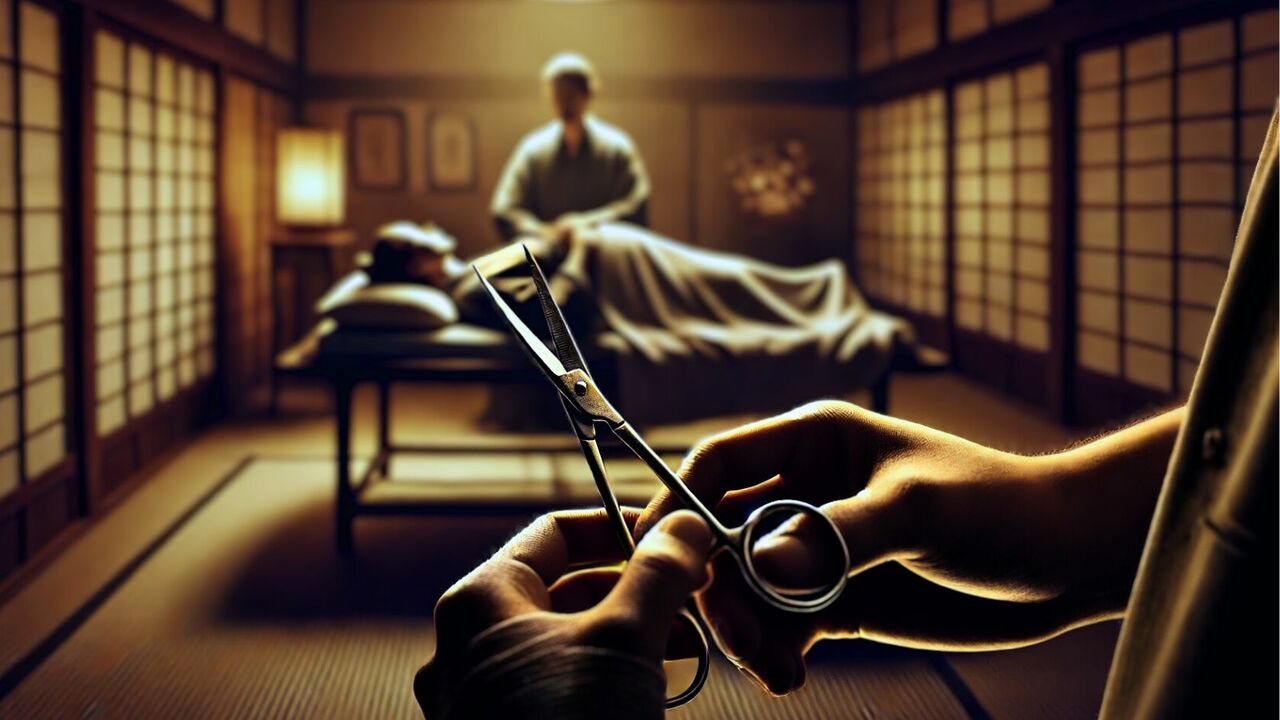「ベルツ先生が診たそうだ。どうやら心臓病らしいな」
するとそれまで、ずっと蚊帳の外だった森 林太郎が、おずおずと会話に割って入ってきた。
「あのう……、少々よろしいでしょうか?」
「どうした?」
「ベルツ先生は、お元気でしょうか?」森と大御門は、二人とも医学生時代にベルツに学んだことがあったのだ。
「ああ。ますますご活躍されている。この調子なら、あと二十年くらいは日本で頑張ってもらえそうだ」
しかし万条は、すぐに焦った顔で話を戻した。
「それで、新島先生は大丈夫だったのか?」
新島襄のこととなると、やはり放ってはおけなかったからだ。明治八年、新島は京都で同志社英学校を開学した。最近、大学設立の旨意を起草し、大学昇格を狙っているとのことで、同じ京都の学校として、万条も関心を寄せていたのだ。
「命には別状なかったが、当分の間、静養が必要ということだった」
「そうだったのか……」
ようやく万条は、ほっとした。何も知らなかったからだが、そのあと思わず独りごちた。
「それなら、京都にいる間は、安妙寺に任せておけばいいか……」
「安妙寺?」大御門が懐かしそうな顔で繰り返した。
「あいつは、今、どうしている?」
安妙寺一久もまた、万条と大御門の共通の幼なじみだった。三人とも近くに住んでいて、飛鳥井邸での蹴鞠事件のときにも居合わせていた。
「去年、医院を新島先生の家のすぐそばに移転したそうだ。相変わらず抜け目なくやっていて、けっこう繁盛しているみたいだぞ」
「ほう……。昔からあいつは、面倒見が良かったからな」
大御門が納得すると、万条は冗談めかして付け加えた。
「しかも患者が亡くなると、寺で働いている親父を呼んで、葬式の世話までしてやっているらしい──」
「なるほど!」
大御門が膝を叩いた。そしてしみじみと言った。
「坊主と医者は、昔から持ちつ持たれつの間柄だしなぁ……」